お知らせ
子どもみらい類型
子どもみらい類型
教育入門Ⅰ「演劇実習②」
1/24(火)3・4限 今回の教育入門Ⅰは、先週に引き続き演劇実習です。今回も中畑八郎先生にご指導いただきました。
最初に、前回の振り返りと注意がありました。「受け身にならず、積極性を持つことが大事」だと強調されました。演じることにとどまらず、人生の全ての場面に通じる言葉だと感じました。
続いては、演じることについての講義です。テレビの「報道」と「バラエティー」を引き合いに出しながら、真実を見抜く目を持つことが大切であると話されました。また、文化についても触れられ、「文化とは社会・人生のゆとりであり、ゆとりは遊び心につながる、ゆとりが社会生活を円滑にする」と語られました。
後半は表現練習です。状況に応じた表現練習にはじまり、ジェスチャーゲームやコミュニケーション練習を行いました。中でも、ジェスチャーゲームでは、「公園で阿波踊りをする猿」や「化粧をする私のお姉さん」「お風呂の後でアイスを食べる弟」「お父さんのいびきで起きたお母さん」などのお題が出され、生徒達は四苦八苦しながらも表現を楽しんでいました。中畑先生は、恥ずかしさからなかなか演じたがらない生徒にも、「まずはやってみる努力をする」ことの大切さを説かれ、生徒もそれに応えようと一生懸命頑張っていました。
最後に2回の講座のまとめとして、人間観察することの大切さを話されました。将来教師をめざす生徒達に、「子どもの興味ある話題を提供しようと思うと人間観察が必要です。人間観察をすると人の心がわかるようになり、想像力が広がります。そうすると知識も豊富になります。」と熱く語られました。
「努力しないといい先生にはなれません。学校に行くのは資格を取るためです。受け身にならず、積極的に努力することで、必ずいい先生になれます。いつか近い将来、保育園や幼稚園で皆さんとお出会いしたいと思います。その時にはいい先生になっていて下さいね。」現在も市内各地の幼稚園や保育園、児童クラブなどで人形劇をされている中畑さんからのメッセージでした。
最初に、前回の振り返りと注意がありました。「受け身にならず、積極性を持つことが大事」だと強調されました。演じることにとどまらず、人生の全ての場面に通じる言葉だと感じました。
続いては、演じることについての講義です。テレビの「報道」と「バラエティー」を引き合いに出しながら、真実を見抜く目を持つことが大切であると話されました。また、文化についても触れられ、「文化とは社会・人生のゆとりであり、ゆとりは遊び心につながる、ゆとりが社会生活を円滑にする」と語られました。
後半は表現練習です。状況に応じた表現練習にはじまり、ジェスチャーゲームやコミュニケーション練習を行いました。中でも、ジェスチャーゲームでは、「公園で阿波踊りをする猿」や「化粧をする私のお姉さん」「お風呂の後でアイスを食べる弟」「お父さんのいびきで起きたお母さん」などのお題が出され、生徒達は四苦八苦しながらも表現を楽しんでいました。中畑先生は、恥ずかしさからなかなか演じたがらない生徒にも、「まずはやってみる努力をする」ことの大切さを説かれ、生徒もそれに応えようと一生懸命頑張っていました。
最後に2回の講座のまとめとして、人間観察することの大切さを話されました。将来教師をめざす生徒達に、「子どもの興味ある話題を提供しようと思うと人間観察が必要です。人間観察をすると人の心がわかるようになり、想像力が広がります。そうすると知識も豊富になります。」と熱く語られました。
「努力しないといい先生にはなれません。学校に行くのは資格を取るためです。受け身にならず、積極的に努力することで、必ずいい先生になれます。いつか近い将来、保育園や幼稚園で皆さんとお出会いしたいと思います。その時にはいい先生になっていて下さいね。」現在も市内各地の幼稚園や保育園、児童クラブなどで人形劇をされている中畑さんからのメッセージでした。
次回は1月31日、小学校実習の事前指導として、三田市教育委員会の福本八重歌先生にご指導いただきます。
教育入門Ⅰ「演劇実習①」
1/17(火)3・4限 今回の教育入門Ⅰは、演劇実習です。三田市在住の脚本家・演出家で、「三田演技塾」の塾長、中畑八郎先生にご指導いただきました。
まず、生徒全員に「どんな先生になりたいか」と問われ、教室全体に聞こえるようにハキハキ大きな声で、語尾までしっかり声を出すよう指導されました。
また、「自分の魅力は何ですか」と問いに関連して、「動物か花の名前を入れて自己紹介しなさい」という指示がありましたが、生徒からは「顔がリスっぽい」等のユニークな回答もあり、楽しく活動することができていました。
中畑先生の言葉の中で印象的だったのは、「良い先生に、好印象の残る先生になって欲しい(=有名になって欲しい)。有名な人の言葉には重みがあり、信用もされる。有名になるために、早く自分の長所を見つけて、磨いて欲しい。」という言葉です。話し方の指導が中心でしたが、中畑先生の人生論、教師論がうかがえました。
次回は演劇実習の2回目です。中畑先生による「アクセントをつけた話し方などの実践練習」を予定しています。
まず、生徒全員に「どんな先生になりたいか」と問われ、教室全体に聞こえるようにハキハキ大きな声で、語尾までしっかり声を出すよう指導されました。
また、「自分の魅力は何ですか」と問いに関連して、「動物か花の名前を入れて自己紹介しなさい」という指示がありましたが、生徒からは「顔がリスっぽい」等のユニークな回答もあり、楽しく活動することができていました。
中畑先生の言葉の中で印象的だったのは、「良い先生に、好印象の残る先生になって欲しい(=有名になって欲しい)。有名な人の言葉には重みがあり、信用もされる。有名になるために、早く自分の長所を見つけて、磨いて欲しい。」という言葉です。話し方の指導が中心でしたが、中畑先生の人生論、教師論がうかがえました。
次回は演劇実習の2回目です。中畑先生による「アクセントをつけた話し方などの実践練習」を予定しています。
教育入門Ⅰ 「民話絵本の制作」
11/29(火)3・4限 今回の教育入門Ⅰは、民話絵本の制作です。ボランティアサークル「さんだガイド塾」の方々にもご指導いただきました。
夏休み中の課題で調べていた三田市の民話を元にして絵本を作成します。10月から、「くわばらくわばら欣勝寺」など13作品の制作に取りかかり、今回やっと絵付けが始まったところです。
三田市の民話研究をされている「さんだガイド塾」の方が生徒に対して積極的に声かけをしていただき、それぞれの民話についての由来や解釈などを話していただきました。生徒達は2時間連続の作業だったにも関わらず、とても熱心に取り組み、ゴールが見えてきたグループもあります。何とか冬休み前には完成したいと思います。
出来上がった絵本は宮城県東松島市の大曲小学校・大曲保育所に贈る予定ですが、「さんだガイド塾」にも利用していただき、三田市の民話を紹介するお手伝いができればと思っています。
授業終了後は、「さんだガイド塾」の7名の方々と生徒達が一緒にお弁当を食べました。食事中も民話について熱く語られるガイド塾の方の生き生きとした表情がとても印象的でした。
夏休み中の課題で調べていた三田市の民話を元にして絵本を作成します。10月から、「くわばらくわばら欣勝寺」など13作品の制作に取りかかり、今回やっと絵付けが始まったところです。
三田市の民話研究をされている「さんだガイド塾」の方が生徒に対して積極的に声かけをしていただき、それぞれの民話についての由来や解釈などを話していただきました。生徒達は2時間連続の作業だったにも関わらず、とても熱心に取り組み、ゴールが見えてきたグループもあります。何とか冬休み前には完成したいと思います。
出来上がった絵本は宮城県東松島市の大曲小学校・大曲保育所に贈る予定ですが、「さんだガイド塾」にも利用していただき、三田市の民話を紹介するお手伝いができればと思っています。
授業終了後は、「さんだガイド塾」の7名の方々と生徒達が一緒にお弁当を食べました。食事中も民話について熱く語られるガイド塾の方の生き生きとした表情がとても印象的でした。
幼稚園・保育園実習⑥
11/22(火)3・4限 6回目の幼稚園・保育園実習を行いました。今回の実習で幼稚園・保育園実習は最後になりました。
6回の現場実習で生徒達は大きく成長しました。6月に初めて行った実習では、午睡の寝かしつけで一緒に寝てしまったり、目の前でいきなりけんかが始まってうろたえてしまったり、何かある度にどうしたらいいのか分からず立ちすくむ姿が目立ちましたが、今回の実習では、園児達の楽器の練習の際に、手拍子で先生と一緒に指導していたり、子ども同士のトラブルにもそれなりにうまく対応できるようになっていました。
実習後、各園で園長先生から6回の実習を振り返ってアドバイスを受けました。「人と接する時は、その人の世界に入ることが大切です。自分のペースではなく、相手のペースに入ってみると、その人のことが分かってきます。」「どのような場面でもポジション取りをしっかりして下さい。どの角度から見れば先生の動きや子どもの活動が良く見えるか意識して下さい。」など、数々の貴重なアドバイスに、生徒達もうなずきながら聴き入っていました。
6回の現場実習で生徒達は大きく成長しました。6月に初めて行った実習では、午睡の寝かしつけで一緒に寝てしまったり、目の前でいきなりけんかが始まってうろたえてしまったり、何かある度にどうしたらいいのか分からず立ちすくむ姿が目立ちましたが、今回の実習では、園児達の楽器の練習の際に、手拍子で先生と一緒に指導していたり、子ども同士のトラブルにもそれなりにうまく対応できるようになっていました。
実習後、各園で園長先生から6回の実習を振り返ってアドバイスを受けました。「人と接する時は、その人の世界に入ることが大切です。自分のペースではなく、相手のペースに入ってみると、その人のことが分かってきます。」「どのような場面でもポジション取りをしっかりして下さい。どの角度から見れば先生の動きや子どもの活動が良く見えるか意識して下さい。」など、数々の貴重なアドバイスに、生徒達もうなずきながら聴き入っていました。
6回の実習を通して、どの園でも温かく生徒達を迎えていただきました。生徒達はますます子どものことが好きになりました。また同時に、将来の夢への思いをいっそう強くしました。お世話になった幼稚園・保育園の先生方に、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
次回の教育入門Ⅰは、民話絵本の制作です。ボランティアサークル「さんだガイド塾」の方々にご指導いただく予定です。
幼稚園・保育園実習⑤
11/15(火)3・4限 5回目の幼稚園・保育園実習を行いました。今回の実習の目標は「保育士・幼稚園教諭の職務を理解する」ことです。
生徒達は園児達とふれあいながら、先生方がどのように子ども達を援助しておられるか、またどんなことに留意しながらコミュニケーションを図っておられるか観察しました。
半年にわたる4回の実習や夏休み中のインターンシップ、園児とのイモ掘り交流などで経験を積んだ生徒達は、全く戸惑うことなく園児達とふれあっていました。
先週の事前指導では絵本の読み聞かせについて学びましたが、早速実践している生徒も見受けられました。これまでの経験の積み重ねと、新しいことに挑戦する意欲が生徒達を成長させているように感じられました。
次回は11/22(火)に実施します。いよいよ最後の幼稚園・保育園実習です。
教育入門Ⅰ 「絵本の読み聞かせ」
11月8日(火)の教育入門Ⅰは、来週からの幼稚園・保育園実習に向けて事前指導を行いました。テーマは「絵本の読み聞かせについて」。講師は元保育士の玉田勝世先生です。
まず初めに、絵本の読み聞かせ指導について、方法や注意点を話していただき、『大きなかぶ』を範読していただきました。
続いて、7人のグループを作って、読み聞かせのロールプレイを行いました。各自で練習後、グループ内で相互に読み聞かせをするのですが、注意点に気を付けながら初めての絵本を読むのは難しかったようです。それでも、全員立派に読み終えることができました。
休憩をはさんで、後半はグループ代表による読み聞かせ発表です。1グループ3分で全員の前で大型絵本を読みます。玉田先生から1人ずつ講評をいただきました。読むのに精一杯でなかなか聞き手の方を見ることができませんでしたが、最後の読み手は声も大きく、時折聞き手に視線を向けることもできており、高評価をいただきました。
最後に、玉田先生に総括をしていただき、『大きなかぶ』のエプロンシアターも披露していただきました。同じ話でありながら、絵本を読むのとエプロンシアターを行うのとでは全く違った雰囲気になり、生徒達も玉田先生に引き込まれていきながら劇を楽しんでいました。
来週からの2回はいよいよ最後の幼稚園・保育園実習です。生徒達の活動も”実りの秋”を迎えます。
まず初めに、絵本の読み聞かせ指導について、方法や注意点を話していただき、『大きなかぶ』を範読していただきました。
続いて、7人のグループを作って、読み聞かせのロールプレイを行いました。各自で練習後、グループ内で相互に読み聞かせをするのですが、注意点に気を付けながら初めての絵本を読むのは難しかったようです。それでも、全員立派に読み終えることができました。
休憩をはさんで、後半はグループ代表による読み聞かせ発表です。1グループ3分で全員の前で大型絵本を読みます。玉田先生から1人ずつ講評をいただきました。読むのに精一杯でなかなか聞き手の方を見ることができませんでしたが、最後の読み手は声も大きく、時折聞き手に視線を向けることもできており、高評価をいただきました。
最後に、玉田先生に総括をしていただき、『大きなかぶ』のエプロンシアターも披露していただきました。同じ話でありながら、絵本を読むのとエプロンシアターを行うのとでは全く違った雰囲気になり、生徒達も玉田先生に引き込まれていきながら劇を楽しんでいました。
来週からの2回はいよいよ最後の幼稚園・保育園実習です。生徒達の活動も”実りの秋”を迎えます。
教育入門Ⅰ 「幼児期の遊び」
11月1日(火)の教育入門Ⅰは、「幼児期の遊び」をテーマに、大学教授の特別講義を受けました。講師は、神戸親和女子大学 発達教育学部 児童教育学科の坂根美紀子教授です。まずは手遊びを紹介しながら、頭と体のウォーミングアップから講義が始まりました。
Ⅰ 遊びとは Ⅱ 絵本とは の2つの内容で講義が進められましたが、大学生手作りの幼児向けおもちゃや絵本が紹介され、生徒達にとって非常に理解しやすい内容でした。
最後に「しっかりした絵を知り、しっかりした言葉を身につけるために、今のうちにいろいろな本を読んで下さい」とのメッセージを送られました。
質疑応答では、「0歳児に絵本を読み聞かせても効果はありますか?」「先生はなぜ遊びを研究しようと思われたのですか?」など、数名から質問がありました。
坂根先生からも丁寧なお答えをいただきました。ちなみに、最初の質問に対する答えは「すごく大切です。分かっていないように見えても、乳幼児期の体験が大きく育ってから現れるんですよ。」とのことです。
子どもみらい類型の生徒達は、本日から、教職の探究Ⅰで三田市の民話を使った絵本の制作を始めます。次回の教育入門Ⅰは実習の事前指導として、元保育士・玉田勝世先生の実技講習を受けます。
最後に「しっかりした絵を知り、しっかりした言葉を身につけるために、今のうちにいろいろな本を読んで下さい」とのメッセージを送られました。
質疑応答では、「0歳児に絵本を読み聞かせても効果はありますか?」「先生はなぜ遊びを研究しようと思われたのですか?」など、数名から質問がありました。
坂根先生からも丁寧なお答えをいただきました。ちなみに、最初の質問に対する答えは「すごく大切です。分かっていないように見えても、乳幼児期の体験が大きく育ってから現れるんですよ。」とのことです。
子どもみらい類型の生徒達は、本日から、教職の探究Ⅰで三田市の民話を使った絵本の制作を始めます。次回の教育入門Ⅰは実習の事前指導として、元保育士・玉田勝世先生の実技講習を受けます。
教育入門Ⅰ 幼稚園児とのイモ掘り交流
10/25(火)今日の教育入門Ⅰは本校での実習です。3,4時間目に北摂中央幼稚園から年少82名の児童が来ました。生徒と出会って、お兄ちゃんと抱きついたりと、大変和やかな雰囲気でした。イモ掘りは、3つのエリアに分かれ、児童2人に生徒が1人つく形で行われました。採れる度に歓声が上がり、約800個ほどのイモが掘り起こされました。その後は中庭に移動し、折り紙で作った様々な形の物を探し出すゲームをしました。焼き芋が出来上がると、園児が一斉に集まり、熱々のイモを頬張りながら、満足そうな笑顔で交流を終えることができました。これまで4回の幼稚園実習を行うことで、園児との接し方も慣れて、生徒達も共に楽しみながら交流できました。
幼稚園・保育園実習④
10/4(火)3・4限 4回目の幼稚園・保育園実習を行いました。4週目にもなると、到着してすぐ園児達と活動し、積極的に話しかけたりする場面が見受けられました。園児も生徒達に慣れてきたようで、「お兄ちゃん久しぶりやな」と声をかけてくれ、明るい雰囲気でした。
次回は11/15(火)に実施します。
幼稚園・保育園実習③
9/27(火)3・4限 3回目の幼稚園・保育園実習を行いました。今回から子どもみらい類型オリジナルのウェアを着用して実習に臨みます。多くの園が運動会間近ということで、秋空のもと遊技やリレーの練習に励む元気いっぱいの子ども達に囲まれ、生徒達も笑顔がはじけていました。
園児達も高校生を覚えてくれていたようで、給食時には、「僕、お兄ちゃん先生のとこで食べる!」「僕も。」という声が聞こえてきました。生徒達の中には、夏休みを利用したインターンシップで1週間以上幼稚園や保育園の仕事を体験した者も多くおり、1学期よりも頼もしく感じられました。
来週10/4(火)は4回目の実習です。より積極的な取り組みを期待したいと思います。
園児達も高校生を覚えてくれていたようで、給食時には、「僕、お兄ちゃん先生のとこで食べる!」「僕も。」という声が聞こえてきました。生徒達の中には、夏休みを利用したインターンシップで1週間以上幼稚園や保育園の仕事を体験した者も多くおり、1学期よりも頼もしく感じられました。
来週10/4(火)は4回目の実習です。より積極的な取り組みを期待したいと思います。
教育入門Ⅰ 講義「乳幼児期の心理」
9/13(火) 3・4限 「乳幼児期の心理」というテーマで、神戸海星女子学院大学・現代人間学部・心理こども学科・准教授の竹内 伸宜氏に講義をしていただきました。今回から授業の司会・進行を生徒たちに任せることにしました。
乳幼児期はことば以前の時期からはじまり、「一方向的な反応」から「相互的な関係」を経て、まわりの世界に他者とともにかかわる「並ぶ関係」に進み、最終的に「ことばの世界」に発展していく、その間の様子を身近な玩具やプレゼンを用いて解り易く説明して頂きました。
乳幼児期はことば以前の時期からはじまり、「一方向的な反応」から「相互的な関係」を経て、まわりの世界に他者とともにかかわる「並ぶ関係」に進み、最終的に「ことばの世界」に発展していく、その間の様子を身近な玩具やプレゼンを用いて解り易く説明して頂きました。
講義後の質疑応答でも、積極的に手が上がり日頃から感じていた疑問をぶつける生徒もいました。「幼児を抱き抱えたかいたかいをすると非常に喜ぶけれど、あれはどのような心理状態なのか?」・「幼児がある方向を指し示し何かを訴えようとするが、その先に何も該当するものがないことがあるけれど、あれはどういうことなのでしょうか?」等々。幼稚園実習を済ませた生徒たちにとっては、体験に基づいた講義内容でしたので「乳幼児期の心理」についてスムーズに理解が深まったものと思われます。
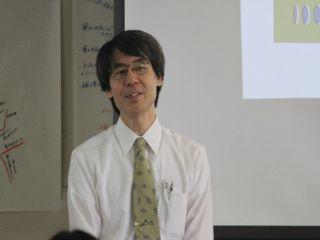





教育入門Ⅰ 夏季休業中の活動報告
9/6(火)3限 夏季休業中の活動報告発表会を行いました。
下野(1-5)と山下(1-5)の両名が7/19(火)に「ハイスクールと特派員登場」に出演し、子どもみらい類型の1学期の取り組みを紹介してくれました。
山本(1-6)は7/23(土)のオープンハイスクールで、「子どもみらい類型の紹介」プレゼンの報告をしてくれました。その日同じプレゼンを3回行ったのだけれど、後になるほど抑揚もありペース配分も良くなり、上手になっていくのが自分でも感じられたと報告してくれました。
蓑原(1-5)と中西(1-6)は8/29(月)の「防災教育全国交流大会」に参加し、舞子高校の震災復興支援活動の呼び掛けに応じて取り組んだ「応援メッセージ」の報告をしてきました。その後、被災児童らからお礼の手紙を頂き逆に勇気づけられたと発表してきました。
その他、「インターンシップ」で夏季休業中5日~10日程度小学校・保育園で実習してきた報告等、いろんな分野で積極的に活動してきてくれました。一回り大きく逞しくなった様に感じました。
《ハイスクール特派員登場》(子どもみらい類型)
7/19(火)17:15~17:45《ハイスクール特派員登場》、今回は"子どもみらい類型"の登場です。下野(1-5)・山下(1-5)の2名が今春スタートした"子どもみらい類型"の魅力をたっぷりと話してくれました。志望動機にはじまり、4月からの講義(活動)内容の紹介、為になった講義、保育園実習での困った事等いっぱい話してくれました。夏休みには、インターンシップとして保育園に実習に行くことになっており、ワクワクしております。


兵庫教育大学の見学
7月12日(火)子どもみらい類型の生徒たちが、今春連携協定を締結した兵庫教育大学の大学見学に行ってきました。高大連携事業の一環で、同大学の大学体験として1日お世話になりました。
プログラムは…
①兵庫教育大学紹介(DVD視聴)
②大学授業聴講「発達障害の理解」
③昼食(学生食堂にて)
④キャンパス案内
⑤講義「魅力的な教師になるために」
⑥大学体験の総括 でした。
大学授業の聴講では大学3回生の学生たちが受けている授業に参加させていただき、90分の講義に真剣に聴き入っていました。昼食は学生食堂でとりましたが、短い時間で慌ただしい中、評判のジェラートに挑戦した生徒たちもいました。午後のキャンパス案内では大学の様々な施設を見学し、改めて高校との違いを実感したようです。
最後に特別講義を受けましたが、講義を担当された佐藤教授からは「生徒の表情がよく、目的も目標も確かでした」と高評価をいただきました。講義中の佐藤教授の「目標に意味が加わって目的になる。大学に合格することは目標であってもいいけれど、それが目的ではいけない。何を学びたいかという意識をしっかりと持って大学を目指してほしい」という言葉が印象的でした。また「学ばない人が教えることは出来ない」というご指摘は、生徒たちの学習意欲をかき立てるものとなりました。
最後に特別講義を受けましたが、講義を担当された佐藤教授からは「生徒の表情がよく、目的も目標も確かでした」と高評価をいただきました。講義中の佐藤教授の「目標に意味が加わって目的になる。大学に合格することは目標であってもいいけれど、それが目的ではいけない。何を学びたいかという意識をしっかりと持って大学を目指してほしい」という言葉が印象的でした。また「学ばない人が教えることは出来ない」というご指摘は、生徒たちの学習意欲をかき立てるものとなりました。
当日は、同じく教育系の特色類型を持つ夢野台高校の2年生とも一緒でしたので、同じ志を持つ生徒とのふれあいを通して子どもみらい類型の生徒たちは充実した1日を過ごすことが出来ました。








震災応援メッセージ
5月24日、子どもみらい類型の生徒たちが、東日本大震災で被災した子どもたちに応援メッセージを送りましたが、先日、メッセージを受け取った東松島市の小学校と保育所からお礼の手紙が届きました。一人ひとり丁寧に書かれた子どもたちのメッセージに、私たちも胸を打たれ、逆に励まされました。今後何らかの形で交流が続けられればと、アイディアを練っているところです。
今回は活動の紹介とメッセージの披露を兼ねて、職員室前に展示をしました。オープンハイスクール当日は、「子どもみらい類型プレゼンルーム」に移動して展示します。是非ともご覧下さい。

今回は活動の紹介とメッセージの披露を兼ねて、職員室前に展示をしました。オープンハイスクール当日は、「子どもみらい類型プレゼンルーム」に移動して展示します。是非ともご覧下さい。

プレゼンルーム開設
教育入門Ⅰ 幼稚園・保育園実習②
6/21(火)3・4限 今回で2回目となる幼稚園・保育園実習を行いました。2回目ということもあり、最初から積極的に園児へ話しかけたり、遊んだりしていました。
前回と同じクラスに入り、お遊戯や昼食を共に過ごし、改めて現場の先生方の大変さを感じたようです。その中でそれぞれ楽しさや、やりがいを感じ充実した表情で実習を終えることになりました。
次回の実習は9月27日(火)です。3ヶ月後の成長が楽しみです。
教育入門Ⅰ 幼稚園・保育園実習
6/14(火)3・4限 いよいよ幼稚園・保育園実習の始まりです。最初は硬い表情が目立ちましたが、園児たちの笑顔に逆に励まされ、しばらく経つと全員明るさを取り戻していました。
1クラスに1~2名が入り、泥玉遊びやパズルなどを通して子どもたちとふれあい、昼食も共にしました。あっという間の2時間が過ぎ、各々が充実した表情で実習園を後にしましたが、今回は子どもたちとふれあうのが精一杯で、改めて現場の先生方の仕事ぶりに敬意を抱いたようです。
1クラスに1~2名が入り、泥玉遊びやパズルなどを通して子どもたちとふれあい、昼食も共にしました。あっという間の2時間が過ぎ、各々が充実した表情で実習園を後にしましたが、今回は子どもたちとふれあうのが精一杯で、改めて現場の先生方の仕事ぶりに敬意を抱いたようです。
次回の実習は21日(火)です。








教育入門Ⅰ 「事前指導」
6/7(火)3・4限 来週から始まる幼稚園・保育園実習を前に、「事前指導」というテーマで玉田勝世講師に事前に心掛けるべきポイントを指導をしていただきました。
まず、生徒に「園児のイメージ」についてマインドマップに表現させ、実習に行った際に気を付けるべき点について各グループで発表しました。
その後、玉田先生から、園児の運動能力・思考過程について話していただき、園児に対する接し方・指導方法を解説して頂きました。
最後に、「手遊び歌」を通して園児との遊び方・触れ合い方も指導して頂きました。有難うございました。



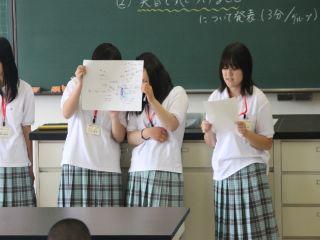


教育入門Ⅰ 「芋植え」
5/31(火) 7限 「芋植え」を実施、講師は本校の藤原教頭です。 





今秋、幼稚園児・保育園児を「芋掘り」に招待する予定ですが、その準備です。みんな「芋植え」は初めての体験のようで、キャッキャッ言いながら楽しく作業に取り組んでおりました。収穫の秋が楽しみです。






学校情報化優良校
学校情報化認定とは・・・
日本教育工学協会(JAET)において、教育の情報化の推進を支援するために、「情報化の推進体制」を整え、「教科指導におけるICT活用」「情報教育」「校務の情報化」に積極的に取り組んでいる学校を客観的に評価し、認定するものです。
※認定期間:2025年度~2027年度(3年間)
今後は『学校情報化先進校』に向けて、さらなる取組みを進めていきます!
三田西陵高校情報
2分でわかる!
子みらいって?
部活動活動風景
生徒会執行部が全部活動を巻き込んで
写真撮影を行いました♪

携帯サイトはこちら
ファイルダウンロード
学校連絡先
兵庫県三田市ゆりのき台3丁目4番
TEL:079-565-5287
カウンタ
1
5
5
1
5
3
1
1
Copyright
このホームページは兵庫県立三田西陵高等学校にて運営・管理されています。
画像・PDF及びこのサイトで使用の全ての流用を禁じます。



