創造科学科ブログより抜粋
令和3年9月28日 課題研究「院生プレゼン」
創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第1回目の授業を受けた。
この授業では、自然科学の最先端の研究に触れ、科学に対する興味関心を深め、神戸大学の大学院生の指導を受けながら実際に自然科学の研究テーマを設定し実験・観察を行っていく。
第1回目の授業では、神戸大学の大学院生8名に来校いただき、それぞれ大学で行っている物理・化学・生物分野の研究内容のプレゼンテーションをしていただいた。その後、その中で興味をもった分野について自分たちで研究したいことを話し合った。院生の方から研究の魅力を聞きながら、好奇心をもってテーマを考えていた。


令和3年9月22日 創造応用IS「探究活動③」
創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの3回目の探究活動と、研究報告会を行った。
数学分野では、統計学の講義を受けた後、電車の乗車人数やアンケート調査の有効性、スポーツにおける統計など考えたテーマについて大学の先生とより具体的に研究内容や研究方法についての相談を行った。
物理分野では、大まかに決めた研究テーマについて、大学の先生の助言のもと、具体的な実験計画を立てた。
化学分野では、磁性流体の活用法を考えるため、実際に磁性流体の作製にとりかかった。普段の実験ではあまり使用することのない器具の扱いに苦戦しつつも、原料となる物質を回収できた。
生物分野では、植物内の水などの液体の動きに着目して大学の先生の助言をいただきながら実際に行う実験方法を考えた。
都市工学分野では、コンビニの配置についてどのように研究を進めてくのか、研究方法や研究を行う際の定義について確認を行った。
研究報告会では、全分野が集まり、研究の進捗状況の報告を行った。研究テーマや研究目的、研究方法を発表し、お互いに意見を交換した。他の分野の研究報告を聞き互いに刺激を受け次回からの研究にいかしていく。





令和3年9月21日 創造基礎B「前期最終発表会」
本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科6期生(1年)が創造基礎B 前期最終発表会「“次世代が選ぶまち”KOBEの実現にむけて、高校生の力を発揮しよう!」を行った。ゲストとして、長田区役所総務部まちづくり課から課長の平岩正行氏、まちづくり推進係長の杉山純一氏、兵庫県企画県民部ビジョン局ビジョン課から大町充弘氏、シチズンシップ共育企画の東末真紀氏の4名をお招きし、講評を行っていただいた。同じ課題についてABの二つに分かれ中間発表を行ったが、最終発表ではAB合同で発表する班もあり、解決策の提案をおこなった。質疑応答や、ゲストからいただいた講評を受け、研究に対する理解を深めたり改善点を見出したりすることができた。今後、各班はコメント等を参考に企画を修正し、実践活動を行っていく予定である。
なお、今回は保護者向けにライブストリーミング配信を行った。
各班の発表の内容は以下の通りである。(発表順)
4班A「10代の少年少女へ、本の世界にご招待!~名谷駅ストーリーウォークの提案~」
4班B「本は人生のバネになる。~シニア向け名谷マイクロライブラリー~」
3班A・B「ビーサン装備で健康LvUP!!―親子卓球大会―」
1班A「長田坂“fun”クラブ」
1班B「NAGATA CRAFT for Teens~長田の名所をマイクラで~」
5班A・B「Mission 3A ~駒ヶ林☆空地リユース大作戦~」
2班A・B「獅子ケ池PR、始めます。~写真で伝える映え自然~」








令和3年9月18日「日経SDGsフォーラム高校生SDGsコンテスト」
創造科学科5期生(2年)3名が、日本経済新聞社主催「日経SDGsフォーラム高校生SDGsコンテスト」の決勝大会に、オンラインで出場した。全国から56校の応募があり、本校は決勝校の10校に選ばれ、発表した。生徒は1年生の創造基礎の活動で駒ヶ林にアーティストを呼び込む活動として、動画やホームページを作成する「神戸駒ヶ林×アーティスト プロジェクト」という活動を行った。その成果をもとに今回発表を行った。質疑応答では、日本総合研究所創発戦略センターシニアスペシャリストの村上芽氏から質問を受けた。惜しくも受賞することはできなかったが、他校の活動を知ることもでき、今後の研究にも役立つものとなった。
日経SDGsフォーラム 高校生SDGsコンテストHP
https://career-edu.nikkeihr.co.jp/category01/sdgscontest/
生徒作成HP「神戸駒ヶ林×Art」
https://sites.google.com/view/komagabayashixart/home?authuser=0


令和3年9月15日 創造応用IS「探究活動②」
創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの探究活動の2回目を行った。




数学分野では、神戸大学の先生から統計学の講義を受け、知識や理解を深めながら研究テーマの決定に向けて活動を行った。
物理分野では、大阪大学の先生、院生の方からアドバイスを受けながら研究テーマについてより掘り下げて内容を考え、研究テーマの決定に向けて話し合った。
化学分野では、前回出し合ったテーマの中で具体的にどのような研究を行うのかを検討した。それぞれの興味・関心を実際に研究としてどのように形にしていくのかを神戸大学の先生にアドバイスをいただきながら話し合った。
生物分野では、前回に出し合った研究テーマについて研究目的や実験方法などを明確にして実際にどのような実験をしていくのかを神戸大学の先生のご指導のもと考えた。
都市工学分野では、身近な都市である三宮における公共施設の配置についてなど、研究内容の具体的な案を出し合い、大阪大学の先生のアドバイスのもと検討した。
令和3年9月8日 創造応用IS「探究活動①」
創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、自分たちで設定した研究テーマについて研究していく探究活動を開始した。
第1回目となる今回は各々が考えてきた研究テーマ、研究内容を出し合い、そのテーマについてお互いに意見を出し合って議論を行った。実際に研究として成り立つのか、実験が行えるのか、研究にどのような科学的視点を盛り込んでいくのか、など多角的な視点から意見を出し合った。そのうえで大学の先生方から助言をいただきながらテーマの絞り込みを行った。今後、絞り込んだテーマをより具体的にどのような実験で何を調べていくのか掘り下げていき研究テーマを決めて実験を行っていく予定である。

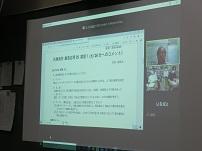


今年度は、主に
数学分野:神戸大学 稲葉 太一 先生
物理分野:大阪大学 小田原 厚子 先生
化学分野:神戸大学 秋本 誠志 先生
生物分野:神戸大学 源 利文 先生
都市工学分野:大阪大学 澤木 昌典 先生
に各分野でご指導、ご助言をいただきながら研究を進めていく。
令和3年8月30日創造基礎B FW駒ヶ林地区
駒ヶ林地区活性化の仕掛けや提案などに取り組む創造科学科6期生(1年)5班の生徒3名が「創造基礎B」の授業の一環として、駒ヶ林地区を訪れた。前回のフィールドワークに引き続き、まちづくり推進担当の杉山係長に案内をしてもらいながら空き地の様子を確認した。自治会の方にもお話をしていただき、以前に本校生が関わって活動した空き地の現状も確認した。今後、この空き地を対象に活動を進めていく予定である。


令和3年8月21日灘高模擬国連練習会
オンラインにて、創造科学科6期生(1年)2名が 灘高等学校ディベート部主催の模擬国連練習会に参加した。議場は国連総会第1委員会(DISEC)、議題は核軍縮で、言語は英(日)/日/英 (公式/非公式/決議)(全日本大会と同じ、ただし公式発言で日本語の使用も認める場合がある)である。国割りはシングルデリゲート、会議形式は全日本高校模擬国連大会の議事進行に則ることとした。
令和3年8月5日BAAC模擬国連交流会
創造科学科5期生(2年)の生徒一名が、BRIDGE Across Asia Conference(アジア太平洋高校模擬国連大会)のオンライン交流会に参加した。この大会は日本の生徒がモンゴル・韓国・タイ・インドの生徒とペアを組み、オンラインで行われる。国・地域の垣根を越えた学びあいと交流を通して、多様性に富んだ社会で活躍できる次世代の人材の発掘と育成に貢献していくことが目的である。本校生徒は書類とプレゼン動画による選考により日本代表生徒の一人に選ばれ、インド代表の高校生とペアを組んでシンガポール大使として模擬国連に参加する。今回はオンラインで開会式とペアの交流を行った。

令和3年7月21日創造応用FW「神戸駒ヶ林×アーティスト プロジェクト」
駒ヶ林地区の古民家再生喫茶店「初駒」において、創造科学科5期生(2年)3名が、駒ヶ林地区での古民家のリノベーションについて、まちづくりコンサルタントの(有)スタヂオカタリスト代表取締役の松原永季氏からお話を伺った。生徒は1年生の創造基礎の活動で駒ヶ林にアーティストを呼び込む活動として、動画やホームページを作成する活動を行った。2年生では、それらの作品をさらにブラッシュアップし、実際に活用してもらえるよう実践活動を続けている。今回は10年以上駒ヶ林地区のまちづくりに関わっている松原氏から、駒ヶ林地区の良さや、古民家再生の事例、アート活動が始まった経緯などについてヒアリングを行った。
生徒作成HP「神戸駒ヶ林×Art」
https://sites.google.com/view/komagabayashixart/home?authuser=0


令和3年7月17日創造基礎実践活動「がまっち展示」
北野工房のまちにあるマッチハウス「マッチ棒」において、創造科学科4期生(3年)5名と5期生(2年)1名が、がま口財布型マッチケース「がまっち」の展示を行った。生徒はがまっち作成の経緯説明のポスターや冊子、ポップを持参し、店の入り口に配置した。生徒は訪れたお客さんに説明して、がまっちの反応を聞いたりした。この展示は、9月5日まで実施予定である。
北野工房のまち「学生さんが作成したマッチとがま口のマッチング『がまっち』展示中!」kitanokoubou.jp/macchibou_gamacchi2021
写真
〈生徒感想〉
今日は北野工房のまち、マッチ棒にて展示開始準備を行いました。ポスターの掲示や北野工房HPのための取材などをし、2時間ほどで終了しました。私たちは、1年生の終わり頃からコロナによる自粛期間に入り、活動が完全に止まってしまったためにモチベーションが底をつき始め、正直がまっちが完成して展示できるというビジョンが見えていませんでした。それでも、日頃から様々な支援をして下さっている神戸まちづくり研究所の古川さんを始め、様々な人たちのおかげで今展示することができています。本当に感謝しかありません。今回のマッチ棒さんでの展示は、今までの活動の集大成のようでとても感慨深く感じています。私たちの想いの乗ったがまっちを通して、1人でも多くの人にマッチとがま口財布の良さが伝わればと思います。
令和3年6月30日 創造応用IS「探究テーマの検討」
創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、今後の探究活動を行う科目班ごとに分かれ、テーマの設定に取り掛かりました。
まずは互いに研究してみたいと思っていたこと、授業や生活の中で研究してみたいと感じたことを出し合いました。校内でテーマになりそうなものを探している班もありました。


探究活動におけるテーマ設定は非常に重要で、焦って決めたり、難度が高すぎたりスケールが大きすぎたりすると途中で行き詰ることが多くあります。今後、夏季休業を利用してさらに研究テーマの候補をしっかりと考え、大学の先生方の助言もいただきながらじっくりとテーマ設定に取り組んでいきます。
令和3年6月29日 創造基礎B前期中間発表会「“次世代が選ぶまち”KOBEの実現に向けて、高校生の力を発揮しよう!」
本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)が創造基礎B前期中間発表会「“次世代が選ぶまち”KOBEの実現に向けて、高校生の力を発揮しよう!」を行った。ゲストとして、長田区役所総務部まちづくり課からまちづくり推進係長の杉山純一氏、齋藤佑季氏をお招きし、講評を行っていただいた。また創造科学科5期生(2年)からも2名参加し、アドバイスを行った。質疑応答や、ゲストからの講評を受け、それぞれの班の課題を発見することができた。
各班の発表の内容は以下の通りである。(発表順)
2班A 「Take a Picture! It’s my best “ Shishigaike”」
2班B 「ねーねー獅子ヶ池登らん?~写真を使った獅子ヶ池PR~」
4班A 「物語の世界への招待~名谷地区におけるストーリーウォークの提案~」
4班B 「マイクロライブラリーで地域活性化!in 名谷」
1班A 「長田坂ファンクラブ(公式)」
1班B 「STAY NAGATA~煌めくながたの現風景~」
5班A 「エコ路地FLESH!~隠れ家的喫茶~」
5班B 「駒ヶ林に来た皆さん!君のスマホがこの町を案内します!」
3班A 「ビーチサンダルを持ち歩こう!」
3班B 「ビーサン装備で健康レベルアップ!!~親子卓球大会~」






令和3年6月25日 RRE「外国人留学生交流会」
本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科6期生(1年生)40名が兵庫教育大学と神戸大学の留学生10名と英語を用いて交流会を行った。まず、お互いの自己紹介を行い、アイスブレイクのゲームを行った。次に、本校生は「SDGsについての課題」をテーマにポスターを用いてプレゼンテーションを行い、留学生は「「SDGsに基づく自国が抱える課題について」をテーマにパワーポイントを用いてプレゼンテーションを行った。最後に各グループ代表が、セッションの報告を行った。生徒は楽しみながら積極的に留学生と交流することができたとともに、他国の魅力と課題を学ぶことができた。
外国人留学生の出身国:ブルキナファソ、ナイジェリア、ジンバブエ(2名)、インドネシア(3名)、中国(1名)、バングラディシュ(2名)





令和3年6月23日 創造応用IS「探究演習②」
本校の化学教室において、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、今後の探究テーマの設定を意識したSDGsに関連した探究活動を行いました。
今回は「安全な水とトイレを世界中に」について考え、「高機能かつ高効率のろ過装置の開発」をテーマとして汚水から不純物を取り除くためのろ過装置を作成し、その評価も行いました。単純に物質を詰めるだけでは不純物が除去されず、得られるろ過水が少ないことを実感したうえで、粒子の大きさや物質吸着のメカニズムを考えろ過装置に詰める量やメカニズムを考えながらろ過装置を作成しました。


身近なものを組み合わせて探究活動が行えることを実感する一方で、ろ過装置開発の過程で大量の汚水や廃棄物が出てしまうなど、視野を広く持ち研究を進めなければいけないという課題も浮き彫りになりました。今後の探究活動でこの体験をいかしていってほしいです。
令和3年6月22日創造基礎A「父親の育休を当たり前にしたい」
本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)を対象に、株式会社ワークライフバランスの大畑愼護氏から「父親の育休を当たり前にしたい」というテーマで、オンラインで講義を実施した。事前学習で男性の育休取得について是非やその理由、質問事項について生徒にアンケート調査した。大畑氏には、それを受けて今回は講義を構成していただいた。まず、株式会社ワークライフバランスの紹介が行われた。男性の育休取得にとどまらず、長時間労働やハラスメントなど労働者の働き方の課題解決のコンサルティングを行っていることや社会への働きかけについて紹介をしていただいた。次に、男性の育休取得に関する課題とその解決のための対策について講義をしていただいた。生徒の質問に一つずつ答えていただく形で、双方向の授業とすることができた。


令和3年6月16日 創造応用IS「探究実践①」
本校の化学教室において、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、探究活動を行っていくに当たり必要な「実験計画の立て方」、「研究ノートの書き方」について実践的に学びました。
「同じ濃度の塩酸・硫酸・酢酸を同定する方法を探究する」をテーマとして、実験計画を立て、必要な器具や試薬の準備をその場で行い、実験を行いながら研究ノートに実験記録を残して行きました。


しっかりと計画を立てることでスムーズに研究を進めることができます。また、行った研究の記録をしっかりと残しておくことは、自分が行った研究を振り返ってさらに深めることや研究内容を発表する上で非常に重要です。
これまでに学んだ化学の知識をフル活用し、3種類の酸を同定する方法を考え、楽しみながら真剣に実験に取り組んでいました。
令和3年6月9日創造基礎B FW中央図書館
創造科学科6期生(1年)4班の生徒8名が「創造基礎B」の授業の一環で、中央図書館を訪問した。「名谷図書館」をテーマにしたこの班は神戸市文化スポーツ局中央図書館企画情報担当の村井課長と同総務課地域連携推進担当の西山係長からお話を伺った。生徒は神戸市の図書館施策全般や利用促進の取組みについて、名谷図書館設置の経緯や運営形態について質問した。公共施設としての図書館の役割が新型コロナウイルス感染症の影響で市民のニーズを再認識したことや、さまざまな取組みで幅広い世代が利用できるよう工夫していることについてお話をしていただいた。


令和3年6月2日 創造応用IS「都市工学分野 集中講義」
本校の第2STEAM ROOMにおいて、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、大阪大学工学研究科 澤木昌典教授から都市工学の分野説明や研究内容、テーマ設定についてのオンライン集中講義を受講しました。
本日の講義を聞くまでは、都市工学はスケールが大きく高校生が研究を行えるのだろうか?と不安に思っていた生徒も多かったようです。しかし、都市工学の研究が社会に果たす役割や過去の研究内容を聞き、都市における身近な問題の解決や人間が安全・快適に過ごすための工夫など、自分たちが生活する地域を良くするための研究だということを知り、研究のイメージが湧いてきている様子でした。



今後、数学・物理・化学・生物・都市工学の5分野から自分の希望の分野を選び、本格的に探究活動を行っていきます。希望分野を選ぶためのよい学びになりました。
令和3年6月1日創造基礎B FW駒ヶ林地区
駒ヶ林地区活性化の仕掛けや提案などに取り組む創造科学科6期生(1年)5班の生徒8名が「創造基礎B」の授業の一環として、駒ヶ林地区を訪れた。まちづくり推進担当の杉山係長と齋藤氏に案内をしてもらいながら、路地をめぐり,町の様子を肌で感じることができた。また、空き家再生に取り組んでおられる方から直接話を伺うこともでき、これからの活動に大いに参考となった。

































