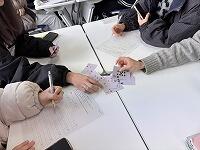創造科学科ブログより抜粋
令和8年1月25日 「創造基礎LB イザ!美カエル大キャラバン」
80回生(1年生)の創造科学科4名が神戸市の人と未来防災センターで開催された「イザ!美カエル大キャラバン」に参加しました。地域×防災を大テーマとして1年間取り組んだこの班は「やさしい日本語~防災と異国文化について考えよう~」をタイトルとしたブースの出展に挑戦しました。1年間の幾度となるフィールドワークの中で、長田区には英語が通じない日本語学習者もいるということを知り、いざという時に誰もが安心して避難ができるように、やさしい日本語に焦点を当てたクイズを行いました。
以下、参加した生徒の感想です。
・夏にお誘いをいただいてからとても楽しみにしていたイベントの一つでしたが、自分たちで考えた企画で外部イベントに参加するのは初めてで班員全員緊張と不安に包まれていましたが本当に幅広い年代の方と交流することができて、素敵なお話もたくさん伺うことができました。また、防災意識が高い方ばかりで、プログラム中にも活発に意見交換が行えたことや、夏にお世話になった方ともう一度お会いすることができてうれしかったです。
・今回のイベントには20か国から21人の海外からの方も参加されており、実際に日本語を学んでおられる方から私たちのプログラムについての直接のアドバイスもいただきました。企業や中学校、高校から大学まで様々な団体が参加しており、私たち自身としても学ぶことの多いイベントとなりました。
令和8年1月24日 「第6回ひょうご高校生環境未来リーダー育成プロジェクト」
第6回ひょうご高校生 環境・未来リーダー 育成プロジェクトに本校から創造科学科9期生2名、普通科1名が参加しました。全6回のプロジェクトの最終回は兵庫県立工業技術センターにて成果発表会が開催されました。
環境問題に関するさまざまな分野の専門家からの講義、北摂地域や淡路地域へのフィールドワーク、他校の生徒たちとのディスカッションの機会を通して考えたことをもとに、それぞれの観点から環境問題への提唱を行いました。
以下、参加した生徒たちの感想です。
・私はこのプロジェクトを通して、高校生が環境問題について積極的に向き合うことの重要性をとても実感しました。たくさんの専門家による講義を受ける中で、環境問題に対して危機感をもつだけでなく、実際に行動にしている大人が数多くいることを知りました。そして、今後は私たちの世代が具体的な行動へとつなげていく姿勢がより必要になると考えました。環境問題について理解を深めることが出来、仲間と議論しながら自分たちの意見を発表することが出来ていい経験になりました。
・このプロジェクトに参加して、環境問題に対する意識が大きく変わりました。環境について考えることはもちろん重要ですが、考えるだけでは意味がなく、実際に行動に移すことの大切さを改めて実感しました。また、グループでの話し合いや意見交換を通して、さまざまな視点から物事を考えることの重要性にも気づきました。異なる考え方やアイデアを知ることで、自分だけでは思いつかなかった解決策や新しい視点を得ることができました。今回の学びを、日常生活や学校活動に生かし、環境を守る行動を少しずつでも積み重ねていきたいと考えています。
・このプロジェクトに参加して、環境に関する知識が圧倒的に増えました。特に、実際に取り組みに関わっている方々から話を聞くことができ、ネット上だけでは知ることのできない日本や兵庫県現状を知ることができました。兵庫県の取組や現状について詳しく知ることができ、より兵庫県のことを好きに、大切にしたいなと感じました。グループでの活動は、他の学校の人と関わることができ、ボランティアの話や、地域での取り組みなどを聞けて、とても楽しかったです。また、環境の中でもより細かい同じテーマのひとと活動できたので、深くまで突き詰めていくことができました。この経験をこれからの探究活動や、環境に関わる時に生かしたいと思います。
令和8年1月24日 「創造基礎LB 子ども食堂EXPO」
80回生(1年生)の創造科学科4名が神戸常盤BASE ZUTで開催された「子ども食堂EXPO」に参加しました。地域×歴史を大テーマに1年間取り組んだこの班は、駒ヶ林浦漁業会の方々との交流の中で、150年の歴史を持つ駒ヶ林港や長田でとれる魚を地域の子どもたちにより身近に感じてもらいたいという想いを抱き、漁の様子や長田で有名な魚(しらすやクロダイなど)をテーマにオリジナルのコマハマすごろくを作成しました。また、長田港で取れる魚のオリジナルお魚シールも作成し、子どもたちにも長田港の魚を身近に感じてもらうことができました。
以下、参加した生徒の感想です。
・イベントでは、3歳から小学4年生までの幅広い年齢の子供たちにすごろくで遊んでもらいました。クイズに答えたり、お魚シールをゲットしたりとすごろくを楽しんでもらいながら、たくさんの子供たちに長田港に興味を持ってもらうことができたのではないかと感じています。また、掲示したポスターもイベントを訪れた多くの保護者の方が見てくださり、子供たちだけでなくその親の世代の方にも伝えることができ、多くの人に長田港を広める初めてのイベントとして、私たちにとって貴重な経験となりました。
令和8年1月13日 「創造基礎LA 戦争と平和について考える」
80回生(1年生)の創造科学科40名が創造基礎LAで「戦争と平和のゲーム」を通し、なぜ戦争が起こるのか、平和を維持するための条件は何かについて考えました。トランプを用いたゲーム形式で盛り上がる一方で、実社会に置き換えた場合について、それぞれが深く考えることができました。
以下、生徒の感想です。
・ゲームの中で,初めのほうは「自陣の得点を増やすこと」のみを考えていた.しかしながら,「自陣:平和・相手:戦争」などとなったときに「やりかえしたい」という気持ちが生まれた.相手を落とすことで,自分たちの相対的順位が上がる,という認識のもと,争いを生む.それによる互いの発展はあまり見込めないのにもかかわらず,だ.人間の根底にある「自らの相対的位置」への意識に気づかされた.
・実際には国際間の守るべき条約や、国連、NATOなど世界の目があるといったところで戦争は抑止されていると思うが、いつ攻撃されるかわからないという脅威があるからこそ、軍備拡張し、それがさらに緊張を高め戦争の発生につながってしまうと思う。
・価値観や宗教の違いや、権益を得ようとしてどちらか一方が行動を起こしてしまうと、相手も自衛のためにも報復せざるをえなくなってしまうと思いました。このゲームと同じように、現実でも核は抑止力になり得るが、どちらかが使おうとすると手がつけられなくなると考えました。
令和7年12月22日 「地域×自然環境イベント」
80回生(1年生)の創造科学科8名が片山児童館で「地域×自然環境イベント」を開催しました。創造基礎LBで大テーマ「地域×自然環境」に取り組む2班は「環境問題」と「外来生物」と普段は異なる切り口で活動しています。今回は地域の小学生へのイベントということで、2班がコラボで活動しました。
「環境問題」班は環境問題を楽しく学べる神経衰弱、牛乳パックを用いたリサイクルコマ作り、「外来生物」班は外来生物輪投げ、外来生物カード作りというブースをそれぞれで1から考え、運営しました。
以下、生徒の感想です。
・私たちは、外来生物問題について子どもたちに興味を持ってもらうことを目的に、外来生物を的にした輪投げと、塗り絵で外来生物カードを作るというアクティビティを、ブースで分かれて行いました。一気にたくさん来る子どもたちの対応は大変でしたが、おれ、外来生物知ってるで!セアカゴケグモとかやろ?や、うちでアメリザリガニ飼ってるねん!と話してくれる子がたくさんいて、想定していたよりも子どもたちの外来生物に対する知識が多いことに驚かされました。活動しながら、
ー知ってた?アメリカザリガニって、絶対にがしたらあかんねんで~
ー知ってる!ちゃんと死ぬまで飼って、お墓作ったるねん!
などというコミュニケーションもとれ、楽しそうに外来生物について学んでくれていたのがよかったと思います。ただ、対応に忙しくて、子どもが興味を持つような話が少ししかできなかったので、今後に生かしたいです
・自分は輪投げを担当しました。遊びを通して興味を持ってくれ、説明を真剣に聞いてくれた姿が印象的でした。また、今回のイベントを通して、伝え方を工夫することの大切さを学びました。さらに、年齢に合わせてルールを調整すると、より理解が深まると感じた。次回のイベントに向けて、今回の反省を生かし、さらに改善していきたいと思います。
・私は今回エコ工作のブースを担当しました。最初は子供たちが環境問題や外来生物について楽しみながら学んでくれるかどうか不安に思っていましたが、作った外来生物カードを見ながら牛乳パックに外来生物の絵を書いていた子達がいて、とてもうれしかったです。ですが反省すべき点もあったので、今回のことを受け、今後の活動に生かしていきたいと思います。
・私たちは、児童館で環境について楽しんで学んでもらうことをテーマにイベントを行いました。子供たちの楽しんで取り組む様子を見ることができ達成感を得られました。イベントを計画する段階で、子供たちがどれくらい知識があるのかを知っておくことでより良いイベントが実施できると感じました。今回のアンケート結果や反省点をふまえ次につなげていきたいです。