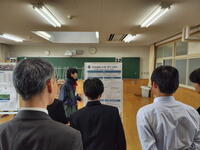総合自然科学科の1年生が受講する『課題研究Ⅰ』とは,理科と公共を融合させた科目であり,私たちを取り巻く様々な社会問題を自然科学の観点から分析することにより,自ら課題を見つけ出し,その問題を解決するための方法を習得することを趣旨としています。
前期は,主に公共の色を強く持つ授業が展開されます。様々な社会問題の学習とその解決法を研究することによって,科学的なリテラシーだけでなく,将来科学者として必要なグローバルな科学観や倫理観を養います。後期は,主に理科の色を強く持つ授業が展開されます。主体的な学びと,科学的思考力や応用力,さらに知の統合を図っていきます。5人編成で課題研究を行い,3月には「ミニ課題研究発表会」が行われます。毎週1時間,および長期休業中なども一部使って研究に取り組みます。
2年生ではさらにレベルの高い研究活動を課題研究で行い,校内外での研究発表も行います。また,3年生の理数探究では,2年生で作製した日本語のポスターを英語で作製し,英語で発表します。
2025(令和7)年度は以下の8つのテーマに分かれて研究しています。
①「角度と飛距離に関する研究」
②「表面張力と洗剤濃度に関する研究」
③「ものの溶けやすさ、溶けにくさに関する研究」
④「臭わない油の作成に関する研究」
⑤「各歯磨き粉の成分による加熱した際の反応の違いに関する研究」
⑥「生物と色認識に関する研究」
⑦「食パンとカビに関する研究」
⑧「数列に関する研究」
課題研究Ⅰ
【課題研究Ⅰ】ミニ課題研究(片付け)・課題研究オリエンテーション
2月17日(火)に、ミニ課題研究の片付けを行いました。
先日の生徒研究発表会をもって一度研究に一区切りをつけ、使用した実験器具の整理・片付けを行いました。また、来年度の研究活動に向けて、課題研究オリエンテーションも実施しました。
3月6日(金)には、今回発表した内容についてクラス内発表を行う予定です。
【課題研究Ⅰ】令和7年度兵庫県立姫路西高等学校 SSH成果発表会に参加しました
令和8年1月31日(土)兵庫県立姫路西高等学校で、「令和7年度兵庫県立姫路西高等学校 SSH成果発表会」開催されました。
課題研究Ⅰの代表として、「車間距離と渋滞の関係に関する研究」というテーマで1名がポスター発表を行いました。
生徒は、高校生や大学・企業の研究者等様々な聴講者の方にタブレットを用いながら発表をしました。
聴講者の方々からアドバイスも多くいただき、2月7日(土)に本校で開催される「生徒研究発表会」に向けての改善点も見えてきました。
残り時間はわずかですが、「生徒研究発表会」で更に良い発表ができるように、いただいたアドバイスを班員に共有し本番に臨んで欲しいです。
【課題研究Ⅰ】ミニ課題研究第12回目の授業を実施しました
1月27日(火)、ミニ課題研究の第12回目の授業を実施しました。
ポスター制作も大詰めを迎え、各班は研究結果を整理するとともに、ポスターの構成や表現の方向性を確認しながら調整を行っていました。中には早くも印刷に取りかかる班もあり、生徒研究発表会に向けて真剣に準備を進めていました。
【課題研究Ⅰ】小高連携いきいき授業を行いました。
1月22日(木)、「小高連携いきいき授業」として、総合自然科学科1年生が、たつの市立御津小学校およびたつの市立神岡小学校を訪問し、星に関する授業を行いました。
警報の発令により、予定より少人数での実施となりましたが、御津小学校には16名、神岡小学校には7名の本校生徒が訪問しました。
授業では、小学6年生を対象に、冬の星座についての講義やミニプラネタリウムの制作を行いました。星座に関するクイズを取り入れたり、小学生と自身の小学生時代の思い出を話したりたりしながら、楽しく学んでもらえるよう工夫を凝らして取り組んでいました。
【課題研究Ⅰ】ミニ課題研究第10回目の授業を実施しました
1月17日(土)ミニ課題研究の第10回目の授業を実施しました。
本日は多くの班がポスターづくりと発表練習を行っていました。
また、来週の木曜日に実施する「小高連携いきいき授業」(小学校への出前授業)の練習をする生徒もいました。
発表等色々なイベントがあり大変ですが、生徒たちは楽しそうに活動しています。