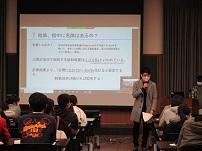カテゴリ:課題研究
令和3年11月3日 課題研究「高塚公園採水」
課題研究で「環境DNA」をテーマに研究している創造科学科6期生(1年生)の8班4名が、カワバタモロコとブラックバス、ブルーギルがいるかを調べるために、高塚公園内の湯谷池にて採水を行った。前日に大学院生から採水方法の指導を受け、それに従って採水した。





令和3年11月2日 課題研究「第5回」
創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第5回目の授業を受けた。
8班に分かれてそれぞれの設定したテーマについて実験や観察を本格的に開始した。今回は全ての班に大学院生が指導に参加していただいた。
高分子化合物の合成研究、ひっ付き虫の特徴を探る研究、髪の毛が痛んだ時の変化を調べる研究、地域の水から環境DNAを採取し生態系を調べる研究、彗星の流れを再現する研究など自分たちで研究の方法を考え、実験・観察を行いながら、出てきた課題は大学院生の方と相談しながら克服するための方法を考えながら研究を行った。


令和3年10月26日 課題研究「第4回」
創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第4回目の授業を受けた。
前回の院生ゼミで作成した研究計画をもとに、探究活動を開始した。班ごとに、DNAの採取のためにフィールドワークに出る、実験条件の確認、観察地点や観察する生物の絞り込みなどを行った。
神戸大学の大学院生から対面やオンラインなど様々な形態で助言をいただきながら研究を進めた。指導をいただいている神戸大学の谷先生からも意見を活発に出し合い自分たちの研究を主体的に進めていこうとする姿勢が非常に良かったというお言葉をいただいた。


令和3年10月12日 課題研究「院生ゼミ」
創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第3回目の授業を受けた。
今回は「院生ゼミ」と題して、自分たちで考えた研究テーマについて神戸大学の大学院生の指導のもと、より具体的に研究目的や仮説を設定し、今後の研究計画を立てた。班員と院生で意見を交わし、質問をぶつけ、コミュニケーションをとりながら進めた。
漠然としていた研究内容が目的や仮説を設定することでより明確になり、自分たちが行う研究に具体性をもたせることができた。これによって実際に研究・実験に必要な器具や試薬を挙げ、実験計画をたてることに繋げることができた。
ここまでの授業で研究・実験を始めるための流れを実践的に学んだ。


令和3年9月28日 課題研究「院生プレゼン」
創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第1回目の授業を受けた。
この授業では、自然科学の最先端の研究に触れ、科学に対する興味関心を深め、神戸大学の大学院生の指導を受けながら実際に自然科学の研究テーマを設定し実験・観察を行っていく。
第1回目の授業では、神戸大学の大学院生8名に来校いただき、それぞれ大学で行っている物理・化学・生物分野の研究内容のプレゼンテーションをしていただいた。その後、その中で興味をもった分野について自分たちで研究したいことを話し合った。院生の方から研究の魅力を聞きながら、好奇心をもってテーマを考えていた。


令和3年2月12日 課題研究 最終発表会
本校武陽ゆーかり館において、本校創造科学科5期生(1年)40名が最先端の自然科学探究活動の成果を発表する「課題研究最終発表会」をオンラインで行った。緊急事態宣言が発出される中、オンラインでの発表会となったが、半年間指導していただいた神戸大学大学院人間発達環境学研究科の大学院生8名の皆さんにも参加していただき、神戸高校との交流発表会で学んだことを生かして主体的な発表を実践した。各班前回の発表会での課題をひとつひとつクリアして、大学院生からもその成長した内容や表現に高い評価をいただいた。なお、発表テーマは以下の通りである。
1班 嶋田ゼミ 半永久的?!第二のカビキラー ~イオン液体のカビ予防効果の検証~
2班 西澤ゼミ 5時間後に意外な結果 ~環境DNAを用いたコイとオオクチバスの分布調査~
3班 西前ゼミ 君は麗しきシャボン玉の真相を見たか ~表面張力とシャボン玉の関係~
4班 冨田ゼミ どんなフードロスが豆苗を成長させる? ~コンポストを用いて調べる~
5班 松本ゼミ おさかなたちのバーコード集め ~環境DNAで獅子が池の外来種調査~
6班 小田ゼミ 町中の石の放射線量について調べる ~GM管を用いた調査~
7班 増田ゼミ 土壌のpHが猫草の生長に与える影響
8班 三谷ゼミ ジェルポリマーの吸収実験 ~イオンとの関係に迫る~






令和3年1月23日課題研究「神戸高校オンライン交流発表会」
本校HR教室において、本校創造科学科5期生(1年)40名が兄弟校でもある神戸高校総合理学科(1年)40名と最先端の自然科学探究活動の成果を発表し合う交流発表会をオンラインで行った。両校とも8つの班が5人グループ研究した内容を、それぞれ2班ずつ1会場で交流発表し、互いの研究から刺激を受けながら、白熱した質疑応答を行った。緊急事態
宣言が発出されたことで急遽オンラインでの発表会となったが、限られた環境の中で半年の研究の成果を懸命に伝え、神戸高校からも多くのことを学ぶことができた。



令和2年12月20日 甲南大学リサーチフェスタ
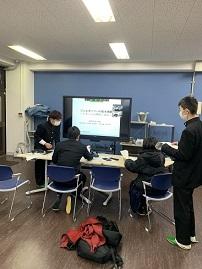


令和2年10月13日課題研究「院生ゼミ」






5班 松本・佐々木ゼミ 数理生物学入門
令和2年9月29日課題研究「院生プレゼン」