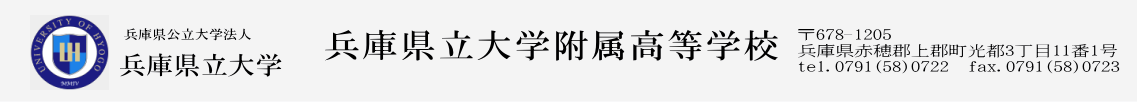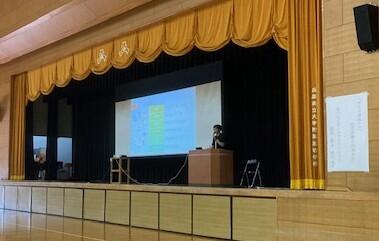保健室より
保健だより(1月)
季節にちなんだ行事食の代表、お節料理は日本文化の一つ。各行事の料理には、それぞれの意味が込められているようです。願い(縁起)、お祝い、お供えなど、それぞれの意味や由来があります。行事食に限らず、季節ごとの旬のものを食すことは、健康にとってもとても良いことです。冬の食材は身体を温めてくれ、免疫を高めてくれるものが多いので、感染症予防にもなります。普段の食事に取り入れる工夫をしてみましょう。
また、寒い季節には、体力維持やエネルギー補給に目を向け、自分の力を最大限に発揮できるようなコンディションをつくりたいものです。水分補給と同時に、バランスを意識して食材選びをしたいところ。日本人に不足しがちな栄養素、ビタミンD、カルシウム、鉄や食物繊維などの摂取については、サプリメントに頼りすぎず、日常の食事の中で出来るだけ補っていけると良いですね。
保健だより(12月)
冬の寒い季節は、家に閉じこもりがちですね。保健だよりにあるように、屋外での散歩や屋内でも体操・筋トレなど、軽くても体を動かことで、身体だけでなく、心も想像以上にリフレッシュします。
ゲームやネットも時間・場所で区切り、お休みの日も出来るだけ3時間までにとどめ、他の活動とのバランスをとりたいところです。生活習慣のルーティンで、食事や睡眠、充電中は離れ、生活行動にメリハリをつけるのがコツのようです。
また、休日でも、起きる時間は崩さず、長期の休みも時間を有効活用し、自己効力感を上げられるような達成目標をもとに、具体的な行動に変えていきましょう。
12月1日は世界AIDS予防デー。性について考える機会にしたいものです。
性感染症についても、予防行動が重要。最近では、梅毒は平成~令和にかけて4.6倍とかなり増えて、県内でも注意喚起され、県内のいきなりAIDS率も昨年の40.7%。本人がHIV感染を知らないまま、いきなり…ということも少なくないようです。
AIDSに関しては県内健康福祉事務所・保健所で、無料・匿名検査をしていますので、知っておいてください。(R7年8月から兵庫県HPから検査の予約申し込みが可能になりました)
『プレコンセプションケア』って?
性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザインや将来の健康を考えて健康管理をおこなうこと。「個人の健康と未来のこどもの健康の可能性を広げる」と言われています。
『性』は心が生きると書きます。これからの皆さんの人生の幅を広げ、心が生きるために、大切に考えていってほしいものです。
1年生対象に歯科保健教室をしていただきました。
今年度は『噛む』というテーマで、兵庫県歯科衛生士学院の皆さんから歯科保健教室を実施していただき、咀嚼力を調べるガムで自分の『噛む力』を試しました。
普段、噛むことはあまり意識しないかも知れませんが、噛むことが消化を助けたり唾液を多く分泌させたり、健康寿命や生活の質にも良い効果があるようです。また、受験期は食いしばりや歯ぎしりなど口腔の健康障害も起こりやすく、口腔ケアにもストレス対策が大事になります。普段のセルフケア・プロケアにリラックスやマウスピースで歯を守る対策もあり、嚙み合わせ矯正効果の実際もご紹介いただきました。
冬休み、年末年始、食生活のリズムにも気を付けながら、歯と口のセルフケア・プロケア習慣を継続し、新たな気持ちで良い年を迎えましょう!
保健だより(11月)
11月になり、寒い日が続き、空気が乾燥しています。風邪症状で保健室に検温をしに来る人が多くなりました。3年生は受験期に入っています。インフルエンザをはじめ色んなウイルスや細菌による感染症の拡大を招かないように、日頃から、手洗い・うがい・歯磨き・マスクの着用、免疫を高める食事や運動、睡眠で予防を心がけ、通学前の検温など、全体で感染予防にご協力いただけると助かります。
保健委員さんからの保健だよりで、薬の服用について触れられていました。何気なく一緒に飲む水ですが、きちんとした意味があります。薬が有効になるような飲み方をしていきましょう!
11月8日は「良い歯」の日でした。昨年度に歯科保健教育講演をしていただいた西真紀子先生から、歯磨剤「salutem」を少し試してみました。キシリトール配合の甘さがほんのりある優しい歯磨剤で、ミント味は無く自然な感じ、携帯にも良いと感じました。
覚えていますか?…歯磨き回数は一日2回~3回、丁寧に小刻みにやさしく歯磨き、 2222テクニック<一日2回・一回2分間、一回2㎝のF歯磨剤、ブラッシングは2時間歯を休ませる>、スラリー法(少量の水5ccくらいでうがい)
フロスや歯間ブラシは歯周病には有効ですが、1450ppmのフッ素配合の歯磨剤の使用だけでは、虫歯について完全には予防できません。砂糖を控えた間食回数制限、一日の飲食は5回までが理想など、自動販売機の飲料を含む日頃の飲食の内容に加え、飲食の回数がより大事になりますので、意識したいところです。
学校の歯科検診から約半年が経ちます。勉強や部活など何かと忙しい毎日ですが、甘いものを飲食することの多いクリスマス前に、かかりつけ医での定期検診など、年に2回は出来るだけプロケアで再点検し、是非、高校生の内に、日頃のセルフケアを確認する習慣をつけておきましょう!
保健だより(10月)
10月も半ばを迎え、長かった暑い夏から、ようやく秋らしい風景が感じられる頃となりました。一日は夜長へと向かいますが、陽光の中(含まれるバイオレットライト)、近隣の野山の葉が黄色や赤色に瞬く様子を日々目で追ってみる。そんな習慣が、目の健康(近視や眼精疲労)には良いようです。高校生の時期は歯の健康度低下と視力低下が身体の健康での主な課題です。時々は遠くを自然に見る習慣ができるといいですね。
①20-20-20ルールって知っていますか?(米国検眼協会と米国眼科学会推奨)
· 20分ごとに作業を区切る
· 20秒間、窓の外や部屋の奥など遠くを見る
· 遠くの距離は6メートル(20フィート)以上を目安
· 自習時に、タイマーやスマホアプリで通知すると習慣化しやすい
②環境の調整も意識しよう!
· 照明:机の明るさを300〜500ルクス程度に調整
· パソコン・タブレット使用時:画面周囲は500〜700ルクス(少し明るめ)が目安、ブルーライトカットも
· 姿勢・距離:本・ノートは30〜40cm、PC・タブレットは50〜70cm離す
· 画面位置:目線より少し下に設定
③まばたき・目の潤い
· 意識的にまばたきする
· 部屋が乾燥している場合は加湿器や人工涙液を使用
④ 短時間の休憩・ストレッチ
· 目を閉じる、上下左右にゆっくり動かす
· 軽く肩や首をほぐす(同時にストレッチ)
· ホットタオル(温め):目の疲れやドライアイに5分程度
· クーリング(冷やす):目の充血や腫れに3分程度
⑤良質な睡眠のために寝る前1時間は画面を見ない。
がん教育講演会を開催しました(9月中旬)
まつもとホームケアクリニック医師 松本直久先生より「がんと緩和ケア、在宅医療の現場から」と題し、全校生徒対象にご講演をいただきました。
足立校長先生からのがん罹患率・死亡率(統計)のご紹介に始まり、緩和ケア、症状、治療や麻酔、在宅医療、家族や周囲へのチームサポート、人生会議、意思決定、最期の体験談などの話題と共に、命の大切さ、日々の大切さを学んだひとときでした。「僕が生きる今日はもっと生きたかった誰かの明日かもしれないから」という歌詞と先生からの最後の言葉。講演の後、家族と話してみたり、職業の選択・設計という点からも示唆を受けたりした人もいたようです。
初めてのがん教育講演でしたが、ご講演の構成内容にも先生の温かな配慮が感じられ、とても感慨深い時間となりました。ご講演後は、スタッフの看護師さんと共にすぐに現場に向かわれました。お忙しい中、心のこもったご講演をいただき本当にありがとうございました。
※緩和ケアには、シシリーソンダース(英)が提唱した「Total pain」という概念や彼女が設立したホスピスSt. Christopher′s Hospiceの理念が広く世界中に影響を与えています。

保健だより(9月)
9月になりました。暑い夏から少しずつ秋の気配が増してきます。みなさんは健やかな日常に戻っていますか?まだまだ毎年、体育大会くらいまでは暑いので、熱中症対策はお互いに声かけて続けていけたら良いですね。
9月は夏の疲れがあっても、眠れずになかなか身体が休まらないかもしれません。日々の良眠対策で、質の良い睡眠を取ってこころも身体もオンにしていきましょう!(特に体内時計は意識したいところです。)
9月1日は防災の日でもあり、防災グッズを見直す月にしてもいいですね。災害避難ルートや集合場所、連絡先、今日の居場所を確認できるものを作ったり、事故やけが防止などの予防対策や準備物点検なども良いかもしれません。
夏休み前に西はりま消防組合の消防士の方々から恒例の救急法の実習をしていただきました。普通救命救急の認定を受けた人は、部活動の部員やクラスの人にも附属学校敷地内のAEDの場所(6か所)など伝えてあげてください。
お話の中で、いざという時、『一歩踏み出す勇気』を持つことが大切と言われていたのが、印象に残りました。
平成29年6月5日より
令和3年2月25日:983898