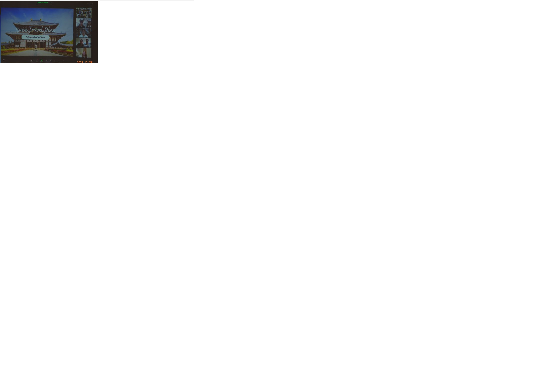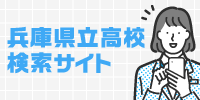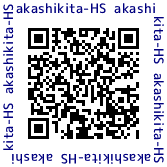SSHブログ
<SSH> STEAM研修(細胞解析装置・遺伝子解析装置を用いた研修実習)
12月13日に、医療機器メーカーであるシスメックスの施設見学へ行きました。最新の遠隔操作ができる機器を実際に操作させて頂き、大変貴重な体験となりました。ある生徒は「細かい動きまで機器の先端に伝えられるのを体験し、医療技術の進歩を感じた」と感想をくれました。また、医療現場で使用されている抗原を調べる機械や、PCRの機械など、詳しい解説とともに案内していただきました。初めて見学する企業の立派な研究室に感動した生徒も多かったようです。
<SSH> 令和5年度 科学講演会
奈良先端科学技術大学院大学 客員助教、MiRXES Japan株式会社 プロジェクトマネージャー (兼) サイエンティフィック アフェアーズ スペシャリストの金井 賢一先生をお招きし、「生命科学とは? 動物老化の理解を目指して」の演題でご講演いただきました。
生命科学や医療分野における最新の研究についてのお話は非常に難しかったですが、先生の研究テーマを中心に、研究に対するアプローチの仕方や、解析技術の基礎に関するお話をしていただきました。人の健康・長寿に関する研究にショウジョウバエを使っているという事を知り、多くの生徒が衝撃を受けました。
また、以下の生徒の感想にあるように、自分たちが授業の探究活動・課題研究で行っていることと研究者の研究活動が同じようなプロセスであることを知り、今後の探究活動・課題研究に活かしていこうと思います。
<講演会を聞いた生徒の感想(抜粋)>
・ 仮説の立て方など、今後の探究や授業で役立てそうな話をたくさん聞けたので、上手く活用できるようにしたいです。
・ 研究する中で自分で仮説を立てた内容が間違っていても、そこからまた新しい仮説が生まれ、新しい考えに発展していき、視野を広げていくことができるという、研究においての大切なプロセスを理解できた。
・ 今回の講演会で聞いた内容には課題研究にも関わるような内容もふくまれていたためこれからの実験に活かせるようにしたいと思った。
<SSH>文献調査に関する特別講義
11月16日(木) 文献調査に関する特別講義
本校SSH運営指導委員の兵庫医科大学薬学部准教授 木下 淳先生より、文献調査に関する特別講義をしていただきました。
これから課題研究を進めていくうえで必要な文献調査の方法、インターネット上にある情報の信憑性の判断、効率的な検索方法についてや、論文を引用する際の注意事項など、興味のある内容について検索を行う実習も含めての講義でした。また、生成AIの現段階の能力についても講義いただき、利用における注意点や問題点を知ることもできました。これから本格的に課題研究が始まる自然科学科1年生にとって、非常に有意義な時間となりました。
<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(立杭焼実習)
11月25日(土) 立杭焼実習(丹波篠山市今田 市野伝市窯・兵庫陶芸美術館・丹波伝統工芸公園「陶の里」)
丹波立杭焼は日本六古窯(瀬戸、常滑、信楽、備前、越前)のひとつ。その発祥は平安時代末期から鎌倉時代のはじめといわれ、現存する日本最古の登窯を目の当たりにし、そのすぐ近くの市野伝市窯にて、市野さんの丁寧なご指導の下、陶芸体験をしました。
豊かな自然に囲まれた丹波焼の郷での体験は、良質な土、きれいな川の水、その他適切な自然条件がそろう土地でこそ可能なものであり、それが人の手によっておよそ850年受け継がれる伝統の継承の重要性を感じながら、思い思いに創意工夫を凝らし、作品を制作しました。
また、兵庫陶芸美術館・丹波伝統工芸公園「陶の里」では芸術的な数多くの作品を目の当たりにし、受け継がれてきた技術の崇高さを感じるとともに、中には最新の科学技術との融合を感じさせてくれるものもあり、五感に語り掛けてくる一つ一つの作品に圧倒され、素晴らしい体験となりました。
<SSH> 咲いテク事業 「第4回データサイエンスコンテスト 決勝」に参加してきました。
10月29日 データサイエンスコンテスト(会場:兵庫県立大学の商科キャンパス)に2年生の自然学科生二人で参加してきました。
当日までに約半年間にわたって、テレビ会話システムを使い、チームを組んだオーストラリア・台湾の学校からそれぞれ2名ずつ、本校の生徒を加えて合計6名のチームで、旅行ビジネスプランを作成してきました。書類選考で予選を通過した4チームの一つとして発表をしてきました。発表も当然テレビ会話システムで行われました。司会も、質問も英語、すべて英語で進行します。画面全体に映る自分たちのプランを6人で分担して、英語で説明を行いました。審査結果発表も英語でした。2位になりました。
明石北高校ホームページ