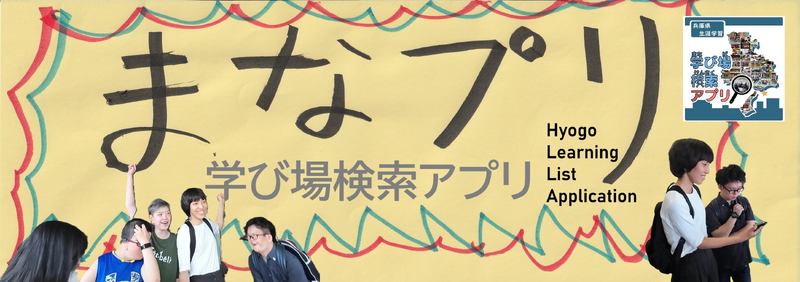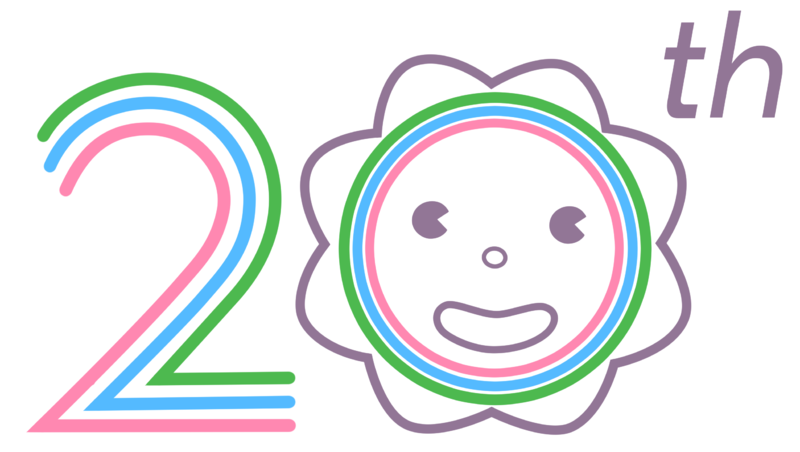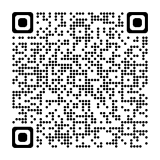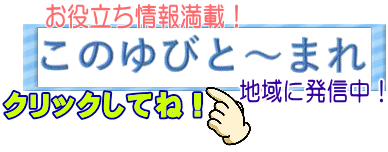給食だより
令和7年12月16日(火)の給食
*麦入りごはん
*牛乳
*大根と豚肉のみそ煮
*かぼちゃのサラダ
*湯葉のすまし汁
今日の煮物に使った大根は、本校の校区でもある、たつの市御津町産のものでした。
たつの市御津町には、農作のために海の水を抜いて陸地にした「干拓地」があります。
揖保川の河口にある「干拓地」の「成山新田」では、大根やにんじんを多く栽培し、県内最大の産地とされています。
砂が混ざった土で大きく育ち、やわらかくて甘い大根ができます。
クラスを回ってこのことを伝えると、「〇〇くんが住んでるところ!」「僕が住んでるところです」など、自分の地元のものということで、少しうれしそうな様子でした。
令和7年12月15日(月)の給食
*麦入りごはん
*牛乳
*豚肉のパン粉焼き
*カラフルピーマンのソテー
*わかめのスープ
今日のソテーには、赤・黄・緑の3種類のピーマンを使いました。
ピーマンは、β-カロテンやビタミンCを多く含みます。
これらの栄養素は、免疫力を高め、風邪から体を守ってくれます。
β-カロテン:皮膚やのど・鼻の粘膜を強くする
ビタミンC:皮膚や血管を強くする
2学期も残り10日を切りました。
最後まで元気に過ごせるよう、しっかり食べて風邪に負けない体をつくりましょう。
令和7年12月12日(金)の給食
*麦入りごはん
*牛乳
*さばのソース焼き
*切干大根の煮物
*ほうれんそうのみそ汁
今日は和食の献立でした。
本校では和食の献立が人気で、今日も「さばがおいしかった!」「煮物がおいしかったです」など、様々な感想が聞かれました。
お昼の放送では「さば」についてお話ししました。
さばなど、魚に含まれる油は健康に良いとされています。
血液をサラサラにして詰まりにくくしてくれたり、脳を活性化する成分が入っていたりします。
これらの油は、豚肉や牛肉などの肉類にはほとんど含まれず、魚に多く含まれています。
今日のさばもよく脂がのっていて、おいしくいただきました。
令和7年12月11日(木)の給食
*麦入りごはん
*牛乳
*麻婆豆腐
*青じそ風味和え
*長ねぎのスープ
今日は中華の献立でした。
和え物は今年度初登場のメニューで、青じそ入りのドレッシングを使い、さっぱりと仕上げました。
お昼の放送では、青じそについてお話ししました。
青じそは薬味として使われることが多く、細かく刻んで色どりや香りを足してくれます。
また、刺身の盛りつけにも使われることが多く、魚のにおい消しや殺菌効果などがあります。
初登場の青じそ風味和えでしたが、ささみ肉が入るなどボリュームもあり、よく食べている様子でした。
令和7年12月10日(水)の給食
*もずくどんぶり
*ぎゅうにゅう
*ポテトサラダ
*大根のみそ汁
*みかんゼリー
今日は、冬が旬の食べ物として「大根」と「みかん」を取り入れました。
もずくどんぶりは、もずくとささみ、たくさんの野菜を、中華風に味付けしたもので、隠れファンも多い一品です。
お昼の放送では、旬についてお話ししました。
旬とは、食べ物が一番多く収穫され、新鮮でおいしく食べられる時期のことを言います。
おいしさのほかに、栄養価も高いなど、良いことがたくさんです。
冬が旬のものを食べて、季節を感じ、体も心も元気に過ごしましょう。
令和7年12月9日(火)の給食
*麦入りごはん
*牛乳
*ポークビーンズ
*野菜のごまドレッシング和え
*コンソメスープ
今日は豆をたっぷり使った、ポークビーンズがメインの献立でした。
ポークビーンズは、アメリカの家庭料理で、豆と豚肉をトマトで煮込んだ料理です。
アメリカでは、白いんげん豆を使うことが多いですが、今日の給食では、大豆を使用しました。
大豆は、苦手とする児童生徒がやや多い食材です。
つかみにくい、食感や味が苦手などが理由として挙げられます。
しかし、栄養面で見ると、たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラル類も豊富に含むため、積極的に取り入れたい食材でもあります。
給食では煮物以外に、児童生徒が好むケチャップ味やカレー、サラダなどに取り入れるなどの工夫をしています。
令和7年12月6日(土)の給食
*カレーライス
*ジョア(ブルーベリー)
*鶏肉ときゅうりの甘酢あえ
今日は、小・中学部の西はりま祭でした。
食べやすいように、カレーライスの献立にしました。
お昼の放送では、乳酸菌についてお話ししました。
乳酸菌は私たちの腸にも存在し、外から入ってきた菌や毒を追い払ってくれます。
からだを守って健康にしてくれる菌なので、「善玉菌」とも呼ばれます。
風邪が流行る時期、乳酸菌を含むものを食べて、からだの内側(腸)から免疫力を高めていきましょう。
令和7年12月5日(金)の給食
*麦入りごはん
*牛乳
*白身魚フライ
*ひじきとツナのサラダ
*コーンスープ
今日はお昼の放送で、牛乳についてお話ししました。
給食に毎日牛乳がある理由は、カルシウムをしっかり摂るためです。
成長期には、骨を作る材料であるカルシウムがたくさん必要になります。
特に、中学部・高等部のみなさんが1日に必要な量は以下のとおりです。
中学部男子1000mg 女子800mg
高等部男子800mg 女子650mg
牛乳200mlには、カルシウムが226mgも含まれています。
寒くなってくると牛乳の消費量が減ると言われています。
家庭でも、シチューやグラタン、クラムチャウダー、ポタージュなど、温かい料理に取り入れてみてはいかがでしょうか。
令和7年12月4日(木)の給食
*パン
*牛乳
*野菜たっぷり焼きそば
*中華スープ
*いちごヨーグルト
今日のメインは焼きそばでした。
パンにはさんで焼きそばパンにできるように、パンの日に取り入れました。
パンや焼きそばの麵は、炭水化物が多い食べ物です。
炭水化物だけを食べ過ぎると、栄養バランスが悪くなり、エネルギーの摂りすぎ、肥満などにもつながります。
そのため、今日の焼きそばは、麺の量よりも野菜の量が多くなるようにしました。(献立名も”野菜たっぷり焼きそば”です)
たんぱく質は、焼きそばに豚肉を入れたり、デザートにヨーグルトを取り入れたりして補いました。
普段の食事も、栄養バランスを意識しましょう。
令和7年12月3日(水)の給食
*豚丼
*牛乳
*小松菜とちくわの和え物
*かぶの卵スープ
今日は秋~冬が旬のかぶを使ったスープでした。
かぶは淡泊な味わいなので、ベーコンや卵を加えて、うま味を足しました。
お昼の放送では、かぶについてお話ししました。
かぶは種類がとても多く、白色の他に赤色や紫色のかぶもあります。
大きさも様々で、小さいもので5cm程度のものから、大きいものでは30cm以上のものがあります。
今日の給食では、白色の直径10cm程度のかぶを使いました。
クラスを回っていると、「かぶはトロっとしていて柔らかい」といった感想が多く聞かれました。