2025年2月の記事一覧
第23回総合学科発表会
令和7年1月25日(土)、第23回総合学科発表会が開催されました。本発表会は、1年次「産業社会と人間」、2・3年次「課題研究」に加え、さまざまな授業で取り組んできた学習活動の成果を発表する場です。「産業社会と人間」や「課題研究」でお世話になった企業・大学関係者の方々をお招きし、神戸市内の中学校から40名以上の中学生に来校いただきました。
ステージ発表の前半の部では、特色ある授業の成果発表として「保育声楽・器楽演奏・ソルフェージュ」選択生徒によるヴォーカルアンサンブル&ピアノ連弾が披露されました。続いて、1年次「産業社会と人間」より代表者による成果発表、2年次「課題研究Ⅰ」より代表者による体験発表が行われました。
そこから場所を教室に移し、1年次の全グループがクロスカリキュラム探究のポスター発表と、2年次全員による課題研究のポスターセッションが行われました。生徒それぞれが自分自身の学びを他者に伝えるという行為を通して、自信を培ったり、達成感を感じられる体験になったと思います。また、他者の発表を通して、2年次は自分の研究をより深めたいと考えたり、1年次は次年度の課題研究が楽しみになったりと、前向きな意欲を感じることもできました。
授業成果物の展示発表は、セミナールームで行い、生徒たちはポスター発表の間に時間交代で見学しました。多種多様で個性的な成果物が展示されており、総合学科で育まれる個の力を感じる内容でした。
ステージ発表の後半の部では、県立神戸甲北高等学校の生徒をお招きし「総合的な探究の時間」の発表が行われました。本校と同じ総合学科高校として、このような交流・発表の機会を通して刺激をもらうことができました。最後には、3年次「課題研究Ⅱ」より代表生徒による発表が行われ、研究のプロセスはもちろん、発表の仕方やプレゼンテーションのスライドまで、発表を見る人が分かりやすいように工夫されていました。
講師の先生方による講評の中で、学びを深めていくためのポイントとして「多角的に物ごとを見ていく」「意味がある・役に立つということから離れて面白さを見出す」「分からないことを面白がる」というお話がありました。ぜひ今回の発表会の経験を踏まえて、さらに探究していってほしいと思います。
〈生徒感想〉
・今までしてきたことの発表が見られて良かった。自分のポスター発表や他の人の課題研究を通してアドバイスをもらったり、新しい気づきができた良い機会となった。(2年)
・友が丘の生徒がどのようなことに興味関心をもって研究に取り組んでいるのか、またどのような経験や考えに基づいてテーマを決めたのかを聞くのが楽しかった。(2年)
・生徒の努力の成果がよく見られた1日で、特に2年生のポスター発表では、今後の自分に活かせるところが多くあった。来年自分も研究するので、先輩のアイデアを吸収していきたい。(1年)
・いろんな人の発表を聞くことで、新たな発見や知識を得ることができ、考えを深められたので良かったです。2年から始まる課題研究も頑張りたいです。(1年)
〈来場者感想〉
・「総合学科」というだけあって、本当に様々な領域について勉強していらっしゃるのだと感じました。また、学年が上がるにつれて研究のプロセスや導くものがはっきりとしていき、発表の内容や質も著しく向上しているがよく分かりました。この学校の教育プロセスの素晴らしさとそれに応える生徒のみなさんの力は他の学校ではなかなか見られないものだと考えます。(企業・大学関係者)
・実社会では正解のない問題がほとんどで考える力が大切です。こういった総合学科で学んでいることが、社会に出て考える力につながるのではないかと思います。そういった取組が教育の現場でおこなわれているのが見られて本当に良かったと感じました。(企業・大学関係者)
・3年間見てきましたが、毎年違ったテーマで面白い。保護者はもっと見にきたらいいのにと思います。(本校保護者)
・自分があまり目を傾けない部分の研究を行っている人が沢山いてほかの価値観を感じとても面白かったです 。また、研究を通しての発見を深堀することやデータ化し分かりやすくするなど一人一人の個性を感じられて、とても充実した時間を過ごすことが出来ました。(中学生)
オープニング「保育声楽・器楽演奏・ソルフェージュ」ヴォーカル・アンサンブル&ピアノ連弾 開会挨拶


1年次「産業社会と人間」発表


2年次「課題研究Ⅰ」体験発表 1年次「産業社会と人間」クロスカリキュラム探究 ポスター発表


2年次「課題研究Ⅰ」ポスターセッション


県立神戸甲北高等学校 発表 3年次「課題研究Ⅱ」発表


作品展示


講評 閉会挨拶


甲南大学リサーチフェスタ2024
12月15日(日)、本校においてオンライン(zoom)で「甲南大学リサーチフェスタ2024」が行われ、本校から2年次の生徒4名(2組の塚本蓮仁さん、5組の岡崎志穂さん、梶村葵衣さん、松下潮奏さん)が参加し、スライドで課題研究の成果を発表しました。
質疑応答を含めて合計9分の持ち時間で、午前にリハーサル2回、午後に本発表3回、合計5回の発表をやり遂げました。最初はペース配分やパソコンの操作等に戸惑いましたが、回を重ねるごとにコツを掴み、本発表は司会進行・発表ともに上達し、段取り良く場を仕切ることが出来ました。
また、自分の発表を聞いてもらうだけでなく、自分自身も、他校の発表3グループ分の審査に参加しました。4つの観点別の点数付けに迷いながらも、自身が審査員を務めることで客観的に見る力が身についたのではないかと思います。また、積極的に質疑応答に参加する頼もしい姿が印象的でした。16:40に閉会式を迎え,長い1日が終わりました。
〈生徒の感想〉
・他校のみなさんの発表は,表やグラフを使ってわかりやすくまとめていたものが多かったように思います。参考になりました。
・たくさんのアドバイスをもらったので今後の研究に生かして行きたいと思います。


中・高生 探究の集い2024
12月14日(土)、関西学院高等部の西宮上ケ原キャンパスにおいて「中・高生 探究の集い2024」が開催されました。本校からは、4組の高原夏海さんが「コンテスト部門」でスライドを用いた口頭発表、2組の栄田怜央奈さん、竹本栄太さんがオープン部門でポスター発表を行いました。
午後のプログラム「交流会」では、全国各地(北は栃木県、南は高知県)から発表に来た学生の皆さんとともにグループディスカッションを通して親睦を深めることができました。閉会式には関西学院大学の中央講堂に集まり、コンテスト部門の結果発表と表彰式、大学の先生方からの講評とがあり、最後に集合写真の撮影がありました。全国の生徒の皆さんとの交流から多くの刺激を受けた一日となりました。


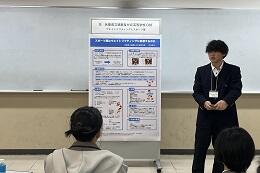
リサーチ・フェア2024 in 関西学院大学総合政策学部
11月16日(土)、関西学院大学総合政策学部(神戸三田キャンパス)において今年で27回目となる「リサーチ・フェア2024」が開催され、本校から2組の藤岡七海さんが参加しました。
持ち時間25分(発表15分,質疑応答10分)を余すことなく使い、大学の先生方からの質問に丁寧に返答しました。他校の生徒の発表や、関西学院大学総合政策学部の生徒の発表もあり、質疑応答にも積極的に参加するなど充実した1日となりました。
1年次「産業社会と人間」ジブシる(カタリ場)
12月12日(木)、1年次生が「ジブシる」の出張授業を受講しました。
大学生の先輩たちの明るい挨拶で始まった今年度の「ジブシる」では、先輩たちの経験談を聞いていくうちに、初めは緊張していた生徒たちも、次第に打ち解け、楽しそうに先輩たちの話に耳を傾けている姿が多く見受けられました。
先輩の話の中には、自らの悩みと直結する話や、今後の学校生活に活きる話がありました。そこから、勇気をもらったり、今後に向けてのヒントを得たり、中には、これからの生活でがんばりたいことを「先輩」と約束している生徒もいました。
生徒たちから見て身近なロールモデルとして、大学生の先輩たちとふれあい、将来の自分の像とも重ね合わせることができ、大きな刺激になったようです。今回の授業で感じたこと、決意した気持ちを忘れず、それぞれの目標達成のために高校生活を送ってほしいです。
〈生徒の感想〉
・自意識をうまく理解しながら、環境要因を言い訳にせずに、自分を見つめ直していきたいなと思いました。また、人生を楽しく過ごす環境について、私は自分の居場所に執着するのではなく、自分を忘れず、自分の居場所を作っていけるような行動が大切だと気づくことができました。
・これからの人生の中で、やりたいことや将来の目標は、どんどん変わっていくかもしれないし、ずっと変わらないけど、「やってみる、飛び込んでみる」と「自分を知る」ことはどんなことにも言えるので、今後も大切にしていきたいと思いました。
・自分を見つめ直し、振り返り、お話を聞いたことによって、自分では気づいていなかった悩み事に気づけたことや、今まで納得できていなかった考え方を理解することができました。新しい自分になれたようで、今回の時間はすごくいい経験になりました。


1年次「産業社会と人間」クロスカリキュラム探究④
12月12日(木)、1年次「産業社会と人間」の授業で、クロスカリキュラム探究の成果発表を行いました。今年度のクロスカリキュラム探究では、異なる教科の教員同士がコラボし、また生徒たちがフィールドワークなどで地域社会に出かけ、実際の専門家とつながることをねらいに実施してきました。
班のメンバーで協力して、学んだ成果をまとめたポスターからは、生徒たちが学んだことが、分かりやすくまとめられており、今回の取り組みでの生徒の成長を読み取ることができました。実際の現場に出て実社会の問題に向き合った生徒たちは、入学した時より逞しく見え、また発表している姿からは、来年度行う課題研究に向けて、準備ができていることを感じさせられるものでした。
今回のクロスカリキュラム探究で興味が湧いたもの、疑問に思ったこと、もっと調べたいと感じたものなどを忘れず、今後の学習活動に活かしてほしいと思います。
〈生徒の感想〉
・自分たちが調べたことをまとめ、何も知らない人に理解してもらうことは難しいことだなと思いました。分かりやすく伝えるためには、文字の配置や色、文字の大きさ、量など、工夫するべきところが多いと気付かされました。
・私たちの班では、ずっと一方的に話していただけなので、聞いている人たちにとっては分かりづらかったのではないかと思いました。次このような機会があったときには、クイズや質問を投げかけながら、一歩的な発表にならないようにしていきたい。
・クロカリの授業では、最初は内容が分からず、難しいのかなと感じていたけれど、1回1回の授業でより深い内容を知ることができたり、興味を持つことができました。他の班の発表を聞いて、色々な分野の色々な良さを知ることもできました。














