授業風景
カテゴリ:今日の出来事
ANZAC Day
きょう4月25日はANZAC Day。
オーストラリアやニュージーランドでは平和を祈念する大事な日とされています。
須磨東家庭科もANZAC Dayに心を寄せよう!ということで、この日にちなんだお菓子「アンザック・ビスケット」を作りました。

化学実験、始まる。
本日、新年度初めの化学実験がスタートしました。
内容は、高校1年生 化学基礎 の『物質の分離・精製』から、蒸留(分留)をテーマに実験を行いました。

高校に入学して、初めての実験ということもあり、みんなが担当教員の話を集中して聞いていました。

枝付きフラスコをセットする、リービッヒ冷却器をセットする、データを記録する、などなど、それぞれ班で分担を決めて、実験に取り組んでいました。
ゴム管を繋ぎ間違えるなど、小さなミスはありましたが、怪我もなく無事終了しました。
これからも、少なくとも学期に1回、2年生になれば文型でも理型でも実験頻度が多くなり、危険も増しますので、器具の使い方をマスターしてもらいたいと思います。
内容は、高校1年生 化学基礎 の『物質の分離・精製』から、蒸留(分留)をテーマに実験を行いました。

高校に入学して、初めての実験ということもあり、みんなが担当教員の話を集中して聞いていました。

枝付きフラスコをセットする、リービッヒ冷却器をセットする、データを記録する、などなど、それぞれ班で分担を決めて、実験に取り組んでいました。
ゴム管を繋ぎ間違えるなど、小さなミスはありましたが、怪我もなく無事終了しました。
これからも、少なくとも学期に1回、2年生になれば文型でも理型でも実験頻度が多くなり、危険も増しますので、器具の使い方をマスターしてもらいたいと思います。
ニワトリ発生の観察
~氷上高校の卵を使って実験~
2年「生物」では「生殖と発生」の単元で、ニワトリやウズラの卵を使って鳥類胚の観察をしています。
今年も、兵庫県立氷上高等学校で生産されたニワトリ有精卵を購入しました。
県内の高校生が自信を持って提供している素材を実験に使わせてもらう、ということも、本校生にとっては大きな刺激になります。


インキュベーターで孵卵します。卵には孵卵時間と胚の位置がわかるように印を入れています。
2月13日(月)4時間目に、理型生物選択者のクラスで初期胚の観察を行いました。


胚を「ろ紙リング」にくっつけて取り出し、ゲルプレートに乗せて、双眼実体顕微鏡で観察します。


どの生徒も非常によく集中し、丁寧に胚を取り出すことができていました。
互いに発生段階の異なる胚を比較したり、細かく観察してスケッチしたりしました。
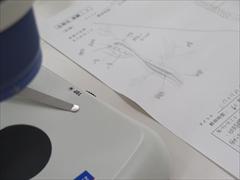
今回はニワトリで行いましたが、ウズラを使った方法は、本校で教材開発を行い、
高校「生物」の教科書にも掲載されています。
実習の方法など、詳しい資料は、
「須磨東 理科実験教材の広場」(旧HPのコーナー)で
紹介しています。
【生徒の感想より】
*顕微鏡を使って見てみると、体節や脊索がくっきり見えて、こんな小さなときから体って成り立っていくんだなーと改めて思いました。背と腹の両面から観察することができ、背側の方が体節が見やすかったです。他の人のを見ると、時期によって発達してるところが違って、比較するのが面白かったです。
*はじめ、卵を割ったときに膜まで割れてしまったときは、失敗してしまったと思ったけど、何とかリカバリーできて、実験を成功させることができてよかった。胚を見てみると、眼胞や心臓、耳胞など、前の方にある器官ばかりができているので、発生の過程は基本的に前の方から進むのではないかと思った。
*心臓がゆっくりと動いているのも確認できたのでよかったです。この胚がヒヨコになり、ニワトリになるんだと、頭ではわかっていても、少し理解が遅れるというか、本当になるんだなぁと感動しました。
*胚を見ただけではこれが何で…というのは分からなかったけれど、図を見ながら自分の胚を見てみると、よく分かり、観察しやすかった。先生は胚を見るだけで分かっていたので本当にすごいと思いました。
*とてもきれいに胚が見られて嬉しかったです。班の人たちの胚と見比べると、自分が取り出した胚の方が目が出ているな、とか、神経管が閉じられていく様子など、違いが分かって面白かったです。心臓が飛び出していることに驚きました。
2年「生物」では「生殖と発生」の単元で、ニワトリやウズラの卵を使って鳥類胚の観察をしています。
今年も、兵庫県立氷上高等学校で生産されたニワトリ有精卵を購入しました。
県内の高校生が自信を持って提供している素材を実験に使わせてもらう、ということも、本校生にとっては大きな刺激になります。


インキュベーターで孵卵します。卵には孵卵時間と胚の位置がわかるように印を入れています。
2月13日(月)4時間目に、理型生物選択者のクラスで初期胚の観察を行いました。


胚を「ろ紙リング」にくっつけて取り出し、ゲルプレートに乗せて、双眼実体顕微鏡で観察します。


どの生徒も非常によく集中し、丁寧に胚を取り出すことができていました。
互いに発生段階の異なる胚を比較したり、細かく観察してスケッチしたりしました。
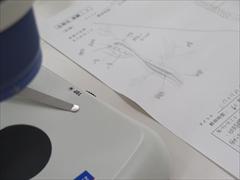
今回はニワトリで行いましたが、ウズラを使った方法は、本校で教材開発を行い、
高校「生物」の教科書にも掲載されています。
実習の方法など、詳しい資料は、
「須磨東 理科実験教材の広場」(旧HPのコーナー)で
紹介しています。
【生徒の感想より】
*顕微鏡を使って見てみると、体節や脊索がくっきり見えて、こんな小さなときから体って成り立っていくんだなーと改めて思いました。背と腹の両面から観察することができ、背側の方が体節が見やすかったです。他の人のを見ると、時期によって発達してるところが違って、比較するのが面白かったです。
*はじめ、卵を割ったときに膜まで割れてしまったときは、失敗してしまったと思ったけど、何とかリカバリーできて、実験を成功させることができてよかった。胚を見てみると、眼胞や心臓、耳胞など、前の方にある器官ばかりができているので、発生の過程は基本的に前の方から進むのではないかと思った。
*心臓がゆっくりと動いているのも確認できたのでよかったです。この胚がヒヨコになり、ニワトリになるんだと、頭ではわかっていても、少し理解が遅れるというか、本当になるんだなぁと感動しました。
*胚を見ただけではこれが何で…というのは分からなかったけれど、図を見ながら自分の胚を見てみると、よく分かり、観察しやすかった。先生は胚を見るだけで分かっていたので本当にすごいと思いました。
*とてもきれいに胚が見られて嬉しかったです。班の人たちの胚と見比べると、自分が取り出した胚の方が目が出ているな、とか、神経管が閉じられていく様子など、違いが分かって面白かったです。心臓が飛び出していることに驚きました。
住所・電話番号
〒654-0152
兵庫県神戸市須磨区
東落合1-1-1
電話 078-793-1616
(停電時の電話は078-793-1617)
FAX 078-793-1617
https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/sumahigashi-hs/NC3/
アクセスカウンター
5
4
5
2
3
2
0


