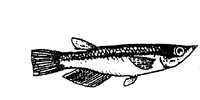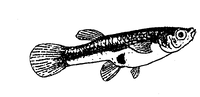兵庫県立北須磨高等学校
〒654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘9丁目23番地
Tel:078-792-7661 Fax:078-792-7662
E-mail:kagakubukai@hyogo-c.ed.jp
分布
北海道を除く日本の各地に分布し、大きさ4cmになるメダカ科の魚。池や川水田、用水路などの流れのゆるい水草がたくさんある所に多く住んでいる。
産卵
産卵期は5月~9月、水温が20℃以上あれば1年中産卵する。卵の直径は1.0~1.5mm で全体に毛があり一部は馬の尾のように長くなっている。メスは産んだ卵を、しばらくの間おしりに付けて泳いでいるが、やがて水草などにこすりつけて、卵をバラバラに付着させる。
メダカは温度・塩分などに対する抵抗力が強く、海岸・塩河の溝などで産卵するものもある。
雌雄
受精卵を得るには雌雄の個体が必要である。外見上雌雄の差の著しいのは尻びれで、メスのそれは小さく、後方にゆくほど幅がせまい。オスの尻びれは大きく全長にわたりほぼ同じ幅で平行四辺形のような形をしている。またオスの背びれには切れ込みがあるが、メスにはない。
種類
在来のメダカはクロメダカ、飼育品種にはヒメダカ、シロメダカ、アオメダカがあり、採卵用としては野生のクロメダカよりはより優れている。
1)飼育
ⅰ.水槽
・メダカは室内より外で飼育する方が手がかからない。太陽の直射の下で、緑藻の生えた自然の池で飼育すると、いちばん健康なメダカができる。
室内で飼育するには水槽が必要で、何でも良いが、抗菌仕様は不可。金属製の入れ物や、水槽の内側に金属の出ている入れ物は魚を殺してしまうので、使用してはいけない。
・魚は空気からとけ込んだ酸素を呼吸に使うので、水面が広いほど酸素がよくとけ込む。直径20~30cm、深さ15~20cmのガラスまたはプラスチックの水槽や空き瓶が利用できる。
ⅱ.入れるメダカの数
・水槽の形にもよるが、1リットルの水に2~3尾、多くても10尾ぐらいまでの割合が望ましい。
・メダカはテリトリーを作る関係上、魚の密度はかなり小さくするか、大きくするかのどちらかで、中途半端はいけない。密度が大きいということはテリトリーを作りにくいので喧嘩が無い。また密度が小さいということは、充分に自分の領域があるということになる。水量で調整してやるとよい。
ⅲ.水
・水道水を1~2日放置して自然に塩素が無くなるのを待つ。急ぐときはチオ硫酸ナトリウム(市販のハイポ)を入れる。
・井戸水はそのまま使用する
・メダカの適温は20~30℃ぐらいだが普通の室温で飼育すればよい。
・1日に2~3時間日光のあたる場所で飼育するのが理想的ではあるが、夏季は極度の高温になることは避けるようにする。気温が高い時期は水が汚れやすいので、しばしば水を取り替える必要があるが、水温の急変は有害なので、水替えは、全部を一度に替えず、半分くらいにしておき、水温差は5℃以内にする。
ⅳ.餌
・イトミミズ、ボウフラ、ミジンコなどがよい。「メダカのエサ」も市販されている。「金魚のエサ」をつぶして与えてもよい。与えすぎると水質が悪化しやすいので、1回5分くらいで食べ切れる量を1日2~3回与える。
ⅴ.その他
・水量によってはエアーをいれてやるとよい。
・体表にカビや寄生虫がついていれば、殺菌のため、薄いメチレンブルー液にしばらく入れておく。(3~6日)
・ストレスを少なくしてやるために水草などを入れて陰をつくってやる。水草の光合成も利用できる。
・メダカは変温動物なので冬の寒い間はじっとしていてエサも食べないが、温度を上げてやると活動する。
・直射日光が長く当たると水温が高くなりすぎ魚が死ぬ。また、日光が全く当たらないところでは水草が枯れるので、育成灯をつけてやる。
2)留意点
|
ⅰ.メダカを飼育していると、春と秋には受精直後の卵を採集して |
 |
ⅱ.メダカとカダヤシ
カダヤシは北アメリカ原産でメダカとよく似た魚だが、卵(卵生)ではなく子供を産む(卵胎生)別の種顆。蚊の幼虫をよく食べ蚊を退治してくれるので、あちこちで放流されている。
| メダカの雄 | カダヤシの雄 |
|
シリビレのはばが広い セビレの後ろに切れ込み |
シリビレが細長い(交接器となっている) |
|
メダカの雌 |
カダヤシの雌 |
|
シリビレのはばがせまい 体が太い |
子どもを持つと色が黒くなる 体が大きく広い |
ⅲ.メダカとカダヤシのテリトリーについて
多くの淡水魚はなわばりを作る。また順位現象が見られることもある。メダカなどでは、最強のものが底近くへ、次の集団が中層へとなわばりを作り、最も弱いものは表層に押し上げられる。また中層には順位的ななわばりといえそうなものを、作らせることもできる。この場合、一番強そうなものを水槽から取り除くと、その場所に次の強いものが入り、順々になわばりの持ち主がかわって、最後の空席には、表層でなわばりを持っていなかったものの1尾が入るというような変化もおこる。