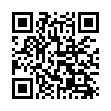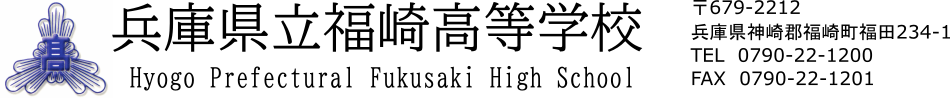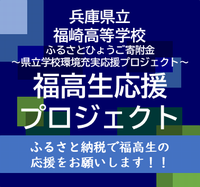2021年10月の記事一覧
令和3年度 第15回講座
講座「チーム医療」の15回目が、10月26日の6限目と7限目に実施されました。
15回目の講座は、姫路獨協大学薬学部医療薬学科の杉本由美教授にお越しいただき、講義をしていただきました。
今回のテーマは、「薬剤師の仕事、チーム医療における役割」。薬剤師になるために必要な能力を知り、チーム医療における薬剤師の仕事を学びました。
講義前半は、姫路獨協大学薬学部での学びと薬剤師の仕事について教えていただきました。薬学部は6年制教育であり、どのような学びや実習が行わているのかを学びました。薬局での患者対応については実際に実習動画を見ながら学び、薬局で投薬を行う前に患者に尋ねることとその目的について知ることができました。
講義後半は、チーム医療における薬剤師の役割について教えていただきました。医療が高度化し、複雑化した専門的な能力が求められる現在の医療現場ではチーム医療が必須であり、薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが非常に有益であることを学びました。
次回は、11月2日に福崎町保健センターから保健師さんにお越しいただき、講義をしていただきます。


令和3年度 第14回講座
講座「チーム医療」の14回目が、10月12日の6限目と7限目に実施されました。
14回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部言語聴覚療法学科の森澤広行先生にお越しいただき、講義をしていただきました。
今回のテーマは、「言語聴覚士の仕事とチーム医療における役割」。リハビリテーション専門職の「言語聴覚士」の仕事を詳しく説明していただきました。
講義前半は、言語聴覚士の担当する障害やどのような場所で活躍しているのかを学びました。言語聴覚士は子どもから高齢者までの幅広い年代の障害に携わり、活躍の場も多岐にわたることを教わりました。また、言語聴覚士の資格を取得するために必要なことを学び、言語聴覚士の仕事のイメージをつかむことができました。
講義後半は、脳と人間の活動について実習を交えながら学びました。脳を活性化させる方法を体験しながら、言語聴覚士の具体的な仕事内容を教えていただきました。また、動画を見ながら誤嚥性肺炎の危険性を教えていただき、食べることの大切さを実感しました。
次回は、10月26日に「薬学」について学びます。


令和3年度 第13回講座
講座「チーム医療」の13回目が、10月5日の6限目と7限目に実施されました。
13回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科の小野泉准教授にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「作業療法士の仕事、チーム医療における役割」。
昨年度は作業療法士が関わる車イスについて説明をしていただきましたが、今年度は「補装具」について詳しく説明をしていただきました。「補装具」には、義肢や装具などさまざまな種類があり、その目的について学びました。
また、補装具の中でも「義手」を中心にさらに詳しく教えていただきました。義手は機能によって、装飾用・作業用・能動用の3種類が存在し、能動用の中に筋電義手があることを教わりました。そして筋電義手の仕組みを実習を通して、実際に義手を操作しながら学びました。
さらに、随意運動で機関車を走らせる実習では、こめかみに付けた装置で電気機関車を動かすことができ驚かされました。お箸の自助具の操作も実際に見学することができ、実習を通して補装具の理解を深めることができました。
次回は、10月12日に「言語聴覚療法」について学びます。


令和3年度 第12回講座
講座「チーム医療」の12回目が、9月28日の6限目と7限目に実施されました。
12回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部理学療法学科の山本洋之教授にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「理学療法士の仕事、チーム医療における役割」。
講義前半は、チーム医療に関わる専門職の説明を中心に作業療法士の仕事を説明していただきました。臨床工学技士、言語聴覚士、作業療法士、そして理学療法士が患者に対して具体的にどのような役割を担っているのかを分かりやすく教えていただきました。
特に理学療法と作業療法の違いについて、理解を深めることができました。
講義後半は、理学療法士の仕事を体験しました。先生が実際に使われている道具の説明やパルスオキシメーター(酸素濃度計)を使った実験を行いました。パルスオキシメーターを使った実験では脈拍数と酸素濃度を計測して、体内に酸素が運ばれる時間を知ることができました。
次回は、10月5日に「作業療法」について学びます。