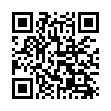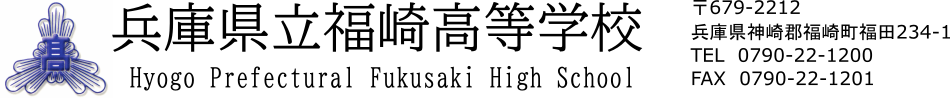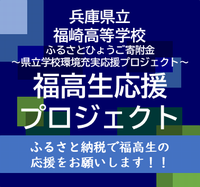カテゴリ:2022年度
令和4年度 第20回講座
講座「チーム医療」の20回目が、11月29日の6限目と7限目に実施されました。
20回目の講座は、医療法人社団アキタケ診療所の秋武宏規院長先生にお越しいただき、講義をしていただきました。
今回のテーマは、「チーム医療について~地域医療連携も含めて~」。
本校の校医を務めてくださっている秋武先生に、医療連携や医療従事者に求められる資質についてお話をしていただきました。
講義の前半は医療連携について、神崎郡の状況も含めてお話をしていただきました。
神崎郡には総合病院が1つしかなく、個人クリニックが重要な役割を担っています。そして、病院の枠を超えた医療連携が行われていることを教えていただきました。
また、病院内でも様々な病気に対して医療連携をこなっていることを学びました。
講義の後半は、医療従事者に求められる資質についてお話をしていただきました。
医療従事者はプロフェッショナルとして、様々な能力が求められます。その中でも秋武先生は、「コミュニケーション能力」と「探究心」を重視していると教えていただきました。
そして最後に、この2つの能力を身につけるためにも、充実した学校生活を送って欲しいというメッセージを頂きました。
今回で講師の先生にお越しいただく授業は終了しました。次回からは授業の振り返りと、プレゼンテーションを行います。


令和4年度 第19回講座
講座「チーム医療」の第19回講座が、11月22日の6限目と7限目に実施されました。
6時間目の講座は、福崎町保健センターの保健師、本城里奈さんと藤田真由香さんにお越しいただきました。
講義のテーマは、「保健師とチーム医療」。
7時間目の講座は、本校、養護教諭の山﨑紅美先生に講義をしていただきました。
講義のテーマは、「養護教諭とは」。
【6限目】
保健師の仕事は「保健指導をする仕事」です。例えば健康診断を受けた後で、「毎日の暮らしで不便ことはないか」「身体のことで心配はあるか」といった相談にのったり、生活指導をしたりするのが仕事です。
保健所で働く以外でも、産業保健師、学校保健師、病院保健師等、様々な仕事があることを学びました。また、地域包括センターなどで介護予防支援などにも従事されていることを教えていただきました。
【7限目】
養護教諭の仕事は、保健管理、保健教育、健康相談及び保健指導(個別)、保健室経営、保健組織活動など多岐にわたります。
難しいお話になるかと思っていましたが、自己紹介から始まり、どうして養護教諭を目指すようになったのか、養護教諭コースの授業内容、教育実習、養護教諭になるためには、など基本的なことをわかりやすく楽しく教えていただきました。
次回は、11月29日にアキタケ診療所の秋武医師にお越しいただき、講義をしていただきます。



令和4年度 第18回講座
講座「チーム医療」の18回目が、11月15日の6限目と7限目に実施されました。
18回目の講座は、姫路獨協大学看護学部の石田寿子先生にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「小児看護の仕事とチーム医療における役割」。
講義の前半は、小児看護の内容や乳幼児期の成長発達についてお話をしていただきました。
小児看護と聞くと幼児のみをイメージしがちですが、小児看護の対象は誕生から成人への移行期までであることを学びました。そして、小児看護で重要な誕生から大人への成長・発達の過程について実習を交えながら教えていただきました。
実習では、人形を用いて新生児と乳児の身長や体重を測定したり、新生児の脈拍を測ったりと貴重な体験をすることができました。
講義の後半は、小児看護のトータルケアについてお話をしていただきました。
トータルケアはチーム医療とも似ていますが、患者の子どもを支えるだけではなく、子どもの成長と発達を支えるためにも家族の支援を行うことが重要であると学びました。
次回は、11月22日に「保健師」と「養護教諭」について学びます。





令和4年度 第17回講座
講座「チーム医療」の17回目が、11月8日の6限目と7限目に実施されました。
17回目の講座は、公立神崎総合病院看護部長の大﨑明美さんにお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「公立神崎総合病院におけるチーム医療」。
講義の前半は、看護師の仕事について実習を交えながらお話をしていただきました。
「脈」のとり方、血圧の測り方、パルスオキシメーターを使った酸素濃度の測り方を教えていただき実習をしました。また、指輪っかテストで足の筋肉量を測ったり、椅子から立ち上がるテストで筋肉年齢をチェックする方法など、楽しみながら看護師の仕事について学びました。
講義の後半は、公立神崎総合病院におけるチーム医療のお話を中心に講義をしていただきました。
神崎総合病院は都市部の大病院と連携をして、チームを作り地域医療を担っています。そして、院内には「感染対策チーム」、「認知症ケアチーム」、「褥瘡管理チーム」、「緩和ケアチーム」などのチームがあり、それぞれのチームの役割を教えていただきました。
そして、最後には医療職を目指している生徒に向けて3つの大切なポイントを教えていただきました。実際に現場で活躍されている方から、直接お話を伺う貴重な機会となりました。
次回は、11月15日に「小児看護」について学びます。




令和4年度 第16回講座
講座「チーム医療」の16回目が、11月1日の6限目と7限目に実施されました。
16回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部言語聴覚療法学科の為季周平准教授にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「言語聴覚士の仕事とチーム医療における役割」。
講義の前半は、言語聴覚士の仕事についてお話をしていただきました。
言語聴覚士の担当する仕事は、言語発達障害や聴覚障害、摂食嚥下障害など多岐にわたります。活躍する場も病院から学校までと広がっていることを知りました。
また、言語障害と深い関係のある「脳」の働きについて教えていただきました。「脳」の役割と病気が発生したときの症状について学びました。
講義の後半は、「脳」と「食」についてお話をしていただきました。
講義前半の内容を踏まえ、実習を交えながら楽しく「脳」の活動について理解を深めることができました。
また、「食」の目的と重要性を学び、誤嚥の動画を見ながら誤嚥性肺炎について教えていただきました。私たちは、食べることで生命機能を維持していると改めて実感しました。
次回は、11月8日に公立神崎総合病院の方にお越しいただき、講義をしていただきます。


令和4年度 第15回講座
講座「チーム医療」の15回目が、10月25日の6限目と7限目に実施されました。
15回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科の仁田静香先生にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは「チーム医療と作業療法」。
講義の前半は、作業療法の仕事についてお話をしていただきました。
作業療法士はリハビリテーションの専門家であり、支援する『作業』には様々な活動があることを教えていただきました。作業療法では作業遂行が目的でもあり、「基本的能力」・「応用的能力」・「社会的適応能力」を維持・改善し、その人らしい生活の獲得が目標であることを学びました。
講義の後半は、発達障害領域の作業療法がご専門の先生から、子どもに関わる作業療法についてお話をしていただきました。
子どもに関わる作業療法士が活躍する場所について教えていただき、療育センターにおける作業療法士の役割を知りました。また、幼少期は「遊び」を通して療育を提供することが必要であり、実習も交えていただきながら楽しく作業療法について学ぶことができました。
次回は、11月1日に「言語聴覚療法」について学びます。

令和4年度 第14回講座
講座「チーム医療」の14回目が、10月11日の6限目と7限目に実施されました。
14回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部理学療法学科の山本洋之教授にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「理学療法とは」。
講義の前半は、理学療法の意味について実習を交えながらお話していただきました。
理学療法とはPhysical Therapy(PT)であり、その意味について説明をしていただきました。そして、パルスオキシメーターを使った実習では、息を止めることで動脈血酸素飽和度と脈拍数から人体の血液循環に要する時間を推測しました。
講義の後半は、理学療法・作業療法・言語聴覚療法の違いをお話していただきました。
イラストを確認しながら、3つの違いを説明していただきました。また、これらの学問をすべて学ぶことができるのが姫路獨協大学であると説明を受けました。
その後の超音波を使った実習では、豆腐に超音波を当てることで摩擦熱から豆腐が高温になることを体験しました。
次回は、10月25日に「作業療法」について学びます。


令和4年度 第13回講座
講座「チーム医療」の13回目が、10月4日の6限目と7限目に実施されました。
台風の影響で9月20日に予定されていた「小児看護」の講座は11月に延期され、今回は姫路獨協大学薬学部の増田智先教授にお越しいただき、「薬剤師」について講義をしていただきました。
講義のテーマは、「薬剤師の仕事、チーム医療における役割」。
講義の前半は、「クスリ」について実習を交えながらお話をしていただきました。
まず、実習では「薬」の飲み比べをおこない味の違いについて考えました。そして、「薬」には副作用が必ずあり、効果の強い「薬」は「毒」であることを知りました。「薬」は、副作用を抑えながら効果を最大限に発揮するように調整されているため、用法用量を適切に管理することが重要であることを教えていただきました。
講義の後半は、薬剤師の仕事についてお話をしていただきました。
医師と薬剤師の役割分担(医薬分業)の歴史や「かかりつけ」薬剤師の重要性について教えていただきました。薬剤師の活躍の場は様々ですが、やはり洞察力・コミュニケーション能力が大切であり、「薬」の専門家として患者さんと接していくことが重要であると学びました。
次回は、10月11日に「理学療法士」について学びます。


令和4年度 第12回講座
講座「チーム医療」の12回目が、9月13日の6限目と7限目に実施されました。
12回目の講座は、姫路獨協大学看護学部看護学科の瀧本茂子教授にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは「看護師の仕事とチーム医療における役割」。
講義の前半は、看護師の仕事についてお話をしていただきました。
高校卒業後、どのようにして看護師・保健師・助産師になるのかを説明していただきました。また、看護師になったあとのキャリアである専門看護師や認定看護師制度についても教えていただきました。
さらに、看護師や保健師が病院以外の場所でどのように活躍しているのかも詳しくお話していただきました。
講義の後半は、「タクティールケア」の実習を行いました。
最初に、老年看護学がご専門の瀧本先生から「タクティールケア」がどのようなもので、どのような効果があるのかを説明していただきました。その後、2人1組になり「タクティールケア」実習に取り組みました。
実習を受けた生徒は、「癒やされた」「気持ちよかった」「眠くなった」など心地よさと安心感を感じたという感想を述べていました。
次回は、9月20日に「小児看護」について学びます。


令和4年度 第11回講座
講座「チーム医療」の11回目が、9月6日の6限目と7限目に実施されました。
11回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部臨床工学科の杉村宗典助教にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「臨床工学技士とチーム医療との関わり」。
講義の前半は、臨床工学技士の役割を中心に説明をしていただきました。
私たちは普段、病院で臨床工学技士に出会うことはありません。その理由は、臨床工学技士が「生命維持管理装置を扱う仕事」をしているからであり、そのことをとても分かりやすく教えていただきました。
コロナ禍でECMO(エクモ)の操作など、これまで以上に臨床工学技士の仕事が注目されており、最新の医療機器を扱うことができる重要な役割を担っていることを学びました。
講義の後半は、不整脈治療を中心とした臨床工学技士の仕事について説明をしていただきました。
心室細動やアブレーションカテーテルなど、お話と動画で詳しく学ぶことができました。また、病院ではどのようなチームが存在し、チーム医療が重要である理由を先生の想いも込めてお話ししていただきました。
次回は、9月13日に「看護師」について学びます。