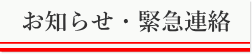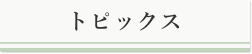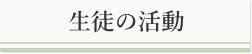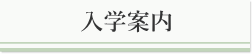生徒の活動
附属中学校に鬼が来た!
本日2月3日は節分。なんと附属中学校に鬼が出ました!
昼休みに8人の鬼が金棒片手に「ソーシャルディスタンスを守らぬ生徒はいねーか?」と怖い顔!能面をつけている鬼もおり、迫力満点!
趣旨は、生徒会執行部による季節行事プラス感染症対策の啓発でした。
また、鬼の背中には、それぞれ違う「ひらがなの札」がついており、8人の組み合わせで質問になる演出もありました。
季節感満載のイベントに、サプライズを受けた生徒らは大喜びでした。
全校集会を実施しました!
1月24日(月)の1時間目に全校集会を行いました。
まず、先週発足した第14代生徒会執行部から、スローガン「一期一笑」についての説明がありました。(出会いも笑顔も大切にした学校生活にしよう)
その後、各専門委員長から12月の目標に対する反省と1・2月の目標、各クラスの取組についての報告がありました。最初は少し緊張した面持ちでしたが、どの専門委員長も初めての発表とは思えないほど堂々とした様子でした。また、先週の金曜日に行われた新春百人一首大会の表彰式も行われ、激戦を制した3名の生徒に表彰状などが贈られ、全校生徒から大きな拍手が送られました。
2022 新春百人一首大会 結果
第1位 末永 明花莉
第2位 竹中 友唯
第3位 安川 弥来


生徒総会を実施しました!
1月17日(月)に第2回生徒総会が実施されました。
まず、「百花繚乱」のスローガンの下、1年間、附属中学校の先頭に立って活躍してくれた第13代生徒会執行部から年間目標や活動報告、そこから見えた成果と課題などを各専門委員会の委員長が報告してくれました。その後、第13代生徒会執行部1人1人が1年間の生徒会活動を振り返り、「生徒会で苦労することや失敗することもあったが、仲間と協力して頑張ることができたこと」、「生徒会を通じて、自分自身が成長できたこと」などを伝えてくれました。最後に、全校生徒から第13代生徒会執行部にお疲れさまの気持ちを込めた温かい拍手が送られました。
続いて、第14代生徒会執行部の認証式が行われ、8人の新生徒会役員に小倉校長から任命書が渡されました。先輩方がこれまで築いてきた伝統や思いを引き継ぎ、附属中学校をより一層盛り上げていってくれることを期待しています。
第14代生徒会役員
生徒会長 定森 佑夏
生徒会副会長 片山 葵子 原田 雅大
生活委員長 冨賀見 智晴
学習委員長 大林 想汰
美化委員長 元西 一惺
図書委員長 角田 美咲
保健安全委員長 関 彩花


2022 新春百人一首大会を開催!
1月21日(金)に2022 新春百人一首大会決勝が開催されました。
この大会は、百人一首を通して日本の伝統文化にふれながら、全校の親睦を深めるために本校では毎年開催されています。
今年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、100枚の札が青、桃色、黄色、緑、橙の五色に色分けされた五色百人一首を用いて、1対1の形式で試合が行われました。
冬休み前から、生徒たちはこの大会に向けて、一つでも多くの歌を覚えようとノートに書いたり、休み時間に級友と対戦したりしている姿が見受けられました。
各クラスで行われた予選会を見事突破した30名の生徒たちが名人・クイーンの座を目指し、本日放課後の決勝戦でしのぎを削りました。
「むらさめの・・・」などの一字決まりの歌や「ちはやぶる・・・」などの有名な歌が詠まれると、多くの生徒たちが上の句の途中で札を取るなど、白熱した戦いが繰り広げられ、非常にレベルの高い大会となりました。




2021年度プロジェクト学習発表会(3年生口頭発表)
1月20日(木)の午後に、「プロジェクト学習発表会」を実施しました。
本校プロジェクト学習では、兵庫県立大学や県立人と自然の博物館、西はりま天文台などから講師を招聘して、自然科学や社会科学に関する内容で10班に分かれ、生徒が主体となり研究を進めています。
発表会では、3年生が2年間の研究の集大成として、口頭発表を実施しました。昨年のポスターセッションの反省を生かした磨きをかけたプレゼンを聞かせてくれました。
質疑応答の時間では、専門家の講師の先生や生徒たちから鋭い質問が飛び交う場面があり、各班とも戸惑うことなく、班員全員で話し合って、答えていました。そんな3年生の堂々とした姿に、1・2年生が尊敬の眼差しを向けていました。
プロジェクト学習という探究活動を通して、科学的に物事を考え、表現する力を磨くことができました。
2年間ご指導いただきました講師の先生方、本当にありがとうございました。