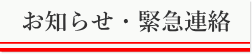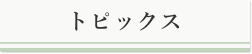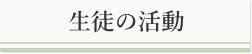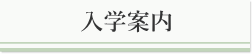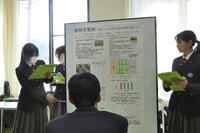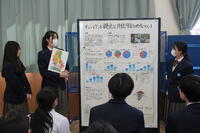生徒の活動
2年生 プロジェクト学習ポスターセッション
2月17日(火)12時40分より、2年生が中間発表として、今年度の探究成果を発表する「プロジェクト学習ポスターセッション」を実施しました。全10班が1年間の探究活動の結果をポスターを用いて発表しました。
各班がそれぞれ工夫した発表をすることで、とても興味を惹く内容となりました。また、ポスターセッションならではの近い距離感でおこなわれ、発表者と聴き手との対話を大切にしました。その結果、積極的に質問する人が多く、2年生にとっては今後の研究をさらに深める有意義な機会となりました。
来年度のプロジェクト学習へとつながるすばらしいポスターセッションとなりました。
【発表内容】
1 学校周辺の森林の種組成を調べる(森林班)
2 今と昔の貝殻を調べる(貝のセカイ班)
3 インバウンド観光と持続可能な地域づくり(インバウンド班)
4 トラップを用いて異なる餌の昆虫相を調べる(インセクト班)
5 学校のパブリックスペースをデザインする(パブスぺ班)
6 天体スペクトルの取得~銀河の謎を解き明かせ!~(天文班)
7 プラズマの振る舞いを調べる(プラズマ班)
8 植えマス内や芝生地の植物の環境を調べる(植物生態班)
9 見て、動かせ!!視線スーパープロジェクト✨(テクテク班)
10 大きな結晶を育てよう(結晶班)
3年生 プロジェクト学習発表会
1月20日(火)に3年生による「プロジェクト学習発表会」が行われました。
2年間研究した成果をスライドにまとめ発表しました。どの班も研究した内容を分かりやすくまとめ、興味深い発表でした。1、2年生もしっかりと先輩方の発表を聞き、質疑応答の時間には積極的に質問していました。
2年間ご指導いただきました講師の先生方、本当にありがとうございました。
【発表内容】
1 スポーツと音楽の関係(スポーツ班)
2 役に立つ微生物をとろう(微生物班)
3 神社と里山の樹木(寺社研究班)
4 珪藻を用いた河川の環境の計測(イケイケ珪藻班)
5 ヒメダカとクロメダカは交配するのか?(GenEco班)
6 株式投資を通して防災に貢献(KK班)
7 オカダンゴムシの迷路実験 / 餌と成長(ダンゴムシ班)
8 身近な緑の機能と効果(みどりの窓口班)
9 写真には映らない?暗黒星雲をみつけよう(天文班)
10 カルス培養(カルス班)
新春百人一首大会
1月16日(金)に新春百人一首大会が行われました。
各クラス7チームに分かれ、チーム対抗戦を2回戦行い、クラス・チーム・個人の合計取り札を競いました。また、個人の合計枚数が多い10名により決勝戦をおこないました。
国語や放課後の時間を使い練習した力をそれぞれが発揮し、各コートで激しい戦いが繰り広げられました。決勝戦では勝ち残った10名が全校生に見守られる中で優勝をめざし全力を尽くしました。
この百人一首大会を通して、クラス・全校の絆がより一層深まりました。
全校集会
12月24日(水)に2025年を締めくくる全校集会を行いました。
足立校長先生からは12月10日は「人権デー」であることを聞き、「学校でも人権の意識を持ちましょう」とお話がありました。そのあと、各種表彰伝達があり沢山の表彰状を授与されました。最後に、音楽部によるクリスマスコンサートがありました。
2025年も本校の教育活動にご協力いただきありがとうございました。みなさまよいお年をお迎えください。
冬レク2025
12月8日(月)に生徒会執行部の運営による冬レクを行いました。
最初の種目は、クラス対抗の「ドッジボール」でした。それぞれのクラスの団結力が試される競技でした。続いての種目は、「だるまさんがころんだ」でした。鬼と同じポーズをとらないとアウトとなる特殊ルールのもと、どれだけ速く鬼にタッチできるかを競いました。最後の種目はArt Festival でも盛り上がった「附属リーグ」でした。お題に該当する人数を予想するもので、附属中の生徒のことをどれだけ観察しているかが鍵となりました。学年を越えた交流ができ、より一層附属中学校が仲良くなれた時間となりました。生徒会の皆さん、ありがとうございました。