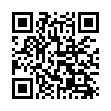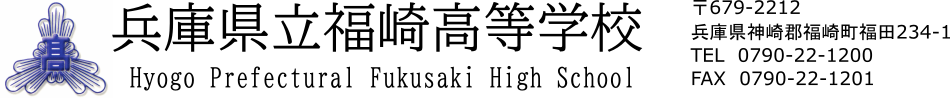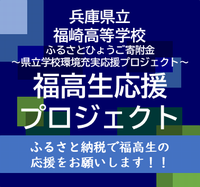2021年5月の記事一覧
令和3年度 第4回講座
講座「チーム医療」の第4回目が、5月25日の6限目と7限目に実施されました。
第4回目の講座は、神戸常盤大学保健科学部医療検査学科講師の田村周二先生にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「病院における臨床検査技師とチーム医療」。
神戸市の病院で長年勤務された経験を持つ先生から、臨床検査技師の仕事や現場での他職種とのチーム連携について教えていただきました。
講義前半は「COVID-19」を主な事例として扱い、臨床検査技師がチーム医療でどのように活躍をしているのかを学びました。「COVID-19」の特徴や医療崩壊が起こる仕組み、病院感染症チームがどのように活躍しているのかを具体的な例をあげて説明をしてくださいました。
講義後半は実際の検査動画を見ながら、どのような検査で何が分かるのかを詳しく教えていただきました。また、生徒全員からの質問に丁寧に答えてくださり、医療現場での心構えや必要な力を知ることができました。
次回は、6月1日に「診療放射線技師とチーム医療」について学びます。
令和3年度 第3回講座
講座「チーム医療」の第3回目が、5月11日の6限目と7限目に実施されました。
第3回目の講座は、神戸常盤大学保健科学部看護学科講師の西村充弘先生にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「精神科におけるチーム医療」。
精神看護学を指導されており依存症にも詳しい先生から、精神科医療や精神科におけるチーム医療について授業をしていただきました。
授業前半は、精神科医療についてお話をしていただきました。現在の日本では精神疾患を抱えて入院をしている患者の割合が最も多く、精神看護の場が多岐にわたっていることを教えていただきました。中でも双極性障害が増加しており、10代後半以降から発症してピークは20代後半であるという説明を受けました。私たちに最も身近な病気であるということを学びました。
授業後半では、依存やチーム医療についてお話をしていただきました。「依存」とは、自らコントロールができなくなってしまう状況であり、現在はゲーム依存の割合が増えてきていることを教えていただきました。精神科医療に携わる医療職も多種類あり、包括的な支援チームを作ることで治療を進めている現状を説明していただきました。
次回は、5月25日に「臨床検査技師とチーム医療」について学びます。
令和3年度 第2回講座
講座「チーム医療」の第2回目が、4月27日の6限目と7限目に実施されました。
第2回目の講座は、神戸常盤大学保健科学部看護学科の島内敦子准教授にお越しいただき、講義をしていただきました。
講義のテーマは、「周産期におけるチーム医療」。
母性看護学がご専門の島内先生から、妊娠・分娩・産褥(じょく)期におけるチーム医療とウィメンズヘルスナーシングについて教えていただきました。
講義の前半は、助産師の役割と妊娠・分娩・産褥期についてお話をしていただきました。
助産師に認められている権利や役割について教えていただき、生徒は助産師と看護師の違いを理解することができました。また、妊娠期・分娩期・産褥期の違いや定義、そして各期に求められることや大切なことを教えていただきました。
講義の後半は、周産期医療におけるチーム医療について映像を観ながら学びました。元気に赤ちゃんが生まれてくるまでには、多くの医療従事者がチームを作り関わっていることを教えていただきました。また、不妊治療とチーム医療についても教えていただきまいた。
次回は、5月11日に「精神科におけるチーム医療」について学びます。
 |
 |
 |