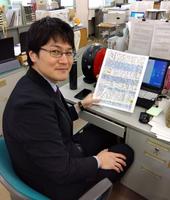芦高リレーインタビュー vol.4
学校運営の中心となってお仕事をされている管理職・各課長の先生方にお話を伺っていくシリーズです。
芦高の「今」について語っていただきます!
★今回は芦高の総務課長・広報担当・戸屋先生にインタビューを行います。
戸屋先生の芦高生の印象を教えていただけますか?
戸屋総務課長・広報担当
芦高生はとにかくエネルギッシュで、それぞれのスタイルで高校生活に前向きに取り組めている生徒が多いですね!行事もそうですし部活動や自治会活動などとにかく動いている生徒が多い印象です。
校訓の「自治・自由・創造」の通り、とにかく自分で何かやってやろうという「勢い」を感じています!
★芦高生はいろいろなことに挑戦している人が多いですよね!
では、広報の仕事を教えていただけますか?
広報という仕事は芦高の様々な取り組みを「見える化」することです。たとえば、体育祭や記念祭などの学校行事では芦高生一人一人が本当に頑張っていて、それを自治会が中心となってまとめている姿は本当に素晴らしいものです。学校行事は誰かに見せるために頑張っているものではないのですが、そうした力いっぱい頑張っている芦高生の姿を私は多くの人に知ってもらいたいのです。もちろん、普段の授業でも、おもしろい授業をしようと取り組んでおられる先生方、そしてその授業に必死に食らいついている芦高生も本当にいいものです。
そして放課後の芦高は本当に楽しい!運動部が元気なのはもちろんなのですが、芦高は文化部が本当に元気なんです。運動部は外からも見えやすいですし、実際、とても活発に活動しています。それに対して文化部は校内で活動しているので皆さんの目に触れる機会が少ないのですが、とても盛んなんです。
HPを見てもらえばわかるのですが、放課後の教室で文化部が毎日、一生懸命に部活動にいそしんでいます。そうした姿を少しでも知ってほしくてHPの部活動ページに各部活動のメンバー紹介と月例報告を作りました!とても楽しい芦高生の姿がそこにはあるのでぜひご覧ください(笑)
★芦高のリアルな姿、とても面白そうですね。そうした場を作ること、それが広報の仕事なのですね!そうした活動を行っていく中で現在、課題としているものはどんなことなのでしょうか?
今、コロナ禍を経て教育界は大きな転換期を迎えています。そうした時代の中で、芦高はジチカツによるルールメイキングの試み、文系・理系の垣根を超えた新しい科目の設定、既存の科目も2,3年生共修化によって新たな学びを創造するなど大きな変化を遂げようとしています。また、始業前、終業後のスマホ使用の解禁、体操服を廃止し個人ビブスとする、第三の通学服の導入など生活面でも、どんどんチャレンジを続けています。そうした転換期に芦高生、先生方はしっかり向き合い、新しいものを作り出そうとしています。そのような走り続ける芦高を余すことなく皆さんに伝えないといけないのですが、まだまだ伝えきれていません。コンテンツはたくさんあるのに、それを十分に伝えきれていないことが課題ですね!
★芦高ではいろいろな試みが行われているのですね。それでは今のお仕事をしていてやりがいを感じるのはどのような時なのでしょうか?
今の時代にふさわしい、より良い芦高になろうと生徒と教員が一体となってとみんな頑張っています。そのプロセスをライブで見届けることができてうれしいですし、こんなに輝いている姿を皆さんにHPや学校公開事業を通じて皆さんにお伝え出来た時に達成感を感じます。これからも、今の芦高の姿をどんどん伝えていきますね!
★ありがとうございます。HPの記事など楽しみにしています!
最後に戸屋先生のことについて伺っていいですか?バスケットボール部を指導するようになったきっかけを教えていただけませんか?
私は中学校からバスケを始めて現在にいたるまで、ずっとバスケ漬けの30数年間でした。バスケを通して多くの学びと喜びを得ることができましたし、今でもプレーすることが大好きです。そうしたバスケ仲間を増やしていくために、高校の教員になりました。芦高バスケ部は本気でバスケに取り組んでいます。ぜひ、本気でバスケをしたい人は芦高に来てください!本気度では絶対に満足してもらえる部活動だと思います!
★バスケ愛、熱いですね!
今日はありがとうございました。これからもよろしくお願いします!
「私のお気に入り」
芦高の誇る自治会・部活動幹事(部活動の対外的な取りまとめを行っている部活動の頭脳的存在です!) 軍団です。
みんなと一緒に芦高を盛り上げていきます!