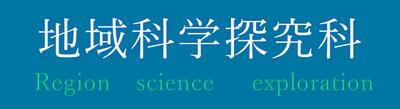応援歌「熱風」 兵庫県立尼崎高等学校
1998.12.23 神戸新聞掲載記事
歌なく沈黙の甲子園
自由の風が県立尼崎高校の新しい船出を後押ししていた。戦後の日本映画を代表する名作「青い山脈」で全国民が実感した”民主主義”こそ新生県尼の誇りだった。
「僕自身は旧制中学時代の校歌はきらいではなかった。しかし、二番の最後などは戦後には通用しないものだったから、変わったのは仕方がなかったんでしょう」
そう語るのは、現校歌の作詞を担当した中松正昭さん。尼中を卒業し、広島高等師範に進んだ中松さんは、旧制校歌には親しみがあった。高師を出て、国語教師として母校の教壇に立つことになった中松さんは、新しい校歌作りに際して、旧制校歌の作詞者だった福武周雄さんに詞句の一部改訂を依頼した。尼中の教員だった福武さんは、戦前の全国中等学校野球大会歌の作詞者でもあった。
福武さんからはすぐに返事があった。「新しい時代なんだから、新しい校歌をあなたたちでお作りなさい」。公募になり、結局選ばれたのは中松さんの詞。あわただしく戦後の時間が流れ、昭和二十六年も夏を迎えていた。
話を二十五年春にもどそう。舞台は甲子園球場。
センバツに初出場した野球部は一回戦で古豪熊本工と対戦。互いにホームランを応酬する激しい打ち合いの末、県尼は15対9で涙をのんだ。
だが、グラウンドの敗戦よりも、一塁側スタンドを埋めた応援団にとって悔しかったのは、試合中高らかに歌う熊工スタンドに対し、校歌も応援歌もまだなかった県尼スタンドはひたすら沈黙せざるを得なかったことだった。
「これじゃあいかん、ということで急きょ、新制の校歌作りヘ動きだした」と、中松さんは語る。 そして、二十六年十月二十七日、文化祭で校歌発表式が行わた。歌ったのは関西学院グリークラブ。作曲を担当した音楽教諭・田口寛さんの尽力で関学のグリーがやってきた。
バンカラ脈々と応援歌に
やっと校歌ができた。これでいつでも甲子園で-と関係者がほっとしたのもつかの間、意外なところから不満の声があがった。声の主はラグビー部員。
校歌発表の直後、ラグビー部が、正月に西宮球技場で開催される全国大会への切符を手にした。「あんな、やさしい校歌では、荒々しいラグビーの応援には軟弱だ」。ラグビー部員やOBからそんな声があがった。
ラガーメンは強硬で説得にも応じる気配がない。やむなく中松さんたちが作ったのが、校歌以上に記憶に残っていると卒業生が口をそろえる応援歌「熱風」である。
「熱風砂を捲(ま)くときも 峻(しゅん)烈の風吹くときも」と始まる「熱風」は、その後、幾たびとなく各種競技の全国大会でこだました。
初代生徒会長は女性
「熱風」誕生が伝統校にままあるバンカラのエピソードとするなら、初代生徒会長はまさに戦後モダンの象徴だったと言えるかもしれない。
昭和二十四年、生徒会を組織することになり、名誉ある初代会長に選出されたのは、なんと女生徒であったという歴史を知る卒業生は少ない。その人、大附(旧姓宮本)多美子さんはわずか二十八人しかいなかった女生徒の一人だった。
「なにしろトイレは男子用しかなくて、女子は簡易トイレだけ。それに裁縫や茶道用の和室もなかった。男女共学なのに」。大附さんは当時を楽しそうに振り返る。大附さんたちがしとやかな中にもぴしりと設備改善の要求を出したのは言うまでもない。「あのころは、進駐軍が時々学校教育もチェックしていたでしょう。県尼に来て、女性の生徒会長と知って、”オー! ワンダフル”でしたよ」
県尼は戦後を積極的に受け入れた。校歌を作詞した中松さんは、三番の「負ひゆく道をあひともに」というフレーズだという。戦後復興めざして手を取り合って立ち上がろう。男女共学という意味だけでなく、工都で懸命に働く人々とその子弟、日本の戦後を支えた人たちへの思いをこめたフレーズであった。
昭和二十四年から四十五年まで県尼に勤務した中松さんの脳裏にはいまも、コンビナー卜の煙突が吐き出すばい煙の中を通学してきた生徒らの姿が焼きついている。その中でも、夕方、定時制に通学してきた生徒らのひたむきな姿の印象は強い。
県尼の定時制は昭和四十三年に尼崎南高として分離・独立した。現在、神戸で工場を経営する三浦清三さんは四十二年の卒業。三浦さんらにとっての校歌はあくまで県尼の校歌である。県尼OBとして同窓会でも県尼校歌を歌いたい、という三浦さんらの希望はかない、二年に一度開かれている定時制同窓会では毎回、輪になって校歌を歌う光景が再現される。中松さんには、その歌声が昼間の卒業生の同窓会より高らかに聞こえる。