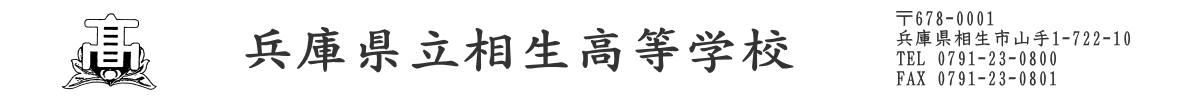| Aioi High School,Passport to the World ~相生高校から世界へ~ |
カテゴリ:校外学習
数学・理科甲子園2024
10月26日(土)に、数学・理科甲子園2024が甲南大学で開催されました。
相生高校は2年自然科学コースの精鋭6名で挑みました。予選では、個人戦で3名、団体戦で3名1チームが力を合わせ、戦いました。残念ながら全61チームのうち上位15チームが進出する本選には進めませんでしたが、団体戦やチャレンジマッチ(敗者戦)では、皆で知恵を絞りながら楽しく数学や理科の問題に取り組みました。
他校の生徒と競い合う中で多くの刺激を受け、実りの多い一日となりました。この貴重な経験を今後の学校生活に役立ててくれるものと期待します。
令和5年度相生歴史巡検 Part2(那波八幡神社~厳島神社)
いよいよ地頭海老名氏関連の名所へ足を運びます。まず訪れたのは、那波八幡神社です。地頭海老名氏は鎌倉幕府の御家人で、もとは相模(現在の神奈川県)に住まう武士でした。承久の乱によって鎌倉幕府の影響力が西国にまで及ぶと、海老名氏は地頭として、現在の相生に広がっていた荘園・矢野荘へ赴任することとなりました。その際、源氏の守護神を祀る鶴岡八幡宮を勧請して那波八幡神社を建立したのです。それからは那波八幡神社が地域のコミュニティの中心として機能し続けました。造船業が盛んとなった20世紀には、タンカーの絵が描かれた絵馬が奉納されたり、戦争の際に忠魂碑が敷地内に建立されたりと、「浦分」(矢野荘の海側の一画、海老名氏が支配した地域)の歴史を現代まで定点観測してきた神社なのです。絵馬や忠魂碑を見ることで、相生がたどってきた歴史を感じることができました。
|
タンカーが描かれた絵馬 |
忠魂碑 |
那波八幡神社 |
続いて、地頭海老名氏の居城とされる大嶋城跡へ向かいます。もともと大嶋城は那波港に浮かぶ島でした。山頂に登るとほのかに潮の香りを感じました。
大嶋城を下って少し歩くと、聖徳太子の家来とされる秦河勝にまつわる伝説のある岬に着きます。現在、秦河勝を祀る大避神社があります。
最後に播磨造船所の社員たちがお祀りした弁天さんへ向かいます。旭の弁天社、別名を厳島神社と言います。厳島神社の鳥居傍の左右にある玉垣には、社宅街やまちづくりに尽力した大本組の初代社長である大本百松の名が刻まれています。かつて造船の街としてにぎわい、社宅街が広がっていた歴史を今に伝える祠なのです。
松本先生の、相生歴史よもやま話を堪能し、ふるさと相生を振り返る素晴らしい一日になりました。
|
大嶋城跡の山頂にある住吉社 |
秦河勝を祀る大避神社 |
播磨造船所の社員ゆかりの厳島神社 |
令和5年度相生歴史巡検 Part1(相生駅~得乗寺「しだれ栗」)
9月24日(日)、秋晴れの快晴の中、松本恵司先生を講師に迎え、相生歴史巡検を行いました。今年度の巡検は、2年生4名・1年生1名の5名が参加しました。
今回のテーマは「【中世】地頭海老名氏による鎌倉文化の移植と【近代】鈴木商店の進出による相生の発展」とし、JR相生駅の南側の地域を中心に、松本先生の解説を交えて散策しました。
相生高校を出発して最初に、JR相生駅の南口を出たすぐのところにある狐塚古墳跡へ向かいました。狐塚古墳は古墳時代中期の横穴式石室をもつ古墳で、発掘調査の結果、遺物も確認されているそうですが、今や古墳は解体され建物が建っています。わずかに古墳をしのぶモニュメントがたたずんでいます。松本先生いわく「古墳は海側から見える目印となるものだから、今よりも海岸線が駅側に近かったことが予想される」とのことで、相生の地形の歴史的変遷についても思いをはせることができました。
次に得乗寺へ向かいました。得乗寺には、平安歌人として名高い和泉式部ゆかりの栗の木があります。和泉式部が相生近辺を訪れた際、急な雨に遭い、栗の木の下で雨宿りをしたのですが、その栗の木が突如、和泉式部を守るかのように枝をしだれさせたというのです。こうした伝承のある「しだれ栗」の木が得乗寺に保存されています。今回、住職さんのご厚意により拝観する機会を得ました。「しだれ栗」の木は近畿にはここ一本しかないとのことで、貴重なものを見ることができた感慨に生徒も教員も皆ひたっていました。
|
狐塚古墳のモニュメント |
しだれ栗のある得乗寺へ |
しだれ栗 |
歴史巡検 英語で紹介
先日行われました相生歴史巡検で訪れた貴重な相生の歴史遺産を、広く海外の方にまで知っていただこうと、英語版での紹介文を作成しました。今回紹介しますのは、江戸時代の役所であった相生若狭野陣屋札座という建物です。この建物は、旗本と呼ばれる階級の武士の役所で、現存している珍しいものです。近年その歴史的価値から保存活動が始まっています。英文・日本語訳は相生歴史巡検に参加した2年の出口大和君によるものです。なお、ALTのリサ先生には添削作業にご協力いただきました。
The Aioi Wakasano Jin’ya Satsuza
The Aioi Wakasano Jin’ya Satsuza is a piece of architecture located in the city of Aioi in the Hyogo Prefecture. A “Jinya” was a public office building for Hatamoto (direct retainers of the syogun) and Daimyō (Japanese feudal lords) that had no castles of their own. During the Edo period, the “satsuza” was the public office which issued paper money called hansatsu to specific han (the domain of a feudal lords). The Wakasano Satsuza also issued paper money used in its own domain as well. In Japan, this building remains standing as a satsuza site to this day. It is also known as the birthplace of Ikuo Ōyama, a political scientist who played an active role in political campaigns during the Taishō Period. In recent years, a campaign to preserve the architecture has been launched because of its historical significance.
訳)相生若狭野陣屋札座は、兵庫県相生市にある建物です。「陣屋」とは、自身の城を持たない旗本(将軍直参の家臣)や大名(日本の封建領主)のための役所です。江戸時代、「札座」は特定の藩(封建領主の領土)で流通する藩札と呼ばれる紙幣を発行する公的機関でした。若狭野の札座も領内で流通する藩札の発行を行っていました。日本では、この建物が今日まで札座の遺構として現存しています。また、大正時代に政治活動で活躍した大山郁夫の生地としても知られています。近年、その歴史的重要性から建物を保存しようとする取組が始まっています。
 |
| The Aioi Wakasano Jin’ya Satsuza(相生若狭野陣屋札座) |
相生歴史巡検 Part3(小河)
|
築池記念碑のすぐ横に、三昧(さんまい)跡が残っています。三昧とは葬儀場のことで、昔はどの村でも葬儀を行っていました。手前の石の上にお供えものを置き、後ろの石には棺を置き、葬儀を行っていたそうです。 |
 |
小河川に沿って約1kmほど遡ると、左手に宇麻志(うまし)神社があります。江戸時代までは馬子大明神といい、蘇我馬子を祀っていましたが、明治維新以後、蘇我氏が天皇を殺めていたため逆臣を祀るわけにはいかず、「うまし」と呼び名が同じである宇麻志阿斯詞備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)を招聘し祀るようになったそうです。
伝説によると、蘇我馬子が相生に来て亡くなり、その従者であった将監光庵が、馬子のために菩提を弔い、剃髪して庵を結び、光庵禅師を名乗り、子孫代々光庵を名乗ったそうです。源重郎池を造った光庵源重郎も小河の豪農として、代々源重郎を襲名していたそうです。
この神社には、相生市指定有形民俗文化財に指定されている絵馬「神馬図絵馬」が有名です。
 |
 |
| 宇麻志神社の境内右手に見える農村舞台。 | 宇麻志神社拝殿。 |
 |
 |
| 立派な本殿。 | 「神馬図絵馬」享保14(1729)年奉納。 |
松本先生の、相生歴史よもやま話を堪能し、ふるさと相生を振り返る素晴らしい一日になりました。巡検の詳細は、後日、HP等を順次作成していきますのでお待ちください。
相生歴史巡検 Part2(小河)
真広から小河に移動し、まずは小河山観音堂(小河山観音寺)です。平安時代、役小角(えんのおづの)が清水を掬んだ自然石を十一面観世音薩と拝み、後に僧行安が一堂を創建した。これが観音堂の由来だそうです。しかし、鎌倉時代末の、新田義貞の感状山城攻撃の際、堂宇を焼失した。江戸時代の明暦元(1655)年、藩主であった浅野長直公が堂宇を再建しました。そのため、浅野公の御神屋を建て神霊を祀るほか、四十七士の絵馬及び銅像があります。境内には、矢野町出身の有志が建立した大石良雄像もあり、良雄像の裏には、小河観音古墳一号墳の玄室が露出しています。観音堂を出て古山陽道を東へ歩くとすぐに、矢野村道路元標があります。この道路元標とは、大正9(1920)年、旧道路法施行令により市町村の知事の定めるところに各一個ずつ設置された貴重なものです。
 |
 |
 |
| 観音堂の前の道は、古山陽道です。 | 大石良雄像。 | 矢野村道路元標。 |

※源重郎池までは築池碑から5km以上上流にあり、この冬までには写真を撮りに行く予定です。
相生歴史巡検 Part1(真広)
9月25日(日)、秋晴れの快晴の中、今年も松本恵司先生を講師に迎え、相生歴史巡検を行いました。今年度は、相生のまだ行ったことがない所を松本先生にお願いし、矢野町の真広(まひろ)・小河(おうご)を中心に行いました。2年生8名・1年生4名の12名が参加しました。
最初に、真広の真広大神宮社を訪れました。ここは天照大御神を祀っています。時代とともに整備されてきたようで、一番手前の鳥居や灯篭は、皇紀2600年記念として、昭和15(1940)年に建てられました。その横には、昭和17(1917)年に建てられた、大東亜戦争の戦勝祈願碑もありました。

入口鳥居が昭和15(1940)年建造。灯篭の左側に戦勝祈願碑。奥に行くほど古くなります。
次に医王寺(真広薬師堂)です。9世紀、比叡山延暦寺の慈覚大師が、僧恵便・恵聡の草庵の旧跡を訪ね来て、ここに草庵を結び薬師如来を刻み、堂宇を建立したそうです。戦国時代の戦乱と洪水で全てが失われたそうですが、御本尊は東山の荒神社境内に安置されたそうです。現在の薬師堂は瓦に宝暦5(1755)年の銘があります。その同じ頃に建てられたのが鐘楼で、この梵鐘は戦時中に軍に供出されましたが、終戦のため奇跡的に返還されました。ただ、鐘の金質調査のため21もの穴が開き、ボルトで埋められた状態で今もその状態をとどめています。
 |
 |
 |
| 真広薬師堂。昔は旅人の宿泊所。 | 鐘楼の梵鐘に残る戦争の傷跡。21のボルトが! | |