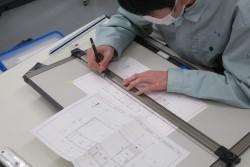環境建設工学科長&愉快な先生たち
環境建設工学科:1年生工業技術基礎 建築の学び
みなさん、お久ぶりです。環境建設工学科の愉快な先生こと「ハッピー」です!(^_-)-☆
しばらくブログに登場しないうちに、季節もすっかり真冬になりましたね。ブログをご覧の皆さんも体調に気をつけましょうね。とくに受験生の方は気を付けてください。
今回は、1年生の授業を紹介します。1年生も残り約3か月で2年生になります。2年生になると環境建設工学科は、「建築類型」と「都市計画類型」に分かれて、専門的な学習がスタートします。
今回は2年生に向けて本格的に建築の学習を始めた、1年生の実習の様子をお伝えします。
2学期から少しずつ建築の学習をスタートしましたが、3学期は、より本格的な図面作成に取り掛かります。今回の第1回目のミッションは……「木造平屋建て住宅の平面図を完成させよ!」です。
「平屋建て」とは「1階建て」のことです。日本の住宅は2階建てが多いですが、1年生には少し作図が難しいので、今回の課題を簡単にしました。
これまで、少しずつ正しい線の引き方、文字や数字の書き方を学習してきた1年生。さすがに1~2学期に比べると手際もよくなりました。大きな成長ですね!1時間目~3時間目まで、ずっと図面を描く授業でしたが、集中して無言で黙々と作業していました。すごい集中力です。
でも、休み時間はみんなで楽しくワイワイとしていましたよ(^^)/
切り替えは大切ですね!

環境建設工学科:栗栖川新宮地区橋梁上部工事 現場見学会
こんにちは!今回は、本校正門前の栗栖川に架かる新橋「龍北橋」の架設を見学しました。
雪がひらひら舞う中での見学・・・橋って、どうやって組み立てられているのでしょう?

約23トンのT形の桁をクレーンで吊り上げ、設置部に移動させます。
そして、両端の支持部で待つ職人さんが声を掛け合いながら設置します。

とても大きな部材を重機で丁寧に動かし、職人さんたちが細かく声を出し合って協力しながら設置する姿を間近に見ることができました。生徒たちは安全第一の慎重な作業やコミュニケーションの大切さを学んだようです。
次に、場所を休憩室に移動して、部材を保護するシースという部品に、願い事を書かせていただきました。『これが、今後50年、100年と安全な橋を支えるのだと思うと緊張する・・!』という生徒もいました。皆の願いが未来に架かる橋となって叶うよう願っています。
その後、PC(プレストレストコンクリート)鋼材と同じ構造のPC板(通称ぴょんぴょん板)の上を歩き、PC構造を体感しました。PCはコンクリートにPC鋼線を通すことで、コンクリートの苦手な引っ張り力を克服した技術です。龍北橋はこの技術を用いた橋であり、PC橋といいます。
最後に、VRで橋桁の架設体験をさせていただきました。VRは、土木工事のような大規模工事をシミュレーションする際にとても役立っており、今後はより一層使われる技術だそうです。
百聞は一見に如かず!なかなか間近で見ることのできない橋梁架設工事を見ることができ、また丁寧な説明をいただき、より詳しく学ぶことができました。生徒たちにとって大変貴重な体験であり、就職や進学を考える一つの機会となったようです。環境建設工学科では、現場見学や企業説明会など、多くの実体験に触れる機会があるので、自分に合った進路選択のきっかけにしてもらいたいと思います。
環境建設工学科:2年 建築専門分科会製図コンクール
皆さん、お久し振りです。
環境建設工学科長の『グリーンT』です。
今回は12月7日に開催された兵庫県建築専門分科会製図コンクールにおいて、本校2年 建築類型の溝口未来が最優秀賞、一色優花が優秀賞に選ばれたので報告いたします!
このコンクールは兵庫県内にある建築系学科を有する学校の生徒たちが参加するもので、毎年12月に開催されます。2年建築類型の生徒17名は11月の初旬から図面を描き始め、約1ヶ月間を費やして図面を仕上げました。図面を汚さず、いかに正確に描き上げるか、数字や文字が丁寧に記入されているか、その他様々な部分が採点されます。今回入賞した二人は普段から丁寧に図面を描き上げることを意識して授業に臨んでいるので、その結果が表れたのかなと思います。
残念ながら入賞を逃した生徒たちも、与えられた期日をしっかりと守り、遅れることなく全員が期日を守って提出してくれました。私自身はそのことが何よりも嬉しいです(^^)
環境建設工学科:生コンクリート工場施設見学
11月に、2年生が生コンクリートプラントである株式会社ヒメコンを訪ねました!社長をはじめ、数十名の従業員の方々が歓迎してくださいました。
まず、3つのグループに分かれ、建設重機体験、コンクリートに関する座学、生コンクリートのスランプ試験を、それぞれ順に体験しました。
建設重機体験では、大型のショベルカーやダンプカーの操縦体験、そしてコンクリートミキサー車の内部まで見せていただきました。
幼い頃の記憶が蘇り、ワクワクする生徒たち・・・大型重機の操縦には憧れますよね!
建設重機体験では、大型のショベルカーやダンプカーの操縦体験、そしてコンクリートミキサー車の内部まで見せていただきました。
幼い頃の記憶が蘇り、ワクワクする生徒たち・・・大型重機の操縦には憧れますよね!

コンクリートに関する座学では、コンクリートの歴史やコンクリートの製造方法について学習しました。
生コンクリートのスランプ試験では、ひとりずつ、全員が体験させていただき、コンクリートの材料の配合と柔らかさの関係や空隙について教わりました。

さらに、希望した生徒には、事務所の内部を案内してくださり、プラント内のミキサーの操作方法について教わりました。パソコンで遠隔操作されており、大きなモニターにはプラント内部が映し出され、安全を確認しながら、コンクリートの硬さについても映像で確認しながら調整しているとのことです。
どの生徒の質問にも丁寧に回答くださり、またどの体験においても、丁寧に教えてくださったので、すべての生徒が、「とてもよい体験をした」、「楽しかった」と目を輝かせていました。
将来について具体的な考えを持つ生徒も居れば、まだ具体的でない生徒もいますが、来年に迫る就職活動や進学活動の一助となれば幸いです。
環境建設工学科:令和5年度 建設業魅力説明会
皆さんこんにちは。環境建設工学科長の「グリーンT」です。
今回は兵庫県 県土整備部 県土企画局主催の建設業育成魅力アップ協議会事業のひとつである「建設業魅力説明会」が行われたので、その様子をお伝えします。今年度も説明講師として株式会社神崎組から卒業生を含めた4名が来校され、環境建設に在籍する2年生を前に建設業のやりがいや魅力、また2024年度問題で建設業界がどのように変わっていくのかなどを説明していただきました。本校の卒業生も沢山採用していただいている企業でもあり、また卒業生が母校に来て在校生に話をしてくれる姿は本当に嬉しいものです。
「あんなに○○だった△△君が本当に立派に・・・」。決して悪い意味ではありませんよ(^^;
やはり社会に出ると顔つきや話し方も変わるもんだな、と改めて感心しました。
講義の内容も工夫していただき、大変分かりやすい説明会となりました。