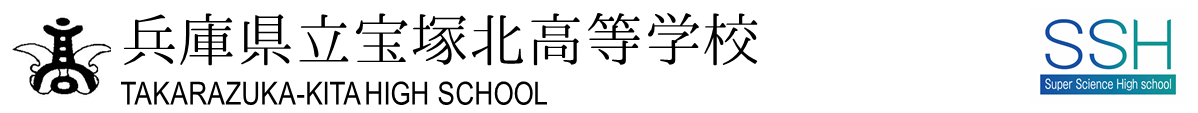北高ダイアリー
40回生修学旅行 2日目(1/22)③
15時半頃、午後のスキー実習が終了しました。
午前中に基本的なトレーニングを行なった初心者コースの人も、リフトに乗って、いよいよ本格的なスキー、スノーボードを体験しました。
また、見学者の生徒たちはホテル周辺で活動を行いました。
午前中はスノーラフティングを行うなど、スキー場周辺で活動をしました。
また、午後はホテル内でキャンドル作り体験をしました。
今から、自由時間を挟んで、その後は楽しみにしている夕食です!!
40回生修学旅行 2日目(1/22)②
各班、スキー実習に取り組んでいます。
少し雪が降っている状況でしたが上級者、中級者、初心者とレベルに分かれて元気に実習を行なっています。
午前中は基本的なところからインストラクターさんに教えて頂いて、徐々に上達しているようです。
その後、昼食はカレーライスをみんなで食べました。
午後も引き続き、スキー実習です。
徐々にレベルアップできるようにがんばります!!
40回生修学旅行 2日目(1/22)①
おはようございます。
修学旅行2日目、無事スタートしました。
元気いっぱい朝食をとることができました。
朝食後、スキーウエアに着替えて、クラスごとに写真撮影、その後スキー学校の開校式を行いました。
団長(校長)挨拶の後、ホテル代表の方、スキー学校代表の方の歓迎のお言葉をいただきました。
その後、生徒代表の2人からの挨拶があり、大いに盛り上げてくれました。
いよいよ今からスキー合宿スタートです。
途中から雪もかなり降ってきていますが、みんな元気に活動を始められています。
40回生修学旅行 1日目(1/21)④
選択体験コースからバスで移動し、いよいよルスツリゾートに到着しました。
到着後、発送した荷物の受け取り、スキーやスノーボードのレンタル品のサイズ合わせ、そして宿泊する部屋に入り、自由時間となりました。
ルスツリゾートは想像以上に大きなホテルだったようで、テンションが上がっている生徒も非常に多く、盛り上がっています。
また、皆さん楽しみにしていた夕食はバイキング形式で、おかわりを何度もしている人も見かけました。
生活班長会議、実習班長会議の後、就寝となります。
明日はいよいよ、スキー、スノーボードです!!
40回生修学旅行 1日目(1/21)③
選択体験コースに分かれて、生徒たち楽しそうです!!
スノーランドは、生徒たち大はしゃぎでスノーラフティングやソリ(チューブスライダー)で遊びました!!たっぷりの雪なので、シンプルに雪合戦も楽しそうです。
カーリング体験は、立つのもやっとな状況で頑張りました。
なんとオリンピックチームがとなりで練習をしています!!
徐々に慣れてきて見違えるように上達しました。
白い恋人パークでは、クッキーに自分たちで可愛くデコレーションしていました。
洞爺湖コースは、熊牧場、火山博物館に訪れました。
今話題の熊の迫力に圧倒されました!!
ノーザンホースパークは、引き馬体験が大人気です!!
ほかにも、ポニーショーを観覧したり、雪遊び、お土産探しと生徒たちエンジョイしています。
このあとはいよいよ、バスでルスツリゾートに移動し、サイズ合わせの後、各自部屋に入って夕食という流れです。
ホテルが楽しみですね!!
40回生修学旅行 1日目(1/21)②
予定通り新千歳空港に到着し、各自空港内で昼食やショッピングを楽しみました。
これからバスで移動して、選択コース体験に入ります。
スノーランド、カーリング、洞爺湖、白い恋人パーク、ノーザンホースパークの5コースに分かれます。
無事どのコースも体験できそうで、楽しみです!!
普通科「リス探」 課外活動インタビュー・施設見学
本校普通科では、探究活動の一環として、さまざまな場所へ足を運び、アンケート調査やインタビューなどに取り組んでいます。
1月16日には、「M-1」をテーマに探究を進めている普通科生徒2名が株式会社朝日放送を訪問し、社員の方ならびにM-1ご担当者の方にインタビューをさせていただきました。
朝日放送では、毎年「M-1グランプリ」の制作・放送が行われています。生徒たちは、その舞台裏や企画の工夫について、熱心に質問を重ねていました。二人ともお笑いが大好きで、インタビュー中は緊張しながらも終始わくわくした表情が見られ、非常に学びの多い時間となりました。
インタビュー後には、夕方のニュース番組「newsおかえり」のスタジオ観覧のほか、副調整室や美術倉庫など、朝日放送内の各施設も見学させていただきました。
本校では3月17日に探究の成果を発表する「探究の日」を予定しています。今回の学びからテーマへの理解をさらに深め、発表に向けて探究を進めてほしいと思います。
最後に、ご多用の中、生徒たちのインタビューを快くお引き受けいただきましたことに、心より感謝申し上げます。
40回生修学旅行 1日目(1/21)①
おはようございます。
いよいよ修学旅行出発です。
保護者の皆様、早朝からご協力いただきまして、ありがとうございました。
おかげさまで、予定通り310名全員が時間通り集合できました!
寒波の影響が心配されましたが、先発のJAL便(1〜3組)、後発のANA便(4〜8組)共に予定通り、伊丹空港を出発しました。
現在、新千歳空港に向けて移動中です。
JAL便(1〜3組)9:45到着予定
ANA便(4〜8組)10:20到着予定
40回生 修学旅行 結団式
40回生2年生は、1/21(水)〜24(土)の3泊4日で北海道(ルスツ・小樽)への修学旅行を実施します。
それに先立ち、本日(1/21)体育館にて結団式を実施しました。
団長の校長先生のお話、引率職員の紹介、最後の諸連絡などを行いました。
修学旅行中の活動については、こちらの「北高ダイアリー」に随時アップしていきます。
ぜひご覧いただければと思います。
中高連携事業(硬式野球)
1月10日(土曜日)昨年度に引き続き、兵庫県立伊丹北高等学校のグラウンドで、伊丹北高校野球部と宝塚北高校野球部の合同事業として、宝塚市内の中学校軟式野球部(御殿山中学校・山手台中学校・宝梅中学校・長尾中学校・中山五月台中学校)を招き、総勢約100名の野球少年、野球少女で、野球の楽しさを満喫しました。当日の早朝は氷点下という極寒でしたが、皆の活気が盛り上がっていくにつれて、気温もどんどん上昇していき、昼前には野球日和となりました。普段は、自分たちの為の練習に集中していますが、この日は、少しでも中学生が高校野球を継続してくれるようにと、生徒たちが練習メニューや声掛けを工夫し、高校野球の楽しさを伝えていました。中学生も非常に満足した様子で、大きな声を出して野球を心から楽しんでいる姿が印象的でした。本校の部員たちも、普段の学校生活では見られない一面も沢山見せてくれて、成長している彼らが逞しく、嬉しく思いました。
本校キャプテンによる、開会の挨拶 ティバッティングのお手伝い
本校マネージャーもお手伝い 本日の流れの説明を聞いています。
元気よくシートノックを受けている様子。 丁寧なゴロ捕球の練習です。
中学生と高校生の集合写真です。
宝塚市すみれガ丘4丁目1-1
Tel:(0797)86-3291 代表
Fax:(0797)86-3292