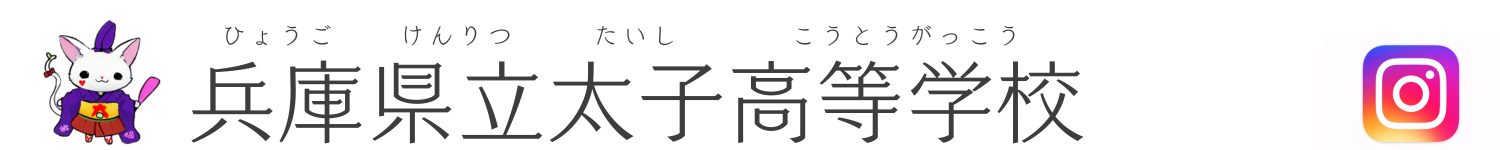ニュース
2 学期終業式 表彰伝達式
| 12月24日(火)、2 学期終業式、表彰伝達式を行いました。 | |
| 2学期終業式 | |
| ○ 校長式辞 | |
| 2 学期始業式に、様々な行事、部活を通して自分の役割を見つけてくださいという話をしました。一つ一つ思い出してみてください。どんな気持ちで何をして、何をしなかったのか。 今日の新聞記事に 『 正しいことをするより、親切なことをしよう 』 と載っていました。 自分では正しいことをしていても、他の人にはあまり温かみを感じられなかったりすることもあります。それは、相手との心の距離にあると思います。心の距離はほんの一瞬で遠くにいってしまいます。相手に想いをうまく伝えられないとき、近くなるようにかけられる言葉はあると思います。 正しい言葉より、親切な心で言葉をかけられると、相手との心の距離を近づけてくれます。 親切なことをすることができるように、成長してください。 冬休み、 親切なことをする ということを考えてみてください。 | |
 | |
| 表彰伝達式 | |
| 女子ソフトテニス部、弓道部、卓球部、男子ソフトテニス部、サッカー部、ダンス部、放送部、美術部、書道部、写真部、校内読書感想文 の表彰伝達式を行いました。 | |
 |  |
| 生徒指導部長訓話 | |
| 今年は、平成から令和に変わりました。どのように過ごしましたか。いろんなことを学ぶことはできましたか。ただ、何となく高校生活を過ごしていませんか。今年の反省をしっかりとして、令和 2 年を迎えてほしいと思います。 今年を振り返ると、自転車での交通事故、苦情をたくさん聞きました。交通ルール、マナーをもう一度見直してほしいと思います。それはあなたたちの命が大切だからです。 年末になると、自分は気をつけていても事故にあう場合があります。もしも、交通事故にあった時には、学校に連絡し、必ず警察に届けてください。 自分を守るために、社会人としてきちんとした対応ができるようになってください。 | |
就職説明会
| 12月23日(月)、2 年次対象の就職説明会を行いました。進路指導部より、就職に関する心構えについて、話をしました。生徒たちは真剣に話を聴いていました。 冬季休業中に、気持ちを引き締め、就職に向けて何をしていけば良いのかをしっかりと考えてくれると思います。 | |
 |  |
クリーン作戦
| 12月19日(木)、全校生徒と全職員で、クリーン作戦を行いました。 | |
| 通学路 、朝日山公園、あすかホール、荒神社、斑鳩寺、石海小学校・幼稚園付近、JR網干駅周辺他の ゴミ拾い、校内グラウンドの草引き、植栽を行いました。 | |
| クリーン作戦の様子 | |
| ○ 各清掃場所へ出発 | ○ 朝日山公園周辺の溝の泥を取っています。 |
 |  |
| ○ 落ち葉を集めています。 | ○ ゴミ袋いっぱいになりました。 |
 |  |
| ○ 花壇作りをしています。 ⇒ | ○ 花壇 完成 |
 |  |
| ○ 鉢植えを作っています。 ⇒ | ○ 完成した鉢植えは生徒玄関前へ |
 |  |
| 通学路である立岡~鵤東、本校~JR網干駅までの県道両側の歩道、また、荒神社、斑鳩寺は、1 年次生でゴミ拾いを行いました。 通学路のゴミは、歩道横の溝にたくさん落ちていて、袋いっぱいに集めることができました。 曇りでとても寒い日でしたが、約 1 時間半、生徒たちは元気に活動し、太子町周辺をきれいにすることができました。 | |
1年次 発災型防災訓練
| 12月19日(木)、1 年次生は発災型防災訓練を行いました。 地域の方にも参加していただき、一緒に活動していただきました。 | |
| 【地震発生、生徒昇降口前集合】 | |
| 学年主任の話 校長先生の話 | |
  | |
| 3 種類の訓練を行いました。 | |
| 【搬送訓練】 | |
| 毛布と竹の棒、またはトレーナー(古着・体操服等)と竹の棒を使ってタンカを作る方法を学び、作ったタンカで人を運ぶ訓練 | |
| ○ 毛布の上に竹の棒を置く | ○ 毛布を三つ折にする |
 |  |
| ○ 作ったタンカを 4人で持ち、グループの1人を運ぶ | |
 |  |
| 【応急救護訓練】 | |
| 新聞紙を折って 『 スリッパ 』 、大きなゴミ袋を切って 『 雨がっぱ 』 を作成する訓練 | |
| ○ 新聞紙の折り方を教わっています。 | ○ スリッパ完成! |
 |  |
| ○ ゴミ袋大をこのように切ります。 | ○ 被ると、雨かっぱ完成! |
 |  |
| 【水防工法訓練】 | |
| 土嚢作りを学び、土嚢積みを行う訓練 | |
| ○ 袋に土を入れる | ○ 袋が破れないように、土の量を考える |
 |  |
| ○ 土を入れたらこぼれないように袋の紐を結ぶ | ○ 土嚢を積み上げる |
 |  |
| 曇りで寒い日でしたが、生徒たちはてきぱきと真剣に訓練に取り組みました。 | |
| 地域の方々には、様々な場面で手助けしていただきました。 | |
| 災害はいつ起こるかわかりません。そのとき、訓練で学んだことを活かして積極的に行動してくれると思います。 | |
芸術鑑賞会
| 12月18日(水)の午後、あすかホールで、芸術鑑賞会を行いました。 『 和太鼓松村組 』 の演奏を聴きました。 日本生まれの和太鼓、アフリカ生まれアメリカ育ちのマリンバ、アンデスの楽器ケーナ、ボリビアの楽器チャランゴなどを融合した新しいサウンドを披露していただきました。 | |
| 【プログラム】 | |
| 1 「碧空」(そらへ) | 碧く澄んだ夢と希望を乗せどこまでも・・・神戸空港をテーマとした楽曲。 |
| 2 「疾風」(はやて) | 大太鼓と桶胴が一陣の風となって、時には静かに、時には厳しくぶつかり合い、 聞く人の心を吹き抜ける。 |
| 3 「花明かり」(はなあかり) | 春の夜の「夜桜」を楽しむ様、月明かりをあびた花びらがきらきらゆれて・・・ |
| 4 『体験コーナー』 | |
| 5 「夏の華」(なつのはな) | 祭りを通して四季をも感じることができる。 人の心を揺さぶる祭りの風景と人々の輝きを表現した華やかな楽曲。 |
| 6 「獅子奮迅」(ししふんじん) | 獅子が凄まじい勢いで奮闘する様を、和太鼓を使って表した楽曲。 |
| 7 「神戸発」(こうべはつ) | 山と海に囲まれた美しい街神戸。そして心の故郷神戸。 人々は夢と希望を持ち、街は活気に溢れる。 |
| 『体験コーナー』 日本の太鼓である和太鼓の歴史、和太鼓 3 種類、「宮太鼓」、「桶胴太鼓」、「締太鼓」の違いについて、 舞台上にある大太鼓は樹齢500年のケヤキの木を繰り抜いて 2 頭の牛の革を張ってつくられていること などを説明していただきました。 その後、代表生徒 6 名は、和太鼓 3 種類と大太鼓の叩き方を教わりました。 生徒の叩く太鼓の音と、お手本で叩かれた太鼓の音は、響き、重みの違いを感じました。 体験コーナーの最後に、会場全員で、太鼓と拍手の三三七拍子をしました。 | |
 | |
| 大太鼓の叩き方 『お手本』 | |
  | |
| 演奏後、代表生徒は、「今日は、私たちのために演奏をしていただきありがとうございました。色々な楽器を使って、様々な情景を表現できることを知りました。とてもかっこよかったです。」とお礼の言葉を述べました。そして、花束を渡しました。 | |
| お礼の言葉 花束贈呈 | |
  | |
| 7 つの演目での和太鼓の音色は、優しい音、強く逞しい音など、様々でした。最後の大きな拍手からも、生徒の心に響く音であったことが伺えました。 | |