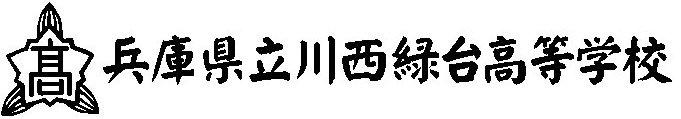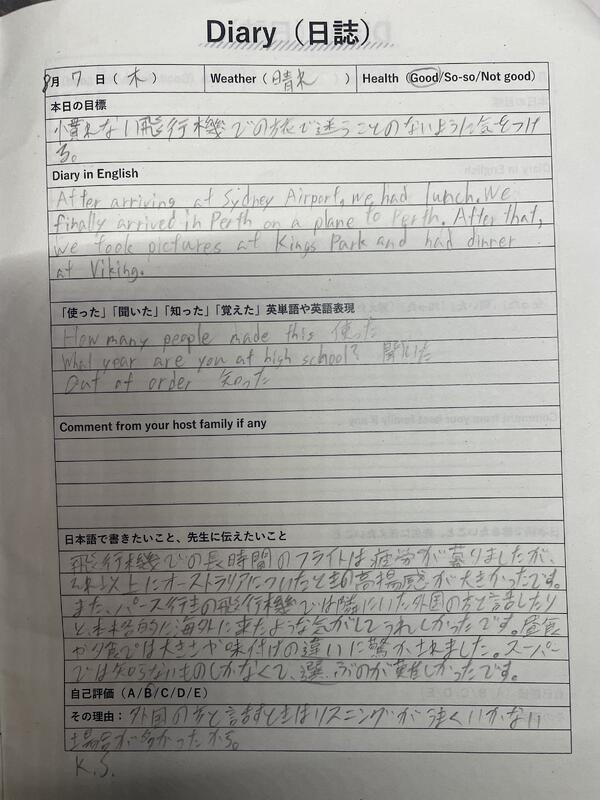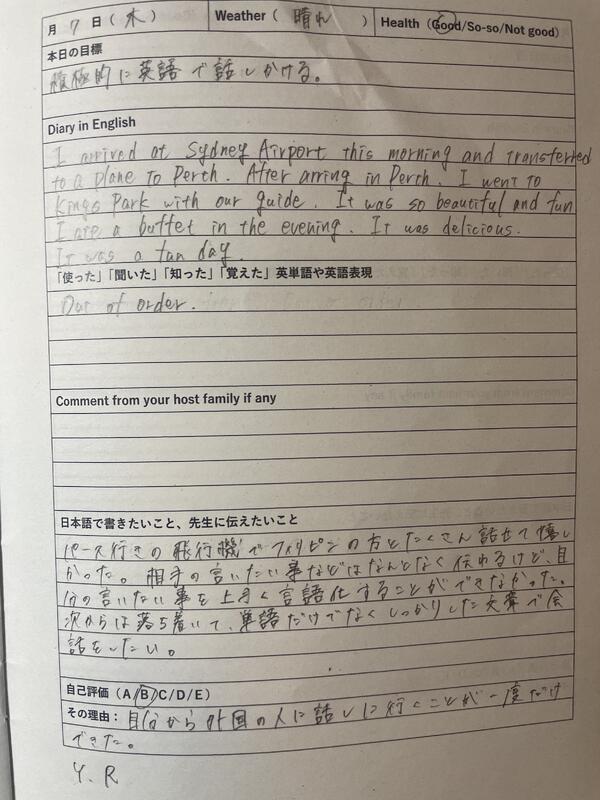ブログ
みどりの風
海外交流プログラム
昨日の振り返りです。
海外交流プログラム
朝ごはんを食べて出発準備をしています。
海外交流プログラム
夕食後、明日の昼食を買いに近くのスーパーマーケットに来ました。会計では慣れないカードでの支払いに苦労もありました。
明日からいよいよ学校とホームステイが始まります。
今日はよく休んで明日に備えます。
海外交流プログラム
長旅と久しぶりのしっかりした食事で、みなさんの食欲も旺盛です。
海外交流プログラム
空港からキングスパークへ行き、様々な植物について学習し、ホテルへ向かいました。
海外交流プログラム
少し迷子になったりしましたが、全員無事にパースに到着しました。
海外交流プログラム
バースに向けて出発します。
海外交流プログラム
シドニーで乗り継ぎます。
海外交流プログラム
搭乗手続きをして、出国準備中です。
海外交流プログラム
本日より、海外交流プログラムでオーストラリアのパースへ向けて出発します。
現地の様子などをこちらのブログで更新していきます。
文理探究科について
文理探究科のパンフレットです。
ぜひご覧ください。
お知らせ
学校情報
〒666-0115
兵庫県川西市向陽台1丁目8
TEL:072-793-0361
FAX:072-793-0520