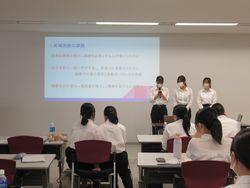看護専攻科トピックス
台湾の康寧大学との交流会
専攻科2年生は、7月の研修旅行で台湾へ行きます。初めて海外に行く生徒もいるため事前の準備として、交流会を実施しました。台湾にある康寧大学の学生とオンラインで繋ぎ、通訳の先生にも入って頂き日本語と台湾語、時折英語も交えながら交流しました。
康寧大学の学生からは学校での実習の様子を英語で紹介してくれました。その中で自分たちとは違う実習室や器具を見て驚いている学生もいました。他国の学生との交流は初めてのため、とても良い経験となりました。龍野北高校の学校紹介では専攻科の紹介の他に、姫路で有名な食べ物、関西圏の観光地やお土産等も入れ、日本の良いところをたくさんアピールしました。お互いの学校や私生活についての質疑応答の時間もあり、学習方法の違い、台湾で流行っているものを知ることができました。
学生は台湾語で挨拶をしたいと交流会前に全員で発音の練習をしており、終了後は「台湾に行くのが楽しみになった」と笑顔で話している学生もいました。
7月の研修旅行でさらに交流が深まり、言語や文化は違いますが同じ看護師を目指す学生として、刺激しあいながら高めあっていける関係になってもらいたいと思います。
臨床看護総論Ⅱ(外部講師)
5月12日から始まる看護臨地実習を前に、専門領域の看護師から講義、ロールプレイやシミュレーションを入れながら、患者様への看護がイメージしやすいように教えていただきました。
15日は姫路北病院に就職した卒業生2名がプロセスレコードの書き方やロールプレイを通して精神科患者様への対応などを教えてくれました。
まず、コミュニケーションの基本を講義していただきました。人は視覚から55%、聴覚から38%、言語から7%の情報を得ており、第一印象が大切であることを再確認しました。また、よく教科書にも出てくる「傾聴」「共感」「受容」について学び、精神科実習だけでなく他の実習でも役立つ講義をしていただきました。
妄想自己紹介や目隠しマスゲームなどを通してコミュニケーションの方法や自分の特性を学びました。これらの授業を通して、専攻科1年生の座学で得た知識が臨地実習で実際に活かせる知識となりました。来てくださった講師の先生方、ありがとうございました。
事例報告会
7か月間続いた看護臨地実習が終了し、事例報告会が行われました。
高校2年生から始まった臨地実習は、新型コロナウイルスの影響で校内での代替実習などを経て、専攻科ではすべての実習を臨地で行うことができました。臨地で実習できる嬉しさとともに不安も大きかったようですが、多くの人々に支えられて成長できました。
今回の発表会では、成人看護学実習Ⅱ(急性期)、成人看護学実習Ⅲ(終末期)、精神看護学実習のうち1つを選択し、自身が行った個別性のある看護を振り返り発表しました。患者様から教えていただいた大切なことは何か、何が学んだことなのか、患者様が伝えたかったことは何かなど、自分の発表内容にそってまとめ、それを相手に伝わるように表現することはとても難しかったようです。しかし、時には投げ出しそうになりながらも一生懸命取り組む姿は、自己研鑽をしようとする学生たちの心を表しているようで頼もしい限りでした。そして、看護科・看護専攻科の5年間の集大成としてふさわしい発表会となりました。
堂々と発表する看護専攻科2年生を羨望や感心のまなざしで聴講する看護専攻科1年生は、3月から始まる老年実習を控えています。先輩たち以上に逞しく成長してくれることを期待しています。


神戸研修
今年度から公衆衛生学の一環として、神戸研修を取り入れました。WHOの医官である茅野先生や海外で看護師として活躍されていた加藤様から、WHOの役割や世界の健康情勢をご講義いただき、その後WHO神戸センターの内部を見学させていただきました。また、午後は兵庫県企画部の山本様から兵庫県の2050年の姿を、保健医療部の阿部様からは兵庫県保健医療計画の概要を講義していただきました。その後グループワークと発表を行いました。
学生からは、「全ての人が平等に適切な質と費用で医療を受けられるように、WHOが中心となり、多様な機関の団体が協力し合っていることが分かった」「国単位ではなく地球を単位としたグローバルな視点で、問題を解決していくために広い視野をもって取り組んでいることが分かった」「日本だけでなく海外でも看護師として働くことができると知り、自分の将来を考えることができた」「地域医療の担い手が減少することが分かった。逼迫するであろう医療現場でも看護師等の医療従事者がその役割を十分に発揮できるように、人々の健康意識を高める看護が必要だと思う」などの感想が聞かれた。

令和6年度 看護専攻科 研修旅行
今年度は、海外での医療の現況を学ぶ機会を設けることができました。受け入れてくださった康寧大學は、台北と台南にキャンパスを構える総合大学で、看護専攻科の学生と同年代の方々が学んでおられます。このような学生達と接する機会は、貴重で、しかも同じ志をもつ学生同士が集うことによって、お互いが良い刺激を受けました。最初はぎこちなかった会話も、スマートフォンなどを活用し、しだいに楽しく話せるようになり、その後の自由時間を一緒に観光等で過ごした班もありました。
また、故宮博物院や九份・十分等の台北から離れた都市も訪れ、台湾の文化を知ることもできました。国内では味わうことのできない体験がたくさんでき、一回り成長した学生になって帰国しました。