カテゴリ:講座の実施報告
10月31日(木)ⅢC1222 (高)商業科教育講座B
〔研修の概要〕
公 開 授 業 ビジネス探究科における課題研究
演習・協議 課題研究や総合的な探究の時間の充実をめざして
・各校における取組に学ぶ
各校における課題研究や総合的な探究の時間の充実に向けて
〔受講者の感想〕
・生徒が主体的に取り組んでいるところが大変素晴らしいと感じました。地域
の企業と連携した取組などを今後取り入れていきたいです。
・課題研究の取組について、1・2年次の授業の上に研究が成り立っていると
感じたので、全体を考えた計画を立てていきたいです。
・探究を進める上で教員のファシリテーターとしての役割が多くなるので、フ
ァシリテーション技術も学んでいきたいと思います。
10月30日(水)ⅢF1302 教員のためのICT基礎講座
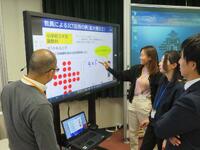
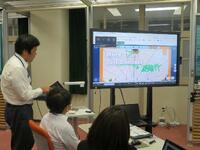
〔研修の概要〕
講義・演習 ICT機器(実物投影機・大型提示装置等)の特性
・一斉学習における教材の提示
演 習 学習効果を高めるための教員によるICTの活用
・教材の作成と活用
〔受講者の感想〕
- 研修の中で改めて、ICTの活用は児童生徒にとって非常に魅力的で、児童生徒のモチベーションを高めるために効果的なツールであると感じることができました。また、他の学校の先生方とも交流する中で、様々な取組やICTの活用事例なども聞くことができ、自校でも活用できればと考えることができました。
- いろいろなICT機器があることは知っていましたが、どこか苦手意識があり使いこなせていないというのが現状です。研修の中で、電子黒板やプロジェクタ、実物投影機(書画カメラ)などを実際に操作したことで、その便利さを改めて実感すると同時に意外と簡単に操作することができると知ることができました。
- 研修を通じて、ICTを活用するメリットやそれぞれのICTの機能を知ることができました。また、それを日々授業等にどのように生かすかといった具体例を考えることができました。その内容を班での話し合い、意見交換し合うことで、新たな発見などもあり、とても良い学びの機会となりました。
10月24日(木) ⅢC1215 (高)情報科教育講座C
〔研修の概要〕
講 義 共通教科「情報」におけるデータの活用・データサイエンス
-記述統計、推測統計を用いた分析-
演 習 データの収集・整理
・オープンデータの整形
演 習 データを活用した問題解決(PPDAC)

〔受講者の感想〕
・「データ活用」をどのように指導すればよいか悩んでいました。今年度、初めて情報Ⅰを指導するときに、活用できそうな題材をたくさん提示していただいたので、今後の指導に生かしていきたいです。
・データ分析で自分でデータを探すということがやはり難しいと感じました。オープンデータを提供しているサイトは多くあるが、そのサイトからどのように取得すればいいか、この点について時間の制限がある中で効率よく探す方法などを考えていきます。
10月11日(金) ⅢC1218 (高)農業科・水産科教育講座B
〔研修の概要〕
講 義 GAPの実践事例から学ぶ
・農業生産過程におけるGAPの考え方
・次世代園芸施設導入事例
株式会社兵庫ネクストファーム 取締役 中村 朋記
演習・協議 GAPの授業実践
・農業科教育に求められるGAPに関する学習展開
〔受講者の感想〕
・GAPによる食品や労働の適切な管理を学ぶことによって、自己管理能力、仕組み化及び
習慣化など自己指導能力を育むことにもつながると感じました。
・日頃から行っている農業科の学習の中に、GAPの考えに沿った内容が含まれているの
で、今後もGAPの考えを意識しながら学習内容をさらに充実させたいと思います。

9月24日(火) ⅢC1202(高)地理歴史科・公民科教育講座A
〔研修の概要〕
講 義 「問い」を中心に構成する学習の展開
ー「問い」を生かした授業づくりの理論と方法-
兵庫教育大学 名誉教授 原田 智仁
演習・協議 探究的な授業を考える
-「問い」を中心に構造化した授業づくり-
〔受講者の感想〕
・「問い」を焦点化し、具体的に設定することで、生徒の理解が深まると分かりました。
生徒の思考を深める発問を今後も考えていきたいです。
・一つの単元が発問の工夫次第で大きく広がることが分かり、教材研究の面白さを改めて
感じました。
・単元を俯瞰的に見ることの重要性を感じました。今後も生徒に身に付けさせたい資質・
能力を意識して、授業展開を考えていきたいです。






