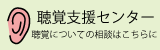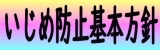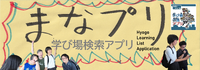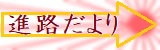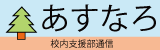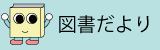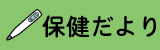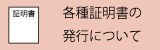学校見学・聴覚障害教育研修会(R7.6.20)
学校・福祉・行政の方々に多数ご参加いただき、「本校の概要とセンター的役割」を知っていただくとともに、校内見学を通じて本校の幼児児童生徒の教育活動の様子を見ていただくいい機会になりました。
研修会では京都府立聾学校舞鶴分校の芦田雅哉首席副校長先生をお招きし、「インクルーシブ教育を目指す聴覚特別支援学校と地域との連携・協議とは」という演題でワークショップを開催いたしました。
姫路医専学校見学会(R7.6.23)
姫路医療専門学校の言語聴覚士養成コースの学生さんが来校し、本校の概要や乳幼児教育相談について学んでいただく良い機会になりました。校内見学では生徒からの質問にも答えていただくなど、本校生徒との交流もできました。是非、将来は難聴子供たちに関わる言語聴覚士として活躍していただけると嬉しいです。
播磨西地区難聴学級担当者会(R7.8.1)
播磨西地域の難聴学級の担任の先生方や各市町の教育委員会の先生方にお集まりいただき、各校の取り組み等について情報共有を行いました。またロジャータッチスクリーンマイクやパスアラウンドマイクの効果的な使い方や自立活動の教材、学年に応じた支援の在り方など、本校からもアドバイスをさせていただいたり、各校の取り組みを知ることで二学期からの指導のヒントになったり、横のつながりをもつ良い機会になりました。
高等学校教職員・養護教諭・コーディネーター等対象難聴理解啓発研修会(R7.8.27)
県内各地から高等学校の先生方にご参加いただき、難聴生徒の困り感や支援の方法等を中心に難聴理解啓発研修会を開催しました。実際に補聴器の音を聞いていただく補聴器体験や自分だけが聞こえにくい状況の難聴体験を通して、普段あまり困り感を出さない難聴生徒のしんどさや聞こえについて考えていただき、英語のリスニングやグループトークにおける配慮の方法についても知っていただくことができました。

保健師対象研修・連携会(R7.9.9)
播磨地域の保健所、健康福祉事務所、保健センター等で、難聴児と関わる方や乳幼児健診を担当する職員の方にご参加いただき、本校での授業の様子や早期教育相談の概要を知っていただきました。言語聴覚士の先生をお招きして難聴・聴覚スクリーニング等に関する研修も行いました。早期からの聴覚障害児への療育の重要性や本校での支援の内容についてお伝えができ、難聴乳幼児の親子支援について本校と連携していただく良い機会となりました。
神戸市立医療センター中央市民病院 玉谷輪子先生ケース会議・講演会(R7.11.14)
神戸市立医療センター中央市民病院の言語聴覚士 玉谷輪子先生をお招きし、「人工内耳の基礎的な内容」についてご講演をいただきました。実音テストやリスニングテストの困り感やその理由、人工内耳装用児の音楽の聞こえ方やSN比による聞こえ方の違いやロジャー等の情報など、実際の聞こえをイメージできる内容でした。