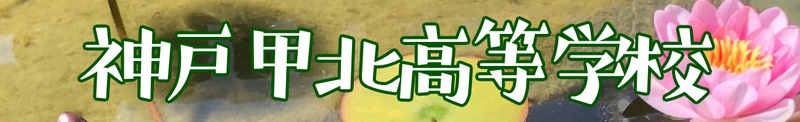チャレンジ44回生Part7
皆さんこんにちは。木下です。
元気に過ごしていますか?
今回のチャレンジ企画は、我が家を今リフォームしていて、大工さんの休みの日を見計らって天井の塗装をしてきました。
我が家は鉄筋コンクリート造のマンションで、リフォームするにあたって天井は2種類の仕上げとしました。
ひとつはマンションのスラブ(コンクリート躯体)をそのままだした躯体現し。もう一つが本来下地に使われる合板をそのまま見せる合板仕上げ。
通常天井の構造は2重の天井になっていて、マンション自体を作り支えているスラブとその下側(部屋から見える側)にクロス仕上げの天井がつきます。
この2重天井にするメリットは、
①スラブと仕上げの天井の間に空間ができるため、電気関係の配線やガス管、給水管、換気扇のダクトなどの目隠しとなりきれいに仕上がる。
②空間ができるため断熱性がある。
③空間ができるため防音・遮音性がある。
そのためほとんどの住宅がこの2重天井構造になっています。
ただ近年ではインダストリアル(工業的)な雰囲気が好まれ、化粧をした天井を抜いた躯体現しの仕上げが増えています。
⇩躯体現し天井

メリットは
①2重天井時より30㎝~50㎝天井高が高くなる。(解放感)
②コンクリート打ちっぱなしっぽくかっこいい。(安藤建築?)
くらいのものです。部屋の体積が増えますので冷暖房効率(光熱費)や騒音に注意しないといけません。
ちなみに床も2重床といって、2重になっている場合が多いです。
次に合板仕上げについてです。
合板とはベニヤ板の事で、木材をかつらむき(料亭の人が大根をむくあのむきかた)して繊維方向を交差させて5枚程度重ね合わせたものです。
サイズは企画が決まっており3×6=910mm×1820mmが統一のサイズです。呼び方は「さぶろく」と言い、昔の長さの単位の尺貫法が建築の世界ではまだ使われています。
ちなみに大工が使うスケールはみんなが使うメートル、センチ以外に尺や寸などが印字されています。
⇩下がセンチ表記、上が尺表記

合板の材はいろいろありますが、メジャーなのがラワンとシナの2種類、他にも檜や桐、OSBなどがあります。今回はラワン材を天井に使いました。
木材は何も塗装していない状態(白木)だと水や汚れや乾燥の影響を受けやすいので、塗装をして保護してあげることが重要です。
塗装方法はウレタン系塗装、ラッカー系塗装、オイル塗装がメジャーですが、今回は水を扱わない部屋にラワン合板仕上げをしていますので、渋柿塗装というちょっと特殊な塗装を行いました。
渋柿塗装は日本古来から使われていた塗装で、渋柿を発酵させて作った塗料です。
他の塗料と違って天然のものなのでアレルギー反応を起こしにくいのと、塗り終えた後、酸化していくため色が段々と濃くなるのがいいところです。(経年変化が楽しめる)
お寺などの日本建築によく使われており、年月が経つと渋い濃いなんともいえない茶色になります。
塗料をまんべんなく、均一に、2度程重ね塗りを行いました。
⇩塗装前

⇓塗装後


まだフローリングやクロスが貼られていない状態でしたので、飛び散っても気にならず気持ちがすごく楽でした。
今後も作業が色々ありますが、休みの日を利用して、ゆっくり進めていきたいと思います。
最後に僕の好きな音楽シリーズでStayという曲のリンクを貼っておきます。
日本より厳しいロックダウンを行っているニュージーランドのアーティストが自宅で収録したものです。
使われている英語は簡単ですので、意味を調べてみるのもいいかもしれません。
ただし、所々で先住民のマオリ語で歌われているところもあるので注意です。
それでは皆さんstay homeでがんばりましょう。KIA KAHA!
https://www.youtube.com/watch?v=rVhd21jpjGQ
元気に過ごしていますか?
今回のチャレンジ企画は、我が家を今リフォームしていて、大工さんの休みの日を見計らって天井の塗装をしてきました。
我が家は鉄筋コンクリート造のマンションで、リフォームするにあたって天井は2種類の仕上げとしました。
ひとつはマンションのスラブ(コンクリート躯体)をそのままだした躯体現し。もう一つが本来下地に使われる合板をそのまま見せる合板仕上げ。
通常天井の構造は2重の天井になっていて、マンション自体を作り支えているスラブとその下側(部屋から見える側)にクロス仕上げの天井がつきます。
この2重天井にするメリットは、
①スラブと仕上げの天井の間に空間ができるため、電気関係の配線やガス管、給水管、換気扇のダクトなどの目隠しとなりきれいに仕上がる。
②空間ができるため断熱性がある。
③空間ができるため防音・遮音性がある。
そのためほとんどの住宅がこの2重天井構造になっています。
ただ近年ではインダストリアル(工業的)な雰囲気が好まれ、化粧をした天井を抜いた躯体現しの仕上げが増えています。
⇩躯体現し天井

メリットは
①2重天井時より30㎝~50㎝天井高が高くなる。(解放感)
②コンクリート打ちっぱなしっぽくかっこいい。(安藤建築?)
くらいのものです。部屋の体積が増えますので冷暖房効率(光熱費)や騒音に注意しないといけません。
ちなみに床も2重床といって、2重になっている場合が多いです。
次に合板仕上げについてです。
合板とはベニヤ板の事で、木材をかつらむき(料亭の人が大根をむくあのむきかた)して繊維方向を交差させて5枚程度重ね合わせたものです。
サイズは企画が決まっており3×6=910mm×1820mmが統一のサイズです。呼び方は「さぶろく」と言い、昔の長さの単位の尺貫法が建築の世界ではまだ使われています。
ちなみに大工が使うスケールはみんなが使うメートル、センチ以外に尺や寸などが印字されています。
⇩下がセンチ表記、上が尺表記

合板の材はいろいろありますが、メジャーなのがラワンとシナの2種類、他にも檜や桐、OSBなどがあります。今回はラワン材を天井に使いました。
木材は何も塗装していない状態(白木)だと水や汚れや乾燥の影響を受けやすいので、塗装をして保護してあげることが重要です。
塗装方法はウレタン系塗装、ラッカー系塗装、オイル塗装がメジャーですが、今回は水を扱わない部屋にラワン合板仕上げをしていますので、渋柿塗装というちょっと特殊な塗装を行いました。
渋柿塗装は日本古来から使われていた塗装で、渋柿を発酵させて作った塗料です。
他の塗料と違って天然のものなのでアレルギー反応を起こしにくいのと、塗り終えた後、酸化していくため色が段々と濃くなるのがいいところです。(経年変化が楽しめる)
お寺などの日本建築によく使われており、年月が経つと渋い濃いなんともいえない茶色になります。
塗料をまんべんなく、均一に、2度程重ね塗りを行いました。
⇩塗装前

⇓塗装後


まだフローリングやクロスが貼られていない状態でしたので、飛び散っても気にならず気持ちがすごく楽でした。
今後も作業が色々ありますが、休みの日を利用して、ゆっくり進めていきたいと思います。
最後に僕の好きな音楽シリーズでStayという曲のリンクを貼っておきます。
日本より厳しいロックダウンを行っているニュージーランドのアーティストが自宅で収録したものです。
使われている英語は簡単ですので、意味を調べてみるのもいいかもしれません。
ただし、所々で先住民のマオリ語で歌われているところもあるので注意です。
それでは皆さんstay homeでがんばりましょう。KIA KAHA!
https://www.youtube.com/watch?v=rVhd21jpjGQ
お知らせ
甲北応援プロジェクト(ふるさと兵庫寄附金)
兵庫県立神戸甲北高等学校
〒651-1144
神戸市北区大脇台9-1
TEL 078(593)7291
FAX 078(593)7293