
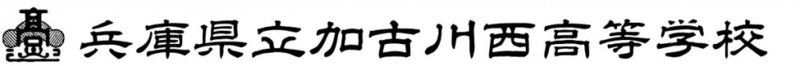


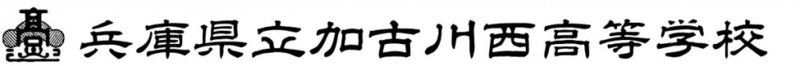
場所:武庫川渓谷福知山線廃線跡・桜の園
コース:JR生瀬駅~武田尾桜の園~JR武田尾駅
今回は、校外自然観察会として、JR生瀬駅から武庫川渓谷に沿って旧福知山線の廃線後を通りJR武田尾駅までのハイキングコースを歩きました。武庫川は、全長65kmの上流は谷中分水界で加古川と繋がり、中流に渓谷がある全国でも珍しい河川です。トンネルと鉄橋の続く旧福知山線廃線跡を歩き、新緑の武庫川渓谷の自然を観察します。また、途中には水上勉の小説「桜守」に描かれた桜博士「笹部新太郎氏」(1887~1978)が桜の研究に心血注いだ演習林「桜の園(亦楽山荘)」があり、山荘を巡り、ヤマザクラなどを観賞しました。
桜の園(亦楽山荘)は面積40ヘクタールで、笹部新太郎氏が1912年(明治45年)兄栄太郎氏から土地を譲り受け、全国から集めた日本古来のサトザクラやヤマザクラの保護、育成のために作った演習林です。中国の詩人・蘇東坡の漢詩『於潛令同年野翁亭』の一節から名づけられた「亦楽山荘(えきらくさんそう)」は演習林をさし、現在では、「桜の園」として親しまれています。91年の生涯の大半を桜に捧げられた笹部氏ですが、特に岐阜県のダムに水没する荘川桜の移植は、世界植林史上稀有の業績として知られています。また、桜に関する資料の収集にも努め、それらのコレクションは、西宮市に寄贈され、現在、財団法人白鹿記念酒造博物館に所蔵されています。最盛期にはヤマザクラ、サトザクラが30種、5,000本以上も植えられていましたが、現在約1千本が残っており、ソメイヨシノは一本もありません。また、ゆかりの荘川ザクラやササベザクラが植樹されています。現在は宝塚市の里山公園となっており、ボランティア「櫻守の会」が手入れを行っています。桜の園には、常緑のアラカシ、ソヨゴ、ツバキ、ヒサカキ、アオキなどが森を覆い、がれ地が多く、エドヒガン、ヤマザクラ、サトザクラのほかに、モミジ、カツラ、イチョウ、キササゲなどが植えられています。
↑武庫川渓谷 ヤマザクラやツツジが点在していました。
↑旧福知山線廃線跡を歩きます。途中トンネルや鉄橋を通ります。長いトンネルの中は真っ暗でライトが必要です。
↑ハイキング道道端のマムシグサ
↑桜の園は、ヤマザクラなどが山を彩っていました。
↑桜の園入口のソメイヨシノ
この日は沢山のハイカーが来ていました。
↑ササベザクラの標識
↑ササベザクラの花
↑桜の園入口の親水公園に植樹されたササベザクラ
↑桜の園入口の記念碑
↑桜の園(亦楽山荘)の案内図
↑ヤマザクラ
↑満開のヤマザクラ とても綺麗でした!ヽ(^o^)丿
↑エドヒガンザクラ
↑亦楽山荘「陽水亭」の案内板
↑亦楽山荘「陽水亭」
↑亦楽山荘「陽水亭」周辺に咲いていたシャガの花
↑JR武田尾駅前のソメイヨシノ
場所:兵庫県立やしろの森公園・小野鴨池公園
今日は、兵庫県生物学会東播磨支部の研修会に参加しました。やしろの森公園の母屋前で、講師の三木自然愛好研究会会長小倉滋先生の説明で「木の中の冬のカミキリムシ」の観察をしました。また、研修会終了後、帰校途中に小野鴨池公園で野鳥などの観察をしました。
↑三木自然愛好研究会会長小倉滋先生のお話を聞きます。昆虫についての興味深いお話がありました。
↑小倉先生が持ってこられたミイデラゴミムシ
棒でつつくと白い煙のような屁を出す
ミイデラゴミムシは、敵に対して悪臭のあるガスなどを吹きつけることと、ガスの噴出のときに鳴る「ぷっ」という音とから、ヘッピリムシ(屁放り虫)と呼ばれる。
外敵からの攻撃を受けると、過酸化水素とヒドロキノンの反応によって生成した、主として水蒸気とベンゾキノンから成る100℃以上の気体を爆発的に噴射する。この高温の気体は尾端の方向を変えることで様々な方向に噴射でき、攻撃を受けた方向に自在に吹きかけることができる。このガスは高温で外敵の、例えばカエルの口の内部に火傷を負わせるのみならず、キノン類はタンパク質と化学反応を起こし、これと結合する性質があるため、外敵の粘膜や皮膚の組織を化学的にも侵す。人間が指でつまんでこの高温のガスを皮膚に浴びせられると、火傷まではいかないが、皮膚の角質のタンパク質とベンゾキノンが反応して褐色の染みができ、悪臭が染み付く。(ウィキペディアから引用)
↑竹を割って、越冬中のカミキリムシを探します。
↑竹の中からベニカミキリの幼虫や成虫が出てきました。
↑エノキの中の越冬中のタマムシの幼虫 でかい!
↑小野鴨池公園のホシハジロ、ヒドリガモ、オオバンとヌートリア 遠くにカルガモやヨシガモがいました。
↑ヌートリア(ネズミ目(齧歯目)ヌートリア科)
南アメリカ原産。日本には本来分布していない外来種で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律では指定第一次指定種に分類されている。
半水性で、池沼や流れの弱い河川の岸辺の土手などに巣穴を掘り、普通は雌雄のペアで生活する。結氷するような寒冷地では、生息できない。主食は、マコモやホテイアオイなどの水生植物の葉や地下茎である。明け方と夕方に活発な採餌のための徘徊行動が見られ、日中は巣穴で休息していることが多い。雌は定住的で、雄に比べて行動範囲は狭い。若い個体は、新しい縄張りを求めて移出する。季節を問わず繁殖し、年に2・3回出産する。妊娠期間は約4か月で、平均5匹の子を産む。十分に発達してから生まれるため、丸1日後には泳げるようになり、3日後くらいには早くも成体と同じ餌を摂り始める。その後、約半年で性成熟する。寿命は5-8年程度。(ウィキペディアから引用)